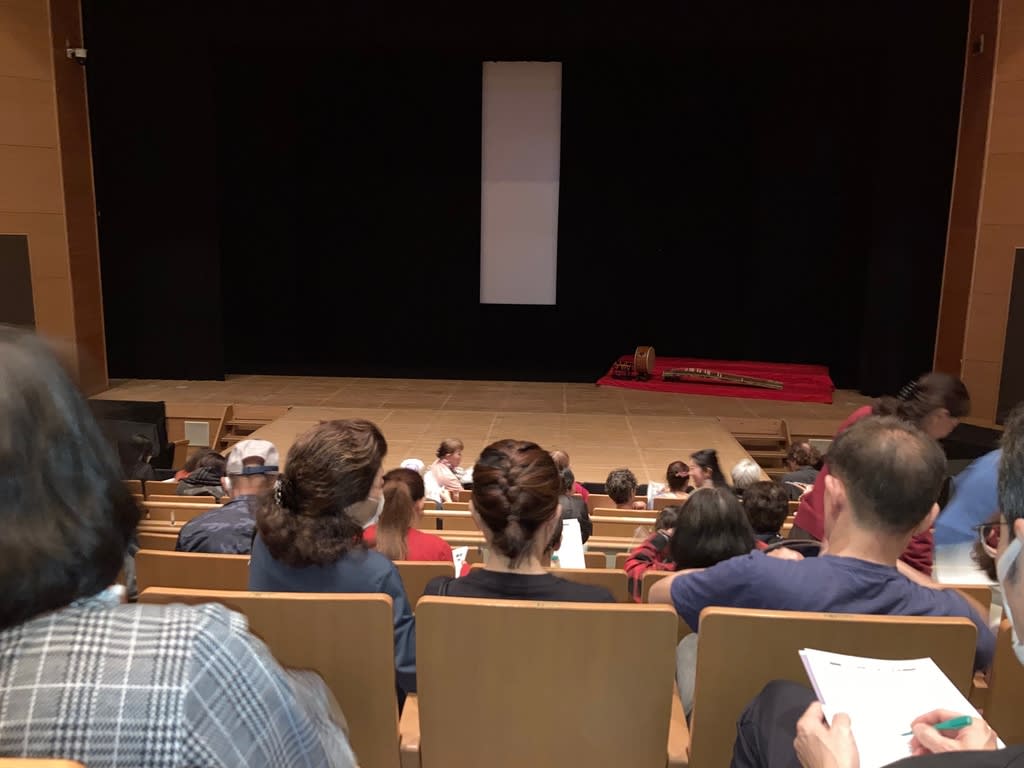(紙面は琉球新報2月28日。この記事を書いた女性芸能担当記者は初歩的なミスが散見される新人記者のようだ。新報は芸能通の記者に担当させないのでしょうか。問題の記事をブログでUPしたいと思いつつ~。記事の中の「沖縄芝居は娯楽でメッセージ性は少ない」との発言は気になります。どの作品にも何らかのメッセージ(テーマ)があります。)なぜ、なはーとのホームページに試演と表記された朗読劇がこんなに高いのか、那覇市 . . . 本文を読む
(つぶやき的に書いています!プロデュースの成功は記念公演にも関わらずチケット代金を3,000円にしたことも一因かもしれません。後援会の皆さんはチケット販売や広告の収益も頑張っていますね。那覇市のなは―と小劇場の試演沖縄芝居翻案劇の朗読会が同じ3,000円です!)「花の代」は以前見た事があったのですが、とても丁寧な舞台で、見応えがありました。チケットはほぼ完売で、行列ができる記念公演になっていました . . . 本文を読む
丁寧な公演で、観客に分かりやすく、優しかったのは、良かった。貧困ゆえに老母と夫婦が生き延びるため、口減らしのために、赤子を土を掘って埋めようとしたら、何と土の中から黄金の羽釜が出てきて、里山の子の家族は救われ、裕福になり、首里王府から褒賞を受ける。そして組踊のパターンに乗っ取って踊ってもどる筋書き。高里風花さんの修士作品の練り直し舞台は、芸大有志の応援と、地元松田区の協力、宜野座村ガラマンホームと . . . 本文を読む
「黄金お羽釜 里川の子」の復元上演です。是非観たいですね。地元出身の高里風花さんが芸大在学中に復元した作品のようです。子供を土に埋めるという物語の流れはちょっと遠野物語のような怖さも秘めているのかと、気になります。組踊では赤子を捨てる場面が出てきます。老いた母親を助けるために赤子を捨てる場面が「大川敵討」に出てきます。赤子は筋書では助かるのですが、赤子より老母を選ぶことの是非も論じられていますね~ . . . 本文を読む
「花の代」は初代「乙姫劇団」の団長、上間郁子さんが、戦前辻遊廓の名妓で評判だったことが思い出されます。女性芸能史は琉球・沖縄の芸能史を鑑みる時、とても重要です。近代芸能の揺籃場所は遊廓です。そして何千人ものジュリと呼ばれた女性たちがいました。彼女たちの水脈は滔々と現代の女性舞踊家にも流れています。それは博論でまとめました。 女性だけの唯一の劇団「うない」には頑張ってほしい。 . . . 本文を読む
大城ナミさんは、2003年にインドのジャイプールで開催されたIFTR国際学会で出会ったインド舞踊の大家でかつPhDの基調講演者を思い起こさせる。研究者であり優れた舞踊家のその方は、直にお話しする機会があり、「日本の着物がタイトで、身体を帯びでしっかり縛っているのは、規律性が高い文化を象徴しているね」と話した。対してインドの民族衣装、サリーはもっと水のように自由だと~、文化の違いをこのように話した . . . 本文を読む
評判の芥川賞を読みたくて、いつものように文藝春秋を購入したが、値段がまた上がっている。 また休刊から32年ぶりの『新沖縄文学』も買った。兼島拓也の戯曲「花売の縁オン(ザ)ライン」が読みたかった。実演の舞台で曖昧だった点が明快になって良かった。ザックリ部分的に読んだ印象は、彼の感性はすごい、と言える。 もう少しじっくり読んで、舞台の記憶をたどりたいが、森川の子の人物造形と、当時の時空、人間関係性、そ . . . 本文を読む
喜納さんは世界的に「花」でよく知られている。特に「ハイサイおじさん」は甲子園の応援曲として、若者にも親しまれている。 昨今、喜納さんの壮大な、神話のような詩編に、全ての武器を花にと訴える詩人の感性のスケールさを感じている。 昨今、若い頃のコンサート動画を観て改めて、喜納昌吉さんの先駆性に驚いた。何気なく聞いていた「ハイサイおじさん」だが、その歌詞を吟味すると、川田さんが紙面で書かれているように、戦 . . . 本文を読む
第二次、第三次保持者の古典から雑踊りまで、演目は8日と重なる踊りもある。地謡は、沖縄タイムス系と琉球新報系に分かれている。 保持者の皆さんはそれぞれに家元や会主、各流派の顔の方々ゆえに、裾野の広い琉舞界のいわばトップである。 それゆえに、会場は幾分緊張感が感じられた。将来この中から人間国宝が誕生するのである。 一人舞は、全てが試される怖い舞台に違いない。全身全霊、それは舞踊家の個々の人生、現況の体 . . . 本文を読む
さし草工房joyで食事して、それから桜を愛でる予定で3人で出発。ナビで全国を走り切ったNさんがご一緒だった。避寒のため2ヶ月ほど那覇に滞在している還暦を過ぎた方。逞しい。 南部は、道路が複雑で、新しいバイパスもあり、慣れないので戸惑ったが無事さし草屋の可愛らしいレストランに着いた。安堵した。小雨は降っていた。暖かいさし草茶を飲みながら、初対面のお喋りを楽しんだ。Nさんを紹介してくださった八代子さん . . . 本文を読む