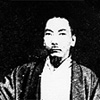研究棟への引きこもりから少し自由になって、観劇をしています。あまりゆらりもできないのですが、「首里城明け渡し」はどうしても見る必要があり、つまり真喜志康忠氏との出会いの中で論考を書かせていただいた思い出の作品でもあり、八木政男さんの演出とテキストの違いによる去年、一昨年の俳優協会の舞台との違い、また真喜志康忠さんたちが演じた舞台との違いなどを見届けたいという思いもありました。
幸い『華風』10月号は丁寧に台本を掲載しています。ほとんど舞台と違うことはありません。さて若者たちのできはどうだったでしょうか?
****************
明治12年3月27日、三条実美の「御達書」を読み上げる松田道之とその前で平服する琉球王府の王族と重臣たちの姿がある。一枚の「御達書」で処分が決定され、尚泰王は長年住み慣れた城を明け渡すことになったのである。まさに史実をなぞった最後の場面を切り取ってできた物語だが、いわば小国琉球が時勢の波に飲まれるその歴史的な場面が写し出されていた。もちろん、戯曲というフィクションだから、歴史をなぞるといっても史実の一部を描いただけである。丁寧に描くとすると、この戯曲はもっとディテールが描かれるべきだし、一幕、二幕で登場した亀川親方や宜湾親方のその後がどうなったかも見えない。若い亀川の息子や娘の許嫁の池城里之子の御朱印を城からとってくるという活躍が未来への希望に感じれないことはないが、戯曲としては、必ずしも優れた作品ではない。菊池寛の作品剽窃もそうだがーー、しかし、今回俳優協会の舞台を見て感じなかった、松田道之の読み上げる御達書、そして津波古親方と松田のやり取りが印象深かった。津波古の言い分に理があると思えたからである。一方的な日本への併合の強制が従来の芝居では割愛されていたセリフによって不合理がぐっと迫ってきたのだ。処分の理由も一方的である。その全文をここに書き記すのは難儀感があるからやめるが、「以上処分の都合もあるから、旧藩書類所蔵の場所は、固く封Xし、同所の物件を、調査または他に持ち出す場合は、内務省官吏の立ち会いを得て取り計らって貰いたい。」など、中央政府樹立に向けて廃藩置県に至った明治政府のその手法は、日本のどの藩でも起こったことなのであろうが、城を明け渡さざるを得なかった時代の趨勢は、たいへんなものだったのだろうと、想像するだけだ。
城を明け渡したのは、確かに琉球だけではなかった。大きな江戸城明渡しもあった。と、ここでため息が出る。時勢という二語が何度も登場する劇である。時勢の波間でゆれる小舟のような琉球の姿である。
松田「しかし、当琉球は、地理気脈は勿論、人種風俗も日本ににて居ります。」
津波古「アジア州や、総てぃ、同ぬ人種どぅ やえーさびらに」
琉球がいかに清国を頼みにしていたか、貿易による利益から恩恵を受けていたかがうかがわれるセリフが登場するのだが、津波古の憂いが明治政府によって即座に解決されたわけではなかったことは歴史が示している。旧慣温存政策がその後明治36年まで続いた。その功罪もある。日清戦争による清の敗北が与えた諦観もまたその後やってきたわけだが、経済の疲弊は続き、1900年まだ明治の時代から海外へ、移民として飛び出さざるを得なかった沖縄である。
仮に他国に併合されずに王国として独自の道を、近代の荒波を、生き延びることができたかどうか、は、すべて推定になってしまう。琉球の伝統(習俗)の軸になった近世の習慣がそのまま推移していたらどうなっていただろうか?日本の教育システムの中で体系的な知の構築がなされていったのは事実である。書き言葉と口語があったが、日本語を取得することによって、それが皇民化教育になっていった負の部分を差し引いても、近代知をそのシステムの中で受容していった(習得していった)66年間でもあった。それを全否定することはできない。近代化は軍国化とパラレルでもあった矛盾(合理・不合理)もあった。近代国家の樹立に邁進した日本は欧米をひたすら真似た。あげくに戦争が続いていった。日露、第一次世界大戦、そして再びシナ事変、韓国の植民地化、そして第二次世界大戦へ突入、敗北(300万人以上の自国の死者、2000万人ともいわれる他国の犠牲者を生み出した)。沖縄戦でも多くの住民が犠牲になった。日本の併合による66年間の結末は無残(悲惨)だった。
琉球が遭遇した歴史は世界史の大きな流れの中の一部だったのかもしれない。もし、併合されなかったら?もし他国に軍隊を送らなかった清が琉球に黄色い軍艦をよこしたら、歴史は変わっていただろうか?
横滑りしてしまった。
舞台は城を追い出された王のことばで幕が降りた。臣下の者たちに泣くなと諭す王のことばは先祖から代々受け継ぎ、幼少の頃から住み慣れた城への愛惜のことばで閉じられる。「くりが 一生ぬ 別り やさやー」
「夜ぅーん 暮りてぃ 行ちゅるんなー。」で一同泣くところで幕。
演技もセリフの味わいも幾分青さが残った。芝居口調の味わいを十分出せなかったは残念だ。メリハリも緩急も必要だが、全体的にテンポが遅かった。丁寧な流れではあった。型の美しさは座っているだけで違うと芝居女優は話した。セリフの調子が同じで、抑揚がまだできていないと語った。首里のあやーめーの言葉使いの抑揚が聞きたかった。亀川里之子の扮装が明るく、親に反抗する少し悪ニーせーの雰囲気で、時勢の流れに添って行く末を見定めたい真面目な若者のイメージがその甘いマスクと髪型ゆえに少し削がれた。きれすぎるイメージである。池城と亀川を入れ替えたらよかったと女優の弁。
実はこの親子の葛藤も菊池寛の作品と類似している。時勢を読み取れない親の世代と時勢の空気を察知している若者の対立が描かれている。それはユニークだ。亀川の清を親とも師とも頼む姿勢はよく演じていた。初老のはずが、もっと年配の老体に見えた。あくまで清を崇拝する心象をよく描いていたと思うが、それでも抑揚などがほしいと芝居のベテランは話した。15分の休憩を挟んだ2時間が短く感じられるほど、舞台は緊密で、薩摩兵の薩摩言葉が抑圧ー被抑圧の構図を見せ、首里城から退出する王を乗せたカゴの登場なと圧巻だった。息抜きになるマルムン的な存在が薩摩兵だったりもした。
しかしいい戯曲は登場人物たちの変化をしっかり書くものだと思うのだが、最後までそれを描ききることがなかったのは戯曲の貧しさかー。ただあまりに強烈な歴史のエポックを描いているゆえに、釘付けになってしまうところがあるね。
舞台美術はお金をかけていて、写実的で奥行があった。
芝居口調(くーちょう)を味わいたい。東江さん、神谷さんなかなか風格ができていた。
ウチナーグチ芝居だということを意識させないぐらい、引き込まれたのは確かだが、俳優協会の舞台が最後に付け加えた尚泰を港で見送りする場面のパノラマ的演劇効果はさすが感極まるところがある。あの場面を付け加えた方がいいね。聞得大君も王妃も登場する場面だ。汽笛が鳴り船が動いていくあの場面は劇的効果が高い!「嘆くなよ臣下命どぅ宝」の名セリフがある。山里永吉のテキストを超えさせるものが役者芝居の面白さだね。
音楽は適度に物語の推移に応じて古典曲が流れ、幕間にも間奏曲(三線曲)が流れ飽きさせなかった。
(うちなーぐちのレッスン)
あねーあいびらん。
あねーあやびらん。
あねーあやびらんの方がもっと丁寧な表現だと女優から教わった。
パノラマ【panorama】
■廃藩置県(ネットからの転載)
これを受けた琉球藩は何の対策もみいだせず、日清両属的な状態を従来通り維持したいと嘆願するのみでした。琉球の支配層の多くは、琉球が日本に帰属するとみずからの地位や身分、財産が危うくなるのではないかと考えていたのです。 |
旧慣温存政策が良かったか、どうか、謝花昇は琉球新報など尚家資本のメディアによっても
その自由民権運動がかなり叩かれたようだ。杣山は、旧慣温存とも兼ねて、士族層が利する
形で奈良原と結託したのではなかったのだろうか?当時の沖縄のエリート層の功罪があるようだ。
近世時代の琉球のシステムが踏襲される近代では、厳しい状況があっただろう。日本に併合された
近代沖縄だが、廃藩置県に関しては、かなりの多くの藩が近代の中央政権化の過程で苦難を強いられた
明治時代でもあった。
「琉球は琉球のもの」ではあった。統治形態に慣れ親しんでいた王府の人々は旧来のシステムを
望んでいたのだろうか?書き言葉を与えられなかった多くの琉球人たちがいた。士族層の特に男子
のみが文字をもっていた。間切り毎に異なる話し言葉が使われていたのである。7,8世紀から女子が
文字をもって表現できた日本の古来からの伝統ははるかに琉球より優れていた。書き言葉を与えられなかった
琉球は、ジェンダーの差別は大きかったのだ、と言えよう。紫式部は朝廷の官女だったゆえに才色兼備だったのか。
一般の婦女子が文字を持たない時代にことばを駆使することができたのは、驚嘆する。歌の歴史がある。
琉球ではおもろがあった。歌い唱えたのだが、文字化したのは士族の男たちだった。
とまた本題からずれるね。記録として残しておきたい。