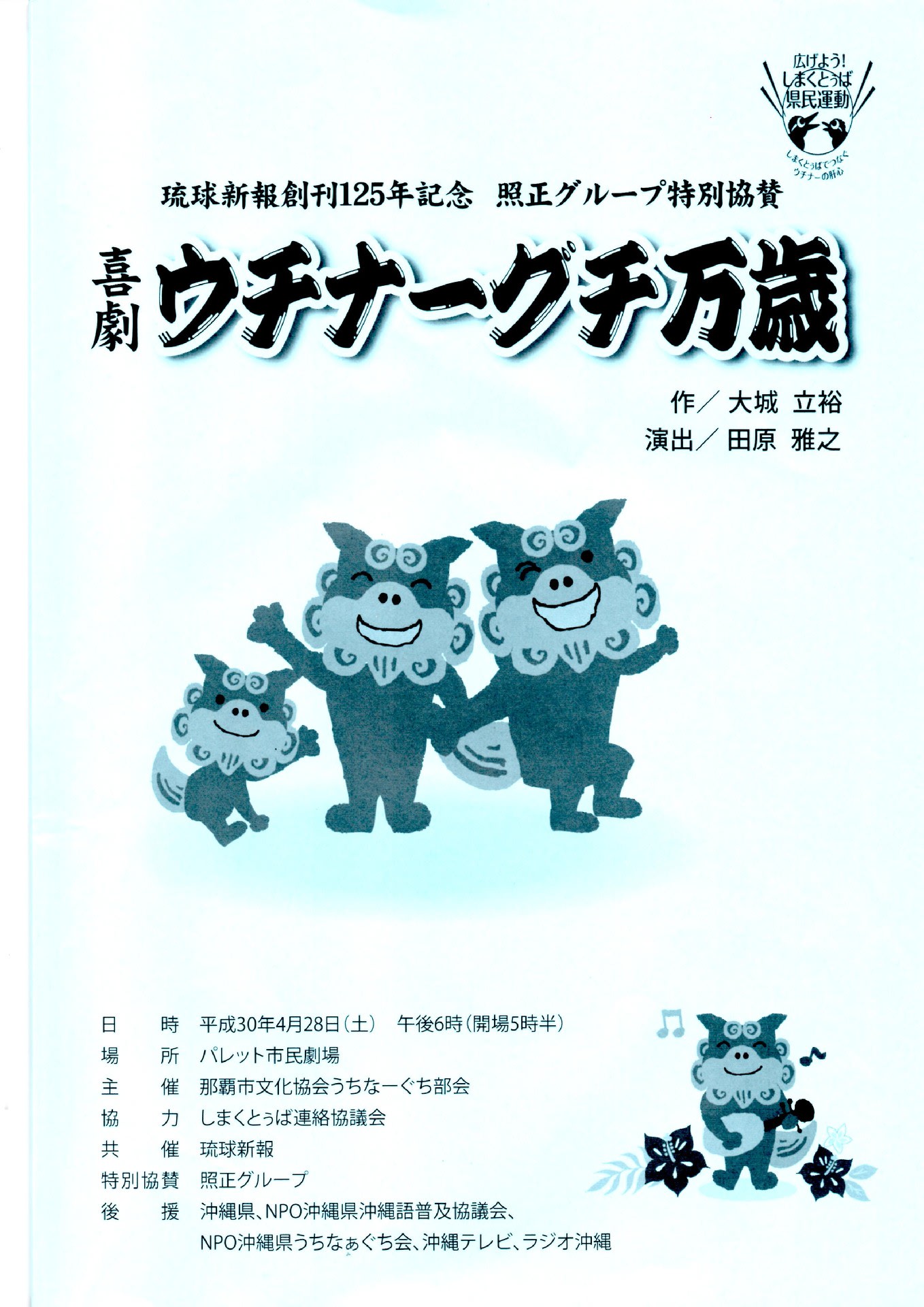

主催は「那覇市文化協会うちなーぐち部会」である。代表の宮平信詳先生のお話、良かったですね!
実は2006年に「しまくとぅばの日」が制定され、その特別企画として喜劇「ウチナーグチ万歳」が上演された時から係わってきた。2006年のパンフレット、また2011年のパンフレットを見たらその痕跡が残っている。プロデューサーの名嘉山秀信さんは、しっかり講演記録を冊子にまとめる企画をしている。いいね。座談会やパネルディスカッションで参加したのだが、できればパンフレットがもっとカラフルであったらいいね。予算を少し上乗せしていいものを残す工夫が次の課題だろうか?
舞台公演には資金がかかる。パレット市民劇場での一回公演で300万円以上の経費がかかるとお聴きした。録画映像が販売されて多くの市民が鑑賞することも可能だが、舞台の臨場感はまた特別である。
今回の公演は2006年、2011年に次ぐ三回目の公演だがそれぞれに時代の流れがあり、今回は特別な味付けがされていたのも事実だ。その良し悪しもある。
2006年の座談会「ウチナーグチは沖縄文化の根」は幸喜良秀、北島角子、松門正秀、新城和博がパネラーで、司会をした。
20111年のパネルディスカッションは基調講演=宮良信詳先生
パネラーは平田大一、宮里朝光、高良勉、大田守邦、山城直吉、船越龍二、司会をした。「琉球新報ホール」
これらの中味の吟味は後ほどやりたい。
まず舞台について。
作者の大城先生が車椅子ではなく杖をつかれてご自分で9階の劇場にお見えになったのには驚いた。先生、お元気になられている。去年の「椎の川」の舞台では車椅子だったので驚いたが、昨日の立ち姿にも驚いた。92歳の作家のエネルギーにただ敬服である。創作を続けておられる。そして舞台も御覧になっている。80代半ばの吉田妙子さんもご一緒だったが、80代の平良進さんにしても、みなさん、ご高齢でキャリアをさらに積まれていて身体芸術の凄さを見せる。芸のバトンを渡している姿は勇敢に見える。拍手!
さて舞台は演出家の意図で現状を説明的に付け加えていた。舞台の中に沖縄芝居の歌劇、「泊阿嘉」や「愛の雨傘」のみならず「武士松武良」やワンドンタリーの舞台も紹介した。沖縄芸能をヤマトグチでやって見せたのも演出の手腕で、安次嶺正美がそれをうまく見せたのは、なるほどで面白かった。どなたもその舞台の再現に取り組んでいない。なるほどと思わせた。「親阿母」のワンドンタリーは何度か見ているが、今回の見せ方はちょっと長かったが、他の泊阿嘉も少々長い感があった。というのは、芝居通の皆さんはよく見ているからだ。あえて「泊阿嘉」を二度も見せたところが、演出意図だがー、なぜ?「愛の雨傘」も二度の見せ方である。差異は面白かった。
*******************************
初演の出演者は7人である。
2006年 2011年 2018年
演出 幸喜良秀 幸喜良秀 田原雅之
語部 大田守邦 平良 進
家長 北村三郎 北村三郎 新垣正弘
長男一郎 具志清健 嘉数道彦 当銘由亮
次男二郎 嘉数道彦 東江祐吉 高宮城実人
三男三郎 濱里太智 金城真次 嘉陽田朝裕
長女松子 座喜味米子 小嶺和佳子 小嶺和佳子
次女竹子 小嶺和佳子 伊良波さゆき 安次嶺正美
三女梅子 金城翔子 山城亜矢乃 大山瑠紗
真境名安興 山本 龍一
伊波普猷 玉那覇真樹
漢那憲和 知名 錦
地謡 徳原清文 花城英樹 花城英樹
************************************
初演は二回公演、再演は一回公演、今回も一回公演である。
田原演出の心意気は真境名、伊波、漢那の3人を登場させているところにも感じられる。彼らの英語廃止を目論んだ校長との争いを印象付けた。また再演から地謡で登用された花城さんを表に出した。地謡が舞台の全体の中で重要な位置づけである。しかし彼の三線の音色がなぜが強く印象に残っていない。表に大きく顔出ししたゆえか、逆に音楽の印象が薄れたイメージがしたのは興味深い。普段は舞台の中にコミットする現代劇にも出ている花城さんである。
ちょっと時間がかかるので端折るが、歌劇のインパクトが大きかった。語りの台詞が女性の語りでそれを平良進さんが重責を担ったのだが、語りの台詞との齟齬が感じられた。後半の宮古語の登場は琉球諸語のあり方への問題提起でよかったが、台詞の明瞭さが問われている。
全体的に語りがキンキン声に聞こえた。首から声が出ているような役者の台詞使いである。熱演だが、声がキンキンで単調に聞こえ、抑揚がないのはなぜか?聞き苦しい台詞廻しである。なぜ?地声など生の暖かさが伝ってきたかもしれない。
マイクのせいだろうか?声の調子になめらかな「耳薬い」の心地よさが感じられなかった。なぜ?面白かった。演出の手も斬新な部分があり、良かった。だけど、心にストーンと落ちてこない何かは何だろう。
今一度ウチナーグチの唱えや会話の調子について、心地よい耳ざわりのいいウチナーグチの口調を追求してほしいと感じた。
詳細をもっと書いてみたいが、出かけないとならない。また続きを書きたいー。
関係者の皆様、ご苦労様!
演技に関して初演のインパクトの大きさが残る。「人類館」のように一人で何役も演じた。三女の金城翔子や長女の座喜味米子の演技が飛びぬけていて、彼女達はその演技で沖縄タイムスの芸術選賞で奨励賞を受賞している。今回、最も目立たなかった次女の役が逆に目立った。演出家の思い入れだが、次女にスポットが当った。安次嶺正美の出番が多かった。それは台詞上ではなく挿入された歌劇による。ハワイのホレホレ節の場面など、もっと演技の差異が見たかった。家(座)長役北島三郎さんの演技の味に新垣正弘さんは熱演だが追いついていないと率直に感じた。家長の役が当銘さんでも良かった。次男、三男高宮城実人や嘉陽田さんも熱演だった。彼らが真境名や伊波、漢那の役を演じても良かったが、新しい演出で若い役者を登用している。
その分展開がスピーディーではなくなった。間延びしていたのは挿入芸が多かったせいでもあろうか。一長一短だ。語り手の平良進さんの語りのスピード感がほしかった。女性言葉の表現、後半の宮古語の投入はなるほどだったが、しまくとぅばへの流れを出したかったのだろうと推測するのだがー。
うちなーぐち万歳!うちなーぐち、どこへ向かっているのだろうか?廃藩置県から今年で138年目である。母語は共通日本語になっている。教科書も日本語だ。うちなーぐちの書き言葉、正書法がまだ確定せず、教育の場でウチナーグチのカリキュラムもまだ取組まれていない。うちなーぐちがしゃべれる人口も減少しつつある。かろうじて沖縄芸能の根がウチナーグチである。
うちなーぐちなくして沖縄芸能は成り立たない。琉歌の8886を基軸に組踊の台詞も成り立っている。古典音楽も琉球舞踊も琉歌と三線が中心である。うちなーぐちが自由にしゃべれる空間作りをしなければだね。ただ琉球諸語の違いを受容しつつそれぞれの地域のことばが飛び交う場所も必要だね。
上記に関して、具体的に前の公演録画映像と比較したいと考えています。脚本も読んで、一度見た舞台をできれば今回の録画映像も見ながら、改めてきちんと対象化したいと考えています。




















にコンタクトよろしくお願いします。
ブログの中味に関する率直な御意見もよろしくお願いします。誤解があるかもしれません。