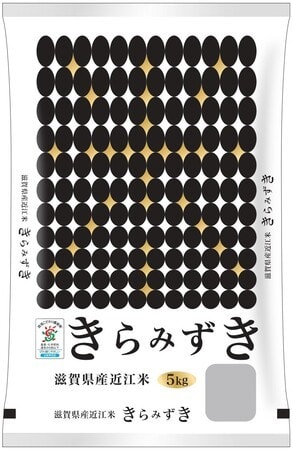「いももち/いもだんご」

主な伝承地域 道内全域
主な使用食材 じゃがいも、片栗粉
歴史・由来・関連行事
「いももち」は、北海道を代表する農産物のじゃがいもを使い、家庭で手軽につくれる郷土料理として浸透している。地域によっては、「いもだんご」とも呼ばれている。北海道以外にも岐阜県、高知県、和歌山県などにも「いももち」が存在するが、地域によって使用する芋の種類やつくり方は異なる。
「いももち」の発祥は、まだ稲作の生産技術が発達していない時代に餅をつくる際、もち米の代わりに当時豊富に生産されていたじゃがいもを使ったことがはじまりといわれている。じゃがいも以外にも、かぼちゃを使うこともあり、いまでも「かぼちゃもち」として伝わっている。
明治の開拓時代、「いももち」は開拓者たちの貴重なエネルギー源として重宝された。その調理の手軽さから庶民的な料理として広まっていった。戦時中や戦後の食糧難の時代にも食べられ、現在は北海道の定番おやつとして、大人から子どもまで広い世代に親しまれる。
食習の機会や時季
じゃがいもは通年手に入るため、1年を通してよく食べられている。子どものおやつとしてもつくられ、現在でも幅広い年齢層からの人気が高い。
飲食方法
つくり方はいたってシンプル。蒸したじゃがいもをつぶして、まんじゅう状にととのえたら、あとは焦げ目が付くまで焼くだけ。主に片栗粉だけを使用するが、片栗粉に小麦粉を適量加えることで口当たりがなめらかになる。じゃがいもの品種は、男爵いもでつくられることが多いが、ほかの品種のじゃがいもでも美味しくつくることができる。食べる際は、バターをのせたり、甘辛く味付けしたごまダレにつけたりと、地域や家庭によってさまざま。また調理法も、チーズを中に入れて焼いたり、揚げたり、汁物にいれたりなど、さまざまなアレンジがある。
保存・継承の取組(伝承者の概要、保存会、SNSの活用、商品化等現代的な取組等について)
手軽にできるおやつや軽食としていまも食べられる。土産店や高速道路のサービスエリアの売店などでも販売され、飲食店でも提供されていることも多い。最近ではスーパーマーケットなどで冷凍の「いももち」や「いももち」の粉も販売されており、家庭でも簡単につくることができる。
*https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/imomochi_hokkaido.html より
通販でも売っている。バリエーションもあり、好みによって選ぶことができる。