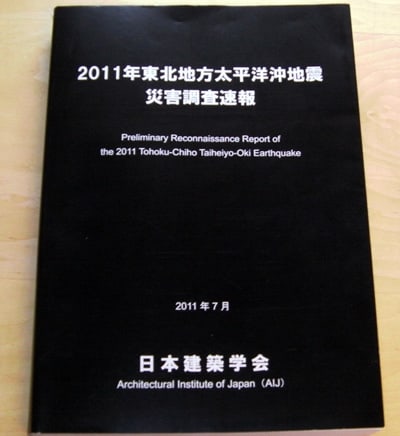災害が発生する度に、日本建築学会は
その概要を調査し、報告書としてまとめ上げる活動を即座に行います。
わたしのような、広告や出版といった世界を経験してきたものからすると、
「学会」という名前を聞いただけで、
すごい世界だなぁと思わざるを得ない。
いわゆる「学会」というものは、
日本学術会議という横断的団体の中に数多くあるけれど、
そのなかでも、もっとも古い部類の歴史を持ち
明治19年からの活動を誇ってきている。
社団法人日本建築学会は,会員相互の協力によって,建築に関する学術・技術・芸術の進歩発達をはかることを目的とする公益法人です。1886年(明治19年)に創立されて以来今日にいたるまで,わが国建築界においてつねに主導的な役割をはたしてきました。
現在,会員は3万5千名余にのぼり,会員の所属は研究教育機関,総合建設業,設計事務所をはじめ,官公庁,公社公団,建築材料・機器メーカー,コンサルタント,学生など多岐にわたっています。
本会は,その目的を達成するため,調査研究の振興,情報の発信と収集,教育と建築文化の振興,業績の表彰,国際交流,提言・要望などの事業を幅広く実施しています。また,全国に9つの支部と36の支所を設けて,それぞれの地域に即した活動を展開しています。
わたしのような経歴のものからすると、
このような自分の活動のマザーのような母艦がきちんと存在する領域への
憧憬を覚えざるを得ない。
自分はこうしたことで世の中にあって貢献していると
実感可能な世界、ということですね。
今回のような未曾有の大災害を経験して、いろいろに取材を進めているのですが、
ある建築設計の関係者から、
「だって、こんな千年に一度の大災害の時点で、自分が建築に関わっていることで、
なにがしかの活動を起こせるというのは、幸せだと思います。」
という言葉を聞いたことがあります。
そういう実感を持てる世界ということに
深く感動を覚えたものでした。
そういうことだったので、この日本建築学会の
「2011年東北太平洋沖地震災害調査報告会」という催事のことを聞いたとき
なんとか、取材しなければと思った次第。
近年、建築から学生たちの関心が薄れてきているのだそうです。
いろいろ、学際的な名称に学部名が変わったりしてきている。
すべての領域でこのような自信喪失状況というのはあるのでしょうか。
出版や広告の世界も、きびしい状況の中で存在基盤は揺らいできている。
これからを支えていく人たちにとって、
あるいは、志を持って仕事をしていこうと考える若い人たちにとって、
このような事態は、どのように感じられているのでしょうか? 不安ですね。
本題としての2011年東北太平洋沖地震災害調査報告については
まったく触れられませんでした(笑)。
でも、調査報告書の重量だけでも1kg以上はありそうな内容ですので
じっくりと読ませていただくしかないのです。
本当は札幌でも9日に報告会はあるのですが、
ちょうど取材も兼ねて、仙台で参加したかったという次第。
さて、これから詳細に読み進めていきたいと思います。
むむむ・・・。