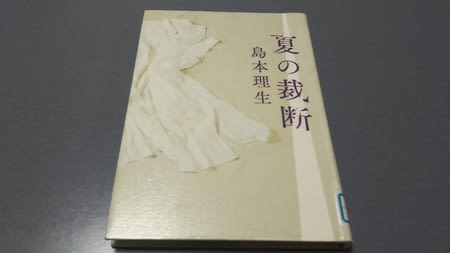
今回ご紹介するのは「夏の裁断」(著:島本理生)です。
-----内容-----
小説家・萱野千紘の前にあらわれた編集者・柴田は悪魔のような男だった―。
過去に性的な傷をかかえる女性作家。
胸苦しいほどの煩悶と、そこからの再生を見事に描いた傑作。
-----感想-----
この作品は昨年の夏、第153回芥川賞の候補になり、又吉直樹さんの「火花」らとともに芥川賞の座を争いました。
私はこの時通算4回目の芥川賞候補になった島本理生さんにぜひこのタイトルを取ってほしいという思い、そして芸人の又吉直樹さんの作品に強豪の島本理生さんが負けるなどあり得ないという思いがありました。
ただブログ友達が高く評価していたことや芸人の名前だけではまず候補にはなれない芥川賞の候補に実際になっていることから「火花」への興味が強まり、昨年7月の芥川賞発表直前に読んでレビューを書いています。
結果、芥川賞を受賞したのは又吉直樹さんの「火花」で、私はこの結果に驚くとともに、直接対決で島本理生さんの作品を破ったことで「火花」への見方が一層高くなりました。
島本理生さんの「夏の裁断」も読んでみようかと思ったのですが、作品がどうやら辛く重い内容のようで読むのが躊躇われました。
近年の私は爽やかな小説のほうが好きで悲しく辛く重い内容の小説は苦手になっていて、そういった作品をよく書く島本理生さんの作品もなかなか読めなくなっていました。
なのでこの時は読むのを見送りました。
3日前の日曜日、図書館で借りる本を選んでいた時にこの作品を見かけ、自然と引き寄せられ手に取ってみました。
しかし辛い内容への拒否感もあり、借りて読んでみるか悩みました。
そこでスマートフォンで「夏の裁断」を検索し、どんな内容なのかを調べてみました。
すると「胸苦しいほどの煩悶と、そこからの再生を見事に描いた傑作。」という言葉が目に留り、主人公が苦しみはするもののそれで終わるのではなく、救いがありそうな気がしました。
なのでついにこの作品を読んでみることにしました。
語り手は萱野(かやの)千紘という29歳の小説家。
冒頭、千紘が帝国ホテルの立食パーティーで柴田という出版社の男性編集者の手をフォークで刺そうとするところから物語が始まります。
柴田によって千紘は精神的にかなり追い詰められていました。
これは数ヶ月前の出来事で、この後すぐに現在の千紘の物語になります。
季節は夏。
千紘は母からの電話で「自炊」を手伝うのを頼まれます。
自炊とは所有している本をデータ化してパソコンなどで見られるようにするため、本の背表紙を裁断し、バラバラになった本のページを全てスキャンしてデータにすることです。
千紘の祖父が2ヶ月前に亡くなり、鎌倉にある祖父の家の整理をしている母は一万冊以上ある蔵書を整理する方法として自炊を考えました。
この母との電話では夕方が深まっていくのを表す良い表現がありました。
そうしている間も、とん、とん、と階段を下りるように夕闇は濃くなっていく。
とん、とん、と階段を下りるようにというのが良いと思いました。
一気に夜になるわけではなく、しかし一歩一歩着実にしんみりと夜に向かっていく様子が上手く表されていると思います。
再び少し柴田との話の回想になります。
柴田は王様のように振る舞っていて驚きました。
振り回された千紘は相当な精神的ダメージを受けたのだと思いました。
再び鎌倉の話になり、千紘が鎌倉の祖父の家に行きます。
このように柴田との回想と鎌倉での話が交互に進んでいきます。
実際に自炊の様子を見た千紘は動揺します。
自炊ということは本を切るのであり、作家である千紘はこれに抵抗があります。
「自分の手足をずたずたにして切り取られるようなものだった。」と胸中で語っています。
それでも千紘は鎌倉の家で自炊を始めます。
二年前、知り合いの作家の授賞式に出席した時に千紘は芙蓉社という出版社の柴田に初めて会いました。
丁寧な口調で話しかけてきたものの異様さの片鱗は見せていました。
事件の後、柴田の上司の人が来ての話し合いで現在はお互いに二度と会わないことになっているのに、千紘は柴田宛に送りはしないものの架空のメールを作っていました。
酷い目に遭ったのに柴田にまだ未練があることが伺われました。
千紘には現在、猪俣君という微妙な関係の人がいます。
イラストレーターの猪俣君と仕事で知り合い、好き好き可愛い大好きなどと言われまくり、きちんと交際もしないまま気が向いたら会う関係になったとのことです。
ずるずると男の人のペースに引き摺り込まれてしまうところに柴田との関係と共通するものがあると思いました。
柴田は相手の女性との関係が親しくなければ礼儀があり、敬語を使い人懐こく話します。
しかし少しでも親しくなると相手の心を傷付け引き裂くのが生き甲斐というようなどうしようもない人間性が姿を現します。
千紘は大学は心理学科で、臨床心理士を目指していたとありました。
図書館でこの本を見かけて借りて読むか悩んでスマホでどんな内容なのかを調べた際、「作家と90分(インタビュアー:瀧井朝世)」という記事で島本理生さんが中学生時代から臨床系の心理学の本を好んで読んでいたとあるのが目に留りました。
なので千紘が心理学を学んでいたのは心理学の本を読んでいた島本さんの経験が反映されていると思いました。
段々と進んでいく柴田との回想の中で、千紘の性格の傾向が気になりました。
異常なまでに心配性で相手のことばかり考えていてもどかしかったです。
そこを柴田につけ込まれてしまいました。
猪俣君が鎌倉の家に押し掛けてきた際、戸惑いながらも千紘は猪俣君を招き入れます。
その際、どうせ、断れないのだ。と自分自身を諦めているのが印象的でした。
柴田の態度が激しく豹変する場面が描かれていました。
千紘はショックを受け、一人になったら震えが込み上げてきて吐きそうにもなっていました。
なにひとつわけが分からなかった。だから私がきっと悪いのだと思った。
「だから私がきっと悪いのだと思った」が非常に印象的で、何一つとして悪くはないのですが千紘はこのように思ってしまいます。
これは人それぞれの考え方の傾向であり、突然理不尽な人間性が襲いかかってきた際、「ふざけるな、お前がおかしいんだろうが」と激怒して応戦する人もいれば理不尽な人間性を正面から受け止めてしまい「そうか、私が悪いのか…」と思う人もいて、千紘の場合は後者の傾向が特に強く出ているということです。
千紘が猪俣君について、「猪俣君はたまに私を気まぐれと表現する。相思相愛じゃない原因を私だけに寄せようとする。」と胸中で語っている場面がありました。
このことから猪俣君に対して冷めていて愛情もないのは明らかです。
にもかかわらず恋人的な付き合いになっているのはずるずると相手の男のペースに引き摺り込まれてしまう千紘の性格と人恋しさもあると思います。
柴田とのことで悩む千紘は大学の時に世話になった教授に相談のメールを送り、会うことになります。
教授が言っていた中で「身の守り方を覚えないと同じことを繰り返すよ」と「本能的に人をコントロールするのが得意な人間はいるんだよ」が印象的でした。
千紘は自分自身の考え方の特徴を知り向き合うことが必要だと思いました。
どんな風に考えやすいのかを客観的に見られるようになり、そんな考えに向かった時に意識して止めてあげられるようにならないと、天性の悪魔とも言うべき柴田のような人に心を破壊されてしまいます。
「それなのにどうして私は、ふりまわすのもいいかげんにして、と怒鳴って今すぐにタクシーを降りることができないのだろう。」
これは「私が悪いのかも」という思いがあるからだと思います。
千紘はどうしても関係を断つ一歩を踏み切ることができません。
やがて、自炊する鎌倉の家から向かって半年ぶりに会った教授が言っていた言葉の中で、次の言葉が一番印象的でした。
「誰にも自分を明け渡さないこと。選別されたり否定される感覚を抱かせる相手は、あなたにとって対等じゃない。自分にとって心地よいものだけを掴むこと」
相手のことばかり考えてしまって自分自身をないがしろにする千紘に対し教授はこの言葉を言い聞かせました。
自分自身をないがしろにしてしまいやすい人が簡単に自分自身を明け渡さないようになれるわけではないですが、少なくとも千紘の心に届く言葉でした。
現在の状況について千紘は「踏みとどまっただけ。」と胸中で語っていましたが、心を破壊されるような酷い目に遭い踏みとどまるのは大変なことです。
私は踏みとどまれて良かったと思います。
千紘の性格は13歳の頃に性的に酷い目に遭ったのが大きく影響しているようでした。
この「過去にあった何らかの事件が大きなトラウマとなり現在の性格に影響を与える」というのはカール・グスタフ・ユング、アルフレッド・アドラーと並ぶ心理学三大巨頭の一人、ジークムント・フロイトの心理学の考え方です。
なので島本理生さんが中学生時代から読んでいたという臨床系の心理学の本はフロイトの心理学の本ではと思いました。
また、島本理生さんはこの作品を最後に純文学小説(芥川賞路線)はもう書かず、これからは既に書いているエンターテイメント小説(直木賞路線)に完全に移るとのことです。
今回「夏の裁断」を読んで、やはり島本理生さんの感性は素晴らしいと思いました。
又吉直樹さんの作品も確かに素晴らしく、私もこれなら芥川賞を取るのも納得とレビューに書いていますが、私にとっての芥川賞といえば島本理生さんのような「感性の小説」なのです。
島本さん最後の純文学小説、私はこの作品に第153回芥川賞を取ってほしかったと思いました。
※「夏の裁断」の文庫での再読感想記事をご覧になる方はこちらをどうぞ。
※「島本理生さんと芥川賞と直木賞 激闘六番勝負」の記事をご覧になる方はこちらをどうぞ。
※図書レビュー館(レビュー記事の作家ごとの一覧)を見る方はこちらをどうぞ。
※図書ランキングはこちらをどうぞ。

















