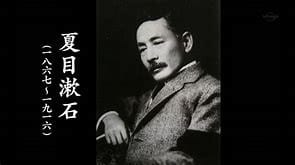湯ざめとは松尾和子の歌のやう 今井杏太郎
季語は「湯ざめ」で冬。はっはっは、こりゃいいや。たしかに、おっしやるとおりです。ちょっと他の歌手でも考えてみたけれど、思い当たらなかった。やはり「松尾和子」が最適だ。句は即興かもしれないが、こういうことは日頃から思ってないと、咄嗟には出てこないものだ。作者は松尾和子全盛期のころから、既に「湯ざめ」を感じていたにちがいない。ムード歌謡と言われた。フランク永井とのデュエット「東京ナイトクラブ」や和田弘とマヒナスターズとの「誰よりも君を愛す」あたりが、代表作だろう。「お座敷小唄」を加えてもいいかな。口先で歌うというのではないが、歌詞内容にさほど思い入れを込めずに歌うのが特長だった。歌詞がどうであれ、行き着く先は甘美で生活臭のない愛の世界と決め込んで、そこに向けて予定調和的に歌い進めるのだから、歌詞との間に妙な感覚的ギャップが生まれてくる。そこがムーディなのであり魅力的なのだが、しかし、このギャップにこだわれば、どこまでいっても中途半端で落ち着かない世界が残されてしまう。まさに「湯ざめ」と同じことで、聴く側の熱が上昇しないままに歌が終わってしまうのだから、なんとなく風邪気味のような心持ちになったりするわけだ。松尾和子が57歳の若さで亡くなったのは1992年、自宅の階段からの転落が、数時間後に死を招いた。その二年ほど前、一度だけ新宿のクラブでステージを見たことがある。「俳句研究」(2006年2月号)所載。(清水哲男)
湯ざめ】 ゆざめ
湯上りに身体を冷やしてしまうこと。冬季は身体が冷えやすく風邪をひいてしますことにもなる。
例句 作者
湯ざめして遥かなるものははるかなり 藤田湘子
湯ざめしてもの食む音の身に返る 岡本 眸
後より掴まるるごと湯ざめせり 古賀まり子
湯ざめして或夜の妻の美しく 鈴木花蓑
わが部屋に湯ざめせし身の灯をともす 中村汀女
化粧ふれば女は湯ざめ知らぬなり 竹下しづの女
つぎつぎに星座のそろふ湯ざめかな 福田甲子雄