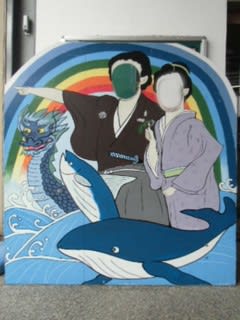高知市春野町甲殿、甲殿川の河口近くに鎮座される「甲殿住吉(こうどのすみよし)神社」。御祭神は『住吉三神』

由緒「文明3年(1471)に建立遷宮、起源はそれよりはるかに古いとされる。土佐十景の一つに数え、社の東には四国八十八箇所三十四番札所種間寺の奥の院・本尾山奥の院がある。」Wikipediaより

三の鳥居前より神域を守護されるのは、天保2年(1831)9月建立の狛犬さん。三角に尖った鼻がかなり特徴のある顔立ちの一対。春野町では一番古い狛犬さんとして、春野町文化財に指定されています。


境内参道には昭和21年(1946)の南海地震の折に、住吉山から崩れ落ちてきた「南海地震の遺し物」とされる大岩が注連縄の結界に守られて鎮座しています。

落石注意の看板

この辺りはは高知市といってもかなり外れた場所。しかも随所に落石注意の看板。時間的なものも含めてそれでもあえて参拝したのは、ご亭主殿が「どうしても見たい!!」と切望した狛犬さんに会うため。

大正8年(1919)の建之ですから、そんなに古いというものではありませんが、
構えの姿勢を崩すことなく、幼い仔狛を背中に乗せています。


愛おしむ様に見返るその表情のなんともおだやかで優しい事・・石工さんは何をモデルにしたんでしょうね。


満足気なご亭主殿が私用に選んでくれていた「岩屋神社:鴛鴦の大槇」は・・石段参道に分け入らないと見られないらしく、危険と言う事で呆気なく終了😩

岩屋神社の向かいに聳える「御菱岩(おいしいわ)」を背景に「申し訳ない」のポーズ😔

参拝日:2013年3月21日