8日(水)。わが家に来てから今日で2524日目を迎え、埼玉高速鉄道の浦和美園駅で6年半にわたって駅長を務めていたイエウサギの「ラビたま」が、18日の”出勤”を最後に引退することになった というニュースを見て感想を述べるモコタロです

ラビたまさん長い間お疲れさまでした 僕はこれからもtoraブログの表紙を飾ります





昨日の夕食は「天ぷら」に初挑戦しました 材料は舞茸、平茸、レンコン、茄子、サツマイモ、海老です。もちろん「天つゆ」も作りました
材料は舞茸、平茸、レンコン、茄子、サツマイモ、海老です。もちろん「天つゆ」も作りました 食材によって揚げる時間が異なるので気を使いましたが、このために買ってきたTANITAのタイマーが役に立ちました
食材によって揚げる時間が異なるので気を使いましたが、このために買ってきたTANITAのタイマーが役に立ちました 娘から「海老は 天ぷらじゃなくて エビフライじゃね?」と鋭い指摘を受けましたが、総合的には”美味しい”と合格点をもらいました
娘から「海老は 天ぷらじゃなくて エビフライじゃね?」と鋭い指摘を受けましたが、総合的には”美味しい”と合格点をもらいました






昨日は「2022 都民芸術フェスティバル」の「オーケストラ・シリーズ」と「室内楽シリーズ」のチケット発売日だったので、日本演奏連盟のWEBサイトにアクセスし、オーケストラ、室内楽とも全公演のチケットを押さえました 受付開始の10時ジャストには繋がりませんでしたが、2分以内に繋がりました
受付開始の10時ジャストには繋がりませんでしたが、2分以内に繋がりました 日程とプログラムは以下の通りです
日程とプログラムは以下の通りです
1⃣オーケストラ・シリーズ 全8公演(会場:東京芸術劇場コンサートホール)
1月19日(水)19時開演 ①ラヴェル「左手のためのピアノ協奏曲」、②同「ピアノ協奏曲」、③ボレロ。粟辻聡指揮 日本フィル、黒岩航紀(ピアノ)。
2月 3日(木)14時開演 ①ウェーバー:歌劇「オベロン」序曲、②ハイドン「チェロ協奏曲第2番」、③ブラームス「交響曲第2番」。齋藤友香理指揮 東京交響楽団、森田啓祐(チェロ)。
2月 8日(火)14時開演 ①ラフマニノフ「ピアノ協奏曲第2番」、②リムスキー・コルサコフ「シェエラザード。角田鋼亮指揮 東京フィル、小山実稚恵(ピアノ)。
2月24日(木)19時開演 ①チャイコフスキー「ヴァイオリン協奏曲」、②ブラームス「交響曲第1番」。高関健指揮 NHK交響楽団、南紫音(ヴァイオリン)。
3月 2日(水)19時開演 ①ドヴォルザーク:序曲「謝肉祭」、②同「ヴァイオリン協奏曲」、③同「交響曲第9番」。阿部加奈子指揮 新日本フィル、北川千紗(ヴァイオリン)。
3月 8日(火)19時開演 ①ベートーヴェン「ピアノ協奏曲第5番」、②ドビュッシー「小組曲」、③ストラヴィンスキー「火の鳥」。和田一樹指揮 東京都交響楽団、若林顕(ピアノ)。
3月16日(水)19時開演 ①モーツアルト:歌劇「後宮からの誘拐」序曲、②ベートーヴェン「ピアノ協奏曲第4番」、③チャイコフスキー「交響曲第5番」。松本宗利音指揮 読売日響、阪田知樹(ピアノ)。
3月17日(木)19時開演 ①シベリウス:交響詩「4つの伝説曲」、②同「ヴァイオリン協奏曲」、③同「交響曲第2番」。藤岡幸夫指揮 東京シティ・フィル、郷古廉(ヴァイオリン)。
2⃣室内楽シリーズ 全2公演(会場:東京文化会館小ホール。各19時開演)
1月31日(月)①ドビュッシー「ヴァイオリン・ソナタ」、②サン=サーンス「ヴァイオリン・ソナタ第1番」、③フランク「ヴァイオリン・ソナタ」。竹澤恭子(ヴァイオリン)、江口玲(ピアノ)。
2月28日(月)①ラヴェル/グリャズノフ「ダフニスとクロエ」第2組曲から「夜明け~パントマイム~全員の踊り」、②バーンスタイン/マスト「ウェストサイドストーリー」より「シンフォニック・ダンス」。ピアノ・デュオ ドゥオール(藤井隆史&白水芳枝)
①ラヴェル「序奏とアレグロ」、②ストラヴィンスキー「ペトルーシュカ」。寺田悦子&渡邊喜久雄(ピアノ)
上記に見る通り、「オーケストラ・シリーズ」の大きな特徴は、指揮者を中心に若手を起用する公演が多いことです 定期演奏会でない「フェスティバル」ならではの人選と言えるでしょう
定期演奏会でない「フェスティバル」ならではの人選と言えるでしょう
なお、チケット代は「コンサート・シリーズ」が A席=4000円、B席=3000円、C席=2000円で、学生は各1000円引きです また「室内楽シリーズ」は全席指定3000円(学生2000円)となっています
また「室内楽シリーズ」は全席指定3000円(学生2000円)となっています






Netfrixで「監視資本主義:デジタル社会がもたらす光と影」(原題:The Social Dilemma)を観ました
フェイスブック、ユーチューブ、インスタグラム、ツイッター、ティックトックなどのソーシャル・ネットワーキング・サービスやスマートフォンが社会に与える影響は計りしれないものがあります これらの情報ツールは先進国アメリカに限らず、フェイクニュース、陰謀論、政府のプロパガンダなどの拡散に大きな役割を果たし、社会の二極化にも大きな影響を及ぼしています
これらの情報ツールは先進国アメリカに限らず、フェイクニュース、陰謀論、政府のプロパガンダなどの拡散に大きな役割を果たし、社会の二極化にも大きな影響を及ぼしています
この作品の特徴は、かつてグーグル、フェイスブックなどで、多くの人により多くの時間をサイト上に滞在させるための「コントロール・ルーム」に在籍していたり、フェイスブックで「いいね!」ボタンを開発した当事者たちが登場し、当時を振り返りながら現在のデジタル環境の危険性を訴えていることです 作中では、中学生を主人公としたドラマが並行して進行していきます
作中では、中学生を主人公としたドラマが並行して進行していきます 1996年以降に生まれたZ世代は「中学生の頃からソーシャルメディアに接してきた初めての世代」です
1996年以降に生まれたZ世代は「中学生の頃からソーシャルメディアに接してきた初めての世代」です ドラマでは四六時中スマホを手放せない若者の悩みや葛藤が描かれています
ドラマでは四六時中スマホを手放せない若者の悩みや葛藤が描かれています
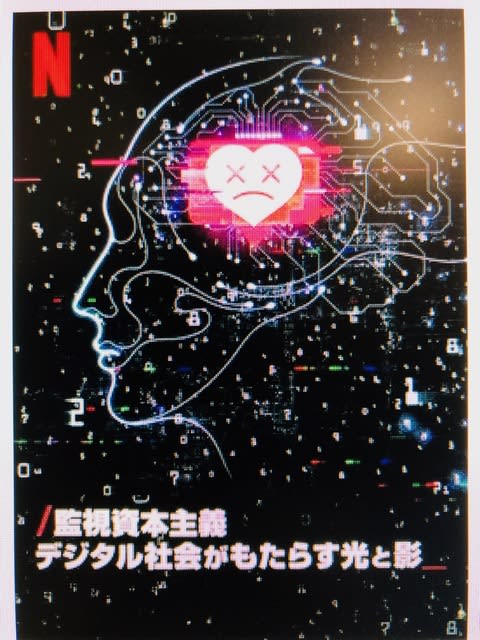
本作では、ソーシャルメディアが普及し始めた2011年と比べ、10代後半の女性の自傷による入院は63%増加、10代前半の女性のそれは183%増加していること、2000年から2009年までの10年間と、2010年から2019年までの10年間で、10代後半の女性の自殺は70%増加、10代前半の女性のそれは151%増加していることをデータで示しています その背景にはソーシャルメディアが社会環境の変化に大きな役割を果たしていた事実があると指摘しています
その背景にはソーシャルメディアが社会環境の変化に大きな役割を果たしていた事実があると指摘しています
グーグルやフェイスブックの元スタッフたちが口々に語っているのは、ソーシャルメディアのサービス提供企業にとって、ユーザーは「顧客」ではなく「商品」だということです 彼らにとって「顧客」とは広告主企業であり、サービス提供によって得られたユーザーの情報(嗜好や行動など)をデータとして収集・解析し、広告に効率よく結びつけることで収益を生み出しているのです
彼らにとって「顧客」とは広告主企業であり、サービス提供によって得られたユーザーの情報(嗜好や行動など)をデータとして収集・解析し、広告に効率よく結びつけることで収益を生み出しているのです 元スタッフたちへのインタビューでとても印象的だったのは、「自分の(10代半ばの)子どもたちにスマホを持たせるか?」との問いに、ほぼ全員から「持たせない」あるいは「1日の時間制限を設けるなど条件付きで持たせる」など消極的な回答が返ってきたことです
元スタッフたちへのインタビューでとても印象的だったのは、「自分の(10代半ばの)子どもたちにスマホを持たせるか?」との問いに、ほぼ全員から「持たせない」あるいは「1日の時間制限を設けるなど条件付きで持たせる」など消極的な回答が返ってきたことです 10代の子どもたちは知らないうちにフェイクニュースをはじめ世論操作や特定の悪意に満ちた思想に誘導される恐れが十分あるからです
10代の子どもたちは知らないうちにフェイクニュースをはじめ世論操作や特定の悪意に満ちた思想に誘導される恐れが十分あるからです これは何も10代の若者たちだけの問題ではありません。彼らは強い口調で訴えます。「(漫然と)お薦め動画を観るな
これは何も10代の若者たちだけの問題ではありません。彼らは強い口調で訴えます。「(漫然と)お薦め動画を観るな 」「スイッチを切れ
」「スイッチを切れ 」と。これは、いい大人が朝から晩までテレビから垂れ流される番組を”はしご”して、1日を漫然と無益に過ごすことに似ています
」と。これは、いい大人が朝から晩までテレビから垂れ流される番組を”はしご”して、1日を漫然と無益に過ごすことに似ています 要は「スマホを観るにしてもテレビを観るにしても、受動的に流されるのではなく、主体性を持って対峙しろ
要は「スマホを観るにしてもテレビを観るにしても、受動的に流されるのではなく、主体性を持って対峙しろ 」と言うことです
」と言うことです
この作品は、とくにZ世代の子どもをお持ちのご家庭にお薦めします



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます