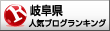能登半島地震については地震発生時の1月1日に簡単に触れさせてもらいました。
その後、大学のサイクリングクラブの同期会グループラインで話題になりました。
なぜなら能登半島は1回生の夏合宿の地だったからです。1972年当時ですから50年以上前になります。

7月22日に穴水に集合し、半島先端を回って輪島、門前、富来、そして津幡で解散というコースでした。
我々のサイクリングクラブは基本テント泊だったので夏合宿はキャンプ場などで泊まることになります。
1日目が珠洲の見附島、2日目が輪島、3日目は富来の砂浜でした。夏真っ盛りでとても暑かった記憶です。
そして私と当時からの親友は1日前に金沢入りし、車も走れる砂浜、千里浜なぎさドライブウェイを通って合流しました。
※今さらですが、上記の地図で羽峠となっているのは羽咋のミスプリですね(-_-;) 今回引きずり出してきて初めて気が付きました。
ここまで思い出話をしてきたのも、私は当時からキャンピングスタイルで移動する体験をしていたことが言いたかったわけです。
就職してのちキャンプしたいなあとは思っていましたが、実際にキャンプできたのは子供が3人に増えたあとの1992年。能登半島の夏合宿からは20年経っていました。ドームテントを自前で買って行ったわけですがね・・・
しかしもっと気軽にキャンプしたいなあとキャンピングカーを買うのが夢になりました。それから2年後の1994年に手に入れることになりました(キャンピングカー参照)。
それから30年弱キャンピングカーの利便性をエンジョイしてきました。
そんななかで災害時の避難生活にキャンピングカーは最適ではないかと思っていました。
だからこういう記事(キャンピングカーが能登集結、キャンピングカーが能登の災害現場で活躍している理由)はさもありなんと思いました。

記事にもあるように
『バッテリー駆動のヒーターがあり、エンジンを切っても暖かい。窓にはカーテンや覆いがある。神戸市から来た保健師の女性(48)は「快適なベッドで疲れがとれるので仕事の効率が上がる。施錠できて安心だし、人目を気にせずに着替えられるのもありがたい」と話す。』
とか
『被災地では宿泊施設が不足して状況で、災害現場を移動しながら、宿泊・食事・トイレ・暖房などを自己完結することができ、被災地に負担をかけない形での災害支援が可能となる』
などのメリットがあるからです。
これに加えて車などで引っ張っていけるキャンピングトレーラーだと駐車場さえあれば簡単に仮設住宅代わりにもできるのでいいなあと思います。実際に長野県からトレーラーハウスが届いたというニュースも流れておりますから。