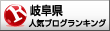95歳の母を施設から自宅に時々連れてくる。子供や孫たちが帰省したとき一緒にご飯を食べるためだ。
そんなときに困るのがバリアフリーにしてない自宅環境。玄関には段差があるし、廊下や階段には手すりなし。お風呂にもトイレにも当然のように手すりはない。それでも応接の椅子がベッドになるので、ふだん寝てばかりいる母の定位置になっている。
そんな母が動くときは廊下の壁に手をついて移動する。しかし具合の悪いのがトイレ。トイレのドアから便器まで壁に手を付いて移動するならいいけれど、置いてある家具やトイレットペーパーかけにつかまって移動するから危なくて仕方ない。

何とかしないと・・・壁に手すりを付けるのが早道だが、素人がいい加減に壁に手すりを付けてもなあ。とりあえず便器周りにパイプ製の『トイレ手すり』を購入して置いてみた。ネットで比較しまくって決めたんだけどね。

自分でも使ってみると、両側に手すりがあるので座るときや立ち上がるときは楽だ。唯一具合悪いのはトイレットペーパーを使うとき。手すりが干渉するので慎重に取り回ししないといけないからだ(-_-;)
便器に座ったり立ち上がったりはこれでいいけど、ここまで辿り着くのがやっぱ危ない。中間の壁にひとつは手すりが必要だと思った。そこで一番小さいやつを調達し、壁に木材が入っている所(釘が打ってある所)を狙って据え付けてみた。

うん、これで便器に辿り着くまでも何とかなる。そして下の写真が最終形。これなら何とかなるだろう(^^;
ってんで、GWに子供たちが帰省したとき、母を自宅に連れてきた。

母に尋ねてみると、「楽だよ」思ったほど感動してくれなかったが、まっいいか。ふたつ合わせて1万円もかからなかったけれど、ネットでさんざん研究して据え付けたんで達成感はあるなあ。ちょっと早い母の日のプレゼントと思えばね。
先日母が95歳の誕生日を迎えた。
あらためて調べると95歳は珍寿だそうだ。そこまで生きるのは珍しいからか、そんな人は珍獣みたいだからか・・・
もう少し調べてみると、それらしい解説サイトがあった。
『なぜ珍かというと、まずはヘンの「王」を 「一、十、一」 に分解する。次に右側のつくりを 「八三」 とみる。これを足せば95になる。』
とのことで、こじつけっぽい。では90歳の卒寿は・・・
『「卒」の略字である「卆」を上下で分けると「九十」と読めることが由来となり、卒寿と呼ばれるようになりました。』
とのことなので五十歩百歩。覚える値打ちもなさそうだ。
その卒寿のときはちゃんとした料亭でセッティングした(母の卒寿祝い)。ところが当日母にボイコットされてしまい、主役抜きだったので残念だった。
そんな母なので心配しつつも当日は関東に住まう弟とその娘とひ孫が来てくれた。今回はどうだろうか。ヒヤヒヤで迎えに行くと無事出席してくれた。やれやれ。

今回予約したレストラン(サガミ)で誕生ケーキを頼んだので母が来てくれて良かったし、料理も結構食べてくれた。
そしてケーキの目の前では、こんなパフォーマンスも披露してくれた。

今回は姪のところに昨年生まれた赤ん坊を見せに来る名目もあり、赤ちゃんを載せるバウンサーがお店にあって安心した。またお子様メニューも充実していた。

よく笑う赤ちゃんと1年ぶりの「姪孫(てっそん)または大姪(おおめい)」たちと会えて楽しい珍寿の会だった。
今まで孫の成長にともなったイベントを何度も記事にしてきた。でも・・・
見直ししてみると『一升餅(いっしょうもち)』について全く触れてないのに気が付いた。
『一升餅』とは・・・私も初体験なので検索すると
一生餅のイベントは、1歳のお誕生日である「初誕生」のお祝いのひとつとしてする伝統行事です。一般的には丸く平たい餅を使って、1歳のお誕生日を祝います。一升餅は、一升(1.8㎏)分の重量があるので1歳のお子さまにとっては、当然ながらとても重いものです。
その理由は
- 一升を通じて食糧に困ることがないように
- 餅のように粘り強く生きていけるように
- のびのびと成長していくように
- 全てが丸く収まるように(丸い形状から)
一般的には「食糧に困ることがないように」という意味合いで一升餅のイベントをすることが多いようです。
といわけで何も知らない私ゃ、女房任せ。肝心の『一升餅』はお袋譲りの電動餅つき機で作成。次にお餅の表面に海苔を切って孫の名前を貼りつける。最後に孫に背負わせるためのリュックサックも自作という涙ぐましい努力を経て当日に臨んだんだわ(^^;
初孫の『一升餅』

背負わせた途端ギャン泣き。親もジジババも、その可愛さにメロメロ。
そしてリュックからお餅を出して餅を踏ませようとしたら、憎々しげに踏み倒すのが面白かった。
2番目の孫の『一升餅』

ご飯を食べてるときは泣いていたのが『一升餅』になったら結構嬉しそうにやってやんの。
重たいお餅を背負わせてもひっくり返ることもなく、前傾姿勢さえやってのけた。
なかなか逞しいわ。
3番目の孫の『一升餅』

何かと初孫(おねえちゃん)のチャチャが入る。
基本的にメッチャ重たいらしく、半泣きで前後どちらかに寄りかかっている。
そんな次女をおねえちゃんはオモチャにしまくっているのが可笑しい。
こんなふうに孫たちは色々と楽しませてくれてます。
昨年行った初孫の七五三。
そして今年は2番目の孫が七五三を迎えた。
2番目の孫のところの氏神さまは日本一有名な国府宮神社なので結婚式も披露宴もここでやった。
七五三の準備で往生こいたのが、ご当人が足袋を怖がって履きたがらないことだった。
しかし母親が草履とセットにして見せると、納得したらしくおとなしく履いてくれたそうだ(^^;

七五三の儀式が始まるまで、待合室にいた。
シーズン中だったこともあって30名くらい集まっていたかな?
儀式で名前を呼ばれるのを聞いていたら地元の稲沢はもとより名古屋、清州、羽島などからも
来ていて、さすが国府宮神社だと感心した。
そのあと、近くの料理屋さんで会食。
最近は座敷でも椅子とテーブルが定着していて、シニアにも優しいスタイルである。

上左側は八寸だろうか。黒豆、アワビ、大根ソーメン?、出汁巻き卵。
右側が子供用の料理。ハンバーグなどお子ちゃまが好きなものが揃っている。
お造りは鯛にマグロ。
茶わん蒸しはチンチンに熱くしてあり、私ゃ大満足\(^o^)/
中身は定番中の定番。稲沢特産のギンナンもちゃんと入っていた。

珍しいフォアグラ。
油で揚げたカンパチの煮物。大根おろしとグリーンピース載せ。

天麩羅もエビ、大葉、カボチャ、サツマイモなど定番メニュー。
最後の味噌汁、漬物、ご飯。
あっ、デザートを写すのを忘れた(^^ゞ
ということで、2番目の孫の七五三が無事終わったのであった。
誕生日は2ヶ月も先だが、子供たちが私の『古稀』のお祝いをやってくれた。
まずは父の享年を2才オーバーできたことが感慨深い。
食事など健康面に気を使ってくれた妻にまずもって感謝したい。

子どもたち3家族が集まると料理などが大変なので、前に取ったことがある仕出し弁当屋さんで調達。
孫たちには食べられそうな別注のものをオーダーして、料理をみんなで楽しんだ。
15時には孫たちにも好評のシフォンケーキを妻に焼いてもらい、作っておいたアイスコーヒーなどでおやつタイム。
そのときに子供たちから記念品を貰った。

京都『SOU・SOU』の布袋。
自転車の絵柄付きである。肩からかける布袋だった。
そう。これは自転車のレースグッズ『サコッシュ』である。
この中にバナナとか行動食を入れレースの最中に補給場所でサッと渡す。
渡された方はサコッシュをたすき掛けにかけて走りながら飲食をするというような使い方をする。
私の場合、カメラ三脚、財布、本などの携帯に重宝している。
今までスタンダードなA4サイズはいくつか持っていたが、小物用のものがなかったのでマジで嬉しかった。
SOU・SOUじたいは結構有名な銘柄らしいのだが、そこでサコッシュというニッチなグッズ。
それも自転車柄はチョーレア!よく探したもんだとビックリした。
もともとサイクリングやロードバイクにルーツのあるアイテムだから専用品なら珍しくもないけどね。
土曜日は初孫の誕生会に行ってきた。
ご覧のように妹ができて、お姉ちゃんがチャチャを入れたり、
二人揃ってカメラ目線にならないのでOK牧場までタイマー撮影10連発せねばならなかった(^_^)

前にスタジオ撮影に行ったときには店の人がぬいぐるみをカメラの上にかざしたりして上手にカメラ目線にしていた。
今回もそれにあやかってアンパンマンのオモチャをカメラ下に置いたりしてみたのだが、
そのうちお姉ちゃんが飽きてしまい変顔をしだしたので途中の1ショットで妥協せざるを得なかった。

ホント子供相手に何かするのは難しい。
日曜日のお昼ごろ、従姉から電話がかかってきました。
「いま○○叔父さん(母の弟)が東京から岐阜の私のところに来てて、伯母さん(母のこと)に会いたいんやそうやけど、今もあの施設にいるの?」
「いや、昨年7月に施設は変ったよ。」
「そこの施設は面会できる?」
「できるようになったよ。親族が面会に行くと刺激になるので行ってあげて。」
ということで、行ってもらいました。
叔父さんとは2年前に私の弟を通じて、母の連絡先を聞いてきました。
「携帯に連絡できない」
とのこと。母は携帯を室内で紛失(後日見つかる)したり、充電切れさせたりして使いこなせないので、3年前に解約したので、連絡できなくなったのでしょう。ただ部屋に固定電話は設置していたので固定電話へかけてもらうよう連絡しました。そののち母に
「○○叔父さんから電話あった?」
と何度か確認してみましたが、
「ないよ。」
の一点張りで、そうこうしてるうちに施設を変わってしまいました。
新しい施設は固定電話は引けないので、連絡事は全て私のところへ来るようになり、
懸案事項だった○○叔父さんの件も直接会いに行って貰えればOK牧場なのです。
その後、面会に行った従姉から連絡があり
「伯母さん喜こんどったよ。叔父さんのことも
『あんた○○ちゃんかね?年取ったねえ。』
と3回言ったし、ちゃんとわかってくれて良かったわ。」
とのことでした。
そう。近い親族が行くと昔話に花が咲くので刺激になって大変良いのです。
後日叔父さんにも連絡を入れ謝意を伝えました。
『あんた○○ちゃんかね?年取ったねえ。』の件も話すと、
「よう、言うわ。自分だってそうやのに(^^;」
と笑ってました。
○○叔父さんに学生時代に世話になったのは弟とうちの娘でしたから二人にも連絡しときました。
今のところ面会は行く人それぞれについて原則週1回なので、変わりばんこに行くと効果的なのです。
また今回の来岐が1週間早かったら、母はペースメーカーの電池替えの入院中で会えなかったので、
まさに奇跡的、これ以上ないグッドタイミングでした。
土曜日に3人目の孫のお宮参りに行ってきた。
上の孫のときは岐阜の長良天神だったが、準備などの都合から息子の住んでいるところの神社に行った。
あいにくの雨模様だったが、お参りが終わるころには小やみになり、記念写真を撮れたので良かった。

本殿の隣には連立鳥居がある稲荷社があり、こちらでも記念写真を撮った。

食事のあとで、フォトスタジオに行き、また写真を撮った。プロの仕事はさすがである。
カメラの上にアンパンマンやミッキーマウスなどのぬいぐるみを置き、
ぬいぐるみに子供の視線を向けさせたり、そのぬいぐるみを子供のところに持ってきたりして、
笑顔にさせ飽きさせないというテクニックを駆使していた。
最近の幼児用品には色々なものがある。特に感心するのが子ども用箸。
リンク先の画像を見てもらうとわかるが、バラバラになりがちな2本の箸を根元で固定し、
さらにそれぞれの箸に輪っかを付け、そこに持ち手の指を差し込むと正しい持ち方になるという優れものだ。

3歳の孫はだいぶ前から使っていたが、
先日来た2歳の孫も画像のように上手に使っていた。
私ゃ、恥ずかしながら正確な箸使いを覚えたのは中学生だか高校生だか?の頃
だったから当時こんなのがあったら苦労しなかったのにと思うばかりである。
食後の儀式といえば先日もアップした「はみがきじょうずかな」である。

2歳児とはいえ、だいぶ自分の意志をハッキリ示すようになったらしく、自宅ではナカナカ言うことを聞かなくなったそうだが、
ジジババの家では猫をかぶってるらしく、ハミガキも自分からやった。そして、
「仕上げはおかあさん」
も素直に従ったので、子供にとって1年は大きな違いになるんだよね。
正確には5ヶ月前のことになりますが、今回の誕生日で父の年を越えることになりました。
長く生きてりゃいいというものでもありませんが、銀行員時代の前半は人生を楽しむより
仕事に忙殺されストレスいっぱい、過労死寸前の生活でした。
そんななか、1泊程度の家族旅行はたまに出かけてました。
40代で本部センター勤務に代わったおかげでネット生活や趣味の自転車を復活できるようになりました。
これならリタイヤしたら、もっと色々なことができるかと楽しみにしていたら体を悪くしたり、コロナ過が
あったりで、いまところ思うようにエンジョイはできていません。
祖父は享年41歳(らしい)。父は68歳。私はできれば88歳を目指したいところです。
しかし元気に動けるのはたぶん70代まででしょうから、これから10年間は頑張って動いていきたいと思っています。
すでに7月なかばのこととなってしまいましたが、長男んちに二人目が宿ったとのことで安産祈願に行くことになりました。
私どもの産土神ともいうべき長良天神さんです。うちの子供たちのお宮参りなどもここで行っており、写真の初孫もお世話になってます。

今年は梅雨明けが早く、真夏の渇水が心配されてましたが、この日は小雨。後日、気象庁から
『じつはまだ梅雨明けしてませんでした』
とのアナウンスがありましたし、線状降水帯などの水害もありましたから例年通りの気候だったようです。
社務所のなかにある待合室で準備、記念写真を撮り、本殿へ。
本殿と社務所がつながっているので雨天でも大丈夫です。

祝詞の文句が違うくらいで『安産祈願』も『七五三』も儀式の内容は同じようなものです。
巫女さんの舞も同じようにありましたしね。
式が終わってから頂いた絵馬に願い事を記し、本殿横に奉納しました。
あれからもう2ヶ月も経っちゃったんだ。月日の経つのは早いものです。
今まで母の部屋は20年間暮らしていたのとチョー物持ちが良いため、同じものが分散してアチコチにある状態だった。
特に郵便物は20年間全部残っていたし、切手は昭和30年代のお年玉切手まである始末だ。
そういう諸々を転居日までに少しづつ運んだ。しかし車(リーフ)に載せられるものは少ないし、
生活しているとタンスや冷蔵庫などの大物は運べない。
それにまずは新しい施設に移るのを優先したかったので、転居日当日は最低限の生活ができるよう
身の回り品だけ持って移動してもらった。
冷たいものが欲しいだろうから冷蔵庫も祖母が使っていたポータブルのものを当座のリリーフとして持って行った。

とりあえず、その日は物珍しいのもあったのか大人しく移ってくれた(~_~)
今まで使っていた中型の冷蔵庫は新しい部屋に持っていきたいし、タンスも数個持って行きたい。
また使わない洗濯機やタンス、ベッドなども運ぶために後日レンタカー(ハイエース)を借りた。
それで不用品を粗大ごみや電化製品リサイクルなどに出しに行き、とりあえずキープする大物は自宅に持ってきた。
中型冷蔵庫と数個のタンスはは母の部屋に運び込んだ。
次に膨大な物品やその他の家具の移動である。
長尺物はキャンピングカーで運ぼうということで3日間かかって大方のものを運び出した。
キャンピングカーのドアから入らないもの(タンス、ロッキングチェアなど)は前にレンタカーで移動してある。
タンスの引き出し一つ分以上あるカセットテープは母の希望で新しい施設に持って行ったが、たぶん聴かないだろうなあ。
他のものは、とりあえず全部自宅に持ってきた。5日目は前の部屋の掃除などをして明け渡しをした。
この間、毎日のように新しい施設にも通い、母の顔を見てきた。3日目までは毎回
「私はいつ帰れるね」
と新しい施設に慣れてない様子だったが、4日目ごろから何も言わなくなった。
おそらく新しい生活に慣れてきたのだろう。
そりゃそうだ。食事も部屋に持ってきてくれるし、お風呂や薬の面倒もみてくれるのだから・・・
しかし、自宅に持ち帰った母の物品には往生こいている。
20年以上ある郵便物、切手や熨斗袋、紙袋などが
4個あるファイルボックスの引き出しあちこちから出てきて呆れるばかりである。
3個までは整理したが、大型のあと1個とその他もろもろの大部分は放置してある。
ボチボチ整理しようと思っているが、先述した発熱外来やコロナの4回目接種など、
諸事が重なり、落ち着いて取り組めない状況が続いている。