川西パレットでの金繕い教室の「器再楽」は、コロナ禍での緊急事態宣言下ですが、会場は使用可とのこと。
しかし、念のため5月中は休止としています。
そんな折、次の繕いの依頼がありました。
武庫之荘のギャラリーRのオーナーさんからです。
今回もフランス製のお皿とのこと。
品物を預かりました。
こんな具合に破損していて。
早速、取り掛かりました。
本格的な接着法では、砥の粉と生漆を使いますが、私は、下地の作業は接着剤で十分だと判断しています。
ズレが生じないように、壊れた個所の接着の手順をよく確認して。
壊れた3つの部分の接着が終わりました。
そして、本体に接着。
裏側の状態です。
少し欠けて無くなっている部分がありますね。
そこには、地の子を混ぜたもので補填して。
紙テープを使ってきちんと固定して。
砥の粉と生漆を使うやり方では、ここまでで約1か月を要すことでしょう。
接着剤が固まった翌日以降に、次の作業です。
紙テープをはがして、余分な接着剤を剃刀の刃を使って、きれいに取り除く作業です。
裏側も。
その仕上げには、水ペーパーを使って。
余分な接着剤が付いている箇所もあったりします。
表側はこんな仕上がりで。
ズレもなくとても綺麗に仕上がりました。
次のステップに進む前に、今回は一工夫。
生漆をテレピンで薄めたものを補修か所にしみこませる作業です。
これで、接着力はさらに増すと思われます。
この後、すぐに余分な生漆をきれいにふき取って、日数をかけて乾燥ですね。
続きます。





























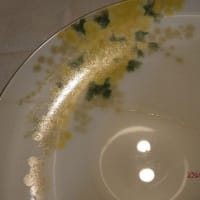


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます