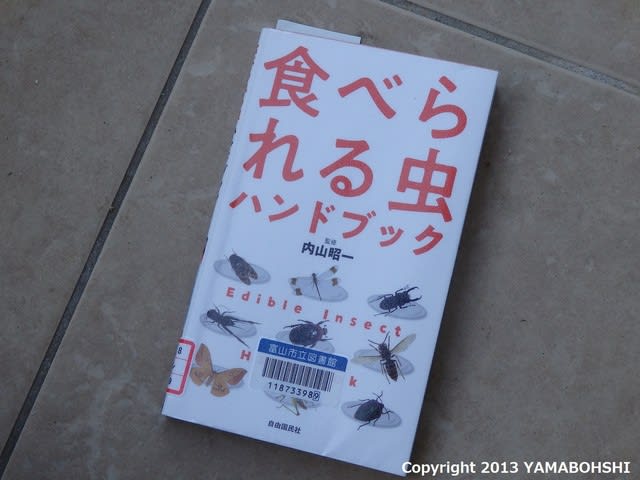早朝、庭に水遣りをしているとき、仕切りの門扉にイラガ(とその時は思っていました)がとまっているのに気付きました。急いでカメラをとりにいき、とりあえず数枚写してから、処分しました。後で映像を見ると、黄色と橙色イラガとは違い、緑色のヒロヘリアオイラガでした。
ヒロヘリアオイラガ(広縁青刺蛾)の前翅は緑色で、その名のように翅の外縁に太い褐色の帯があります。後翅は淡黄色~淡褐色。もともとは中国南部、インド、ジャワ島などに分布している南方系の蛾でしたが、1960年代以降に帰化してから日本中に分布を広げているようです(ウェブサイト『昆虫エクスプローラ/ ヒロヘリアオイラガ』2020/06/05参照)。

《門扉にとまっていたヒロヘリアオイラガ 2020/06/05》

《門扉にとまっていたヒロヘリアオイラガ 2020/06/05》

《門扉にとまっていたヒロヘリアオイラガ 2020/06/05》

《門扉にとまっていたヒロヘリアオイラガ 2020/06/05》

《門扉にとまっていたヒロヘリアオイラガ 2020/06/05》
※ 市立図書館から借りてきた山藤章二著『世間がヘンー山藤章二のずれずれ草ー』を読み終えました。達筆ではありますが、手書き原稿(浄書したもの)をそのまま印刷してあるという体裁の本です。最初はちょっと読みにくくてなかなか読み進められなかったのですが、内容がおもしろく痛快なので、一気に読んでしまいました。
TBSラジオ「荒川強啓デイ・キャッチ!」のラジオコラムの書き下ろしだそうで、「世の中がおかしいのか!?自分がズレているのか、他人がズレているのか!?それが問題だ!!」の全60編。内容は、「仰ぎ見る話」「品という話」「歩く話」「流行語の話」「政治漫画の話」「奉公の話」「九の字の話」「経木の話」「横丁の話」「無駄づかいの話」など。
出版は2000年ですが、著者は1937年生まれだからそのとき73歳前後、今の私とほとんど変わらない年に書かれたものなのだからでしょうか、内容的には「諸手を挙げて賛成」のものばかりです。

《市立図書館から借りてきた山藤章二著『世間がヘンー山藤章二のずれずれ草ー』》