
一雨ごとに、茨城笠間も、田んぼの季節が近づきます。
そんな折、田んぼの縁にて、スコップ持って、笑うおじさんが一名。
一見したところ、どうもやる気のあるお百姓さんには見えないのですが、大丈夫でしょうか。

このお方は、実は、六代目庭師にして陶芸家の、酒井一臣(かずおみ)さんです。
特別に、笠間の陶の歴史に欠かせない、須恵器の窯跡の付近を案内して頂きました。
さっそく、畦の上で、スコップ芸人のポーズ。
ポーズはOKでも、一臣さんの田んぼではありませんから、この後は、口頭での解説です。

笠間市の旧笠間地区の東部、青葉の自宅から3キロほどのところに、窯跡はありました。
西向きの粘土質の土手の斜面を利用して、窯穴を掘り、掘った土で須恵器を制作したらしい。
窯の焚口が、この田んぼだというお話です。
あるご縁で、昔、焚口であることを示す確かな物証を、この地で昔確かめたとのお話。
それは、炭化した粗朶(そだ)でした。

田んぼに立って、向こうの丘を見ながら、いにしえの陶工さんを思います。
須恵器をつくった始まりは、朝鮮半島渡来の専門集団と推察されます。
当時の先端技術、種籾の壺や調理用の甑(こしき)の陶片を見て、若き日の一臣青年は、心打たれました。

丘の上は、栗園になっていました。
雨の中でズームすると、こまめな仕事の薪の山がひとつ。
昔は、薪作りも大仕事でしたから、陶器は、本当に貴重なものでした。
ここにあった窯で焚いたのは、アカマツの薪。
既に当時、このあたりの風景は、アカマツさんだったのです。
半農半陶か、その頃の人々の暮らしぶりにも、想像は尽きません。

時は流れて、今は小川の窯跡です。
良い仕事とは、時代の荒波を超えて、人の心を打つ力があります。
私も素人ながら、昔の尊い仕事のひとかけを、一目拝見したいと思いました。
来月、海外の陶芸ファンの方々が笠間に来られます。
市内の有志の方の依頼で、遠来の皆様の地元メンバーのご案内。
この窯跡が、そのコースになるかどうかは未定ですが、一臣さんと準備中です。

笠間は、大昔から焼物の里でした。
そんな歴史を思いながら、これからの創作と交流の糧にしたい。
一臣さんが、小川でスコップの先を洗い始めましたから、そろそろ時間です。
週の初めから、後ろ姿でごめんなさいの、茨城笠間の春雨でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ふと、ブログランキングに参加しました↓皆様の今日のポチ押しに感謝です。
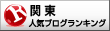 人気ブログランキング
人気ブログランキング  にほんブログ村
にほんブログ村
そんな折、田んぼの縁にて、スコップ持って、笑うおじさんが一名。
一見したところ、どうもやる気のあるお百姓さんには見えないのですが、大丈夫でしょうか。

このお方は、実は、六代目庭師にして陶芸家の、酒井一臣(かずおみ)さんです。
特別に、笠間の陶の歴史に欠かせない、須恵器の窯跡の付近を案内して頂きました。
さっそく、畦の上で、スコップ芸人のポーズ。
ポーズはOKでも、一臣さんの田んぼではありませんから、この後は、口頭での解説です。

笠間市の旧笠間地区の東部、青葉の自宅から3キロほどのところに、窯跡はありました。
西向きの粘土質の土手の斜面を利用して、窯穴を掘り、掘った土で須恵器を制作したらしい。
窯の焚口が、この田んぼだというお話です。
あるご縁で、昔、焚口であることを示す確かな物証を、この地で昔確かめたとのお話。
それは、炭化した粗朶(そだ)でした。

田んぼに立って、向こうの丘を見ながら、いにしえの陶工さんを思います。
須恵器をつくった始まりは、朝鮮半島渡来の専門集団と推察されます。
当時の先端技術、種籾の壺や調理用の甑(こしき)の陶片を見て、若き日の一臣青年は、心打たれました。

丘の上は、栗園になっていました。
雨の中でズームすると、こまめな仕事の薪の山がひとつ。
昔は、薪作りも大仕事でしたから、陶器は、本当に貴重なものでした。
ここにあった窯で焚いたのは、アカマツの薪。
既に当時、このあたりの風景は、アカマツさんだったのです。
半農半陶か、その頃の人々の暮らしぶりにも、想像は尽きません。

時は流れて、今は小川の窯跡です。
良い仕事とは、時代の荒波を超えて、人の心を打つ力があります。
私も素人ながら、昔の尊い仕事のひとかけを、一目拝見したいと思いました。
来月、海外の陶芸ファンの方々が笠間に来られます。
市内の有志の方の依頼で、遠来の皆様の地元メンバーのご案内。
この窯跡が、そのコースになるかどうかは未定ですが、一臣さんと準備中です。

笠間は、大昔から焼物の里でした。
そんな歴史を思いながら、これからの創作と交流の糧にしたい。
一臣さんが、小川でスコップの先を洗い始めましたから、そろそろ時間です。
週の初めから、後ろ姿でごめんなさいの、茨城笠間の春雨でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ふと、ブログランキングに参加しました↓皆様の今日のポチ押しに感謝です。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます