さる高貴な方のお子様が通学する学校で、学級崩壊を思わせるような
出来事があり、マスメディアは「あの名門校でも」と大騒ぎしています。
実は名門私学でもこういった問題は珍しくないのだとか。
「学び」から逃走する子どもたち 佐藤学著 岩波ブックレット
には下記のように書かれています。
公立学校の場合は一つの教室で「学級崩壊」が起きても大きな問題になり
ますが、私立学校の場合は半数近くの教室が「学級崩壊」になっても、
その実態は隠されます。私立学校は少子化の中で経営的に厳しい状況に
置かれていて、ひとたび評判を落とすと廃校にさえなりかねません。
この数年間、「学級崩壊」に苦しむ多くの学校から訪問の依頼を受けましたが、
その多くは私立学校であり、その実態は公立学校とは比較にならないほど深刻
でした。なぜ、私立の小学校高学年と中学校に「学級崩壊」が頻発するのか。
その理由は読者の皆さんに考えていただきたい事柄です。(6~7頁)
また、「学び」からの逃走と学級崩壊の背後には家庭の崩壊に加えて親の態度
の変化があります。たとえば、近年、早期教育に熱心な家庭の子どもが、
小学校高学年から中学校にかけて「学び」を拒絶し、「学び」から逃走する
ケースが増えてきました。「早期教育」や「お受験」に熱中する親や子ども
ほど、いったん成績が芳しくなくなると、早々と絶望し諦める傾向が強いよう
です。小学校の高学年になると、子どもの方も親の利己的な態度に批判的に
なりますから、「学び」からの逃走が一挙に進行します。そのため、大方の
予想に反して、私立の小学校や中学校では、公立の学校以上に授業が成立しない
学級崩壊の状況が拡大していますし、いわゆる底辺校と呼ばれる高校には、
有名な私立幼稚園や私立小学校の卒業生が増える傾向にあります。(42頁)
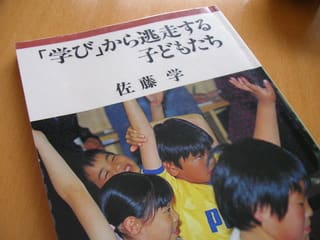
この本を手に取ったのは、PISAの国際学力調査で日本の子どもたちが
順位を下げているというニュースがきっかけでした。
コロ子は、日本の子どもたちは、遊ぶ時間を削って塾通いやお稽古事に
精を出していると思い込んでいたので、PISAの結果がどうにも信じられ
なかったからです。
佐藤氏によると、日本の子どもは家庭での学習時間が極端に短くなり、
読書量も急速に減りつつあるのだそうです。
学ぶことに対するニヒリズム(虚無主義)とシニシズム(冷笑主義)が
子どもたちの間に漂い、それが「学び」からの逃走につながって
いると指摘しています。
講演会のレジュメのような小冊子で、とても読みやすかったです。
出来事があり、マスメディアは「あの名門校でも」と大騒ぎしています。
実は名門私学でもこういった問題は珍しくないのだとか。
「学び」から逃走する子どもたち 佐藤学著 岩波ブックレット
には下記のように書かれています。
公立学校の場合は一つの教室で「学級崩壊」が起きても大きな問題になり
ますが、私立学校の場合は半数近くの教室が「学級崩壊」になっても、
その実態は隠されます。私立学校は少子化の中で経営的に厳しい状況に
置かれていて、ひとたび評判を落とすと廃校にさえなりかねません。
この数年間、「学級崩壊」に苦しむ多くの学校から訪問の依頼を受けましたが、
その多くは私立学校であり、その実態は公立学校とは比較にならないほど深刻
でした。なぜ、私立の小学校高学年と中学校に「学級崩壊」が頻発するのか。
その理由は読者の皆さんに考えていただきたい事柄です。(6~7頁)
また、「学び」からの逃走と学級崩壊の背後には家庭の崩壊に加えて親の態度
の変化があります。たとえば、近年、早期教育に熱心な家庭の子どもが、
小学校高学年から中学校にかけて「学び」を拒絶し、「学び」から逃走する
ケースが増えてきました。「早期教育」や「お受験」に熱中する親や子ども
ほど、いったん成績が芳しくなくなると、早々と絶望し諦める傾向が強いよう
です。小学校の高学年になると、子どもの方も親の利己的な態度に批判的に
なりますから、「学び」からの逃走が一挙に進行します。そのため、大方の
予想に反して、私立の小学校や中学校では、公立の学校以上に授業が成立しない
学級崩壊の状況が拡大していますし、いわゆる底辺校と呼ばれる高校には、
有名な私立幼稚園や私立小学校の卒業生が増える傾向にあります。(42頁)
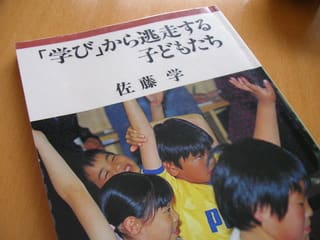
この本を手に取ったのは、PISAの国際学力調査で日本の子どもたちが
順位を下げているというニュースがきっかけでした。
コロ子は、日本の子どもたちは、遊ぶ時間を削って塾通いやお稽古事に
精を出していると思い込んでいたので、PISAの結果がどうにも信じられ
なかったからです。
佐藤氏によると、日本の子どもは家庭での学習時間が極端に短くなり、
読書量も急速に減りつつあるのだそうです。
学ぶことに対するニヒリズム(虚無主義)とシニシズム(冷笑主義)が
子どもたちの間に漂い、それが「学び」からの逃走につながって
いると指摘しています。
講演会のレジュメのような小冊子で、とても読みやすかったです。





















