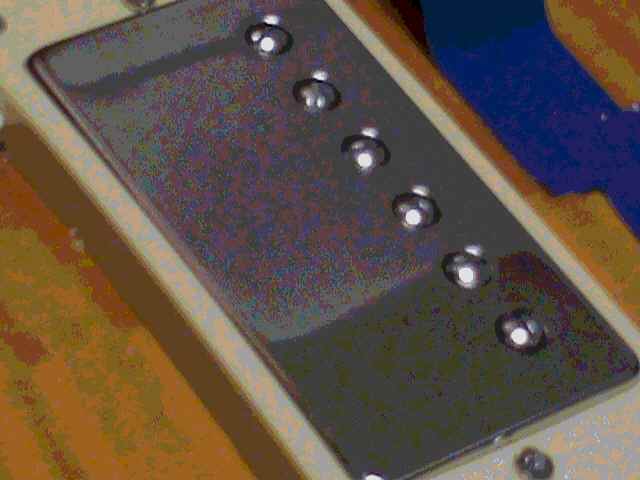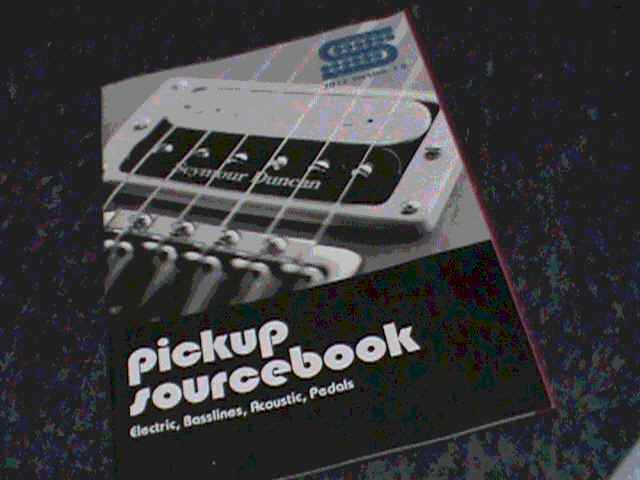今回はピックについてお話したいと思うのだ
読者の皆さんはどんな基準でピックを選んでいるだろうか?
ピックは意外にもギターの音色に大きな影響を与えるマストアイテムなのだ
弾き易さで選ぶというのも良いが音色&音質で選んでみては如何だろうか?
楽器店では大きさ、厚さ、素材など豊富なピックが販売されている
私もかつては色々なメーカーのピックを試してきたのだ
楽器店のお兄さん推奨のピックも一通り試してみたのだ
結果的に現在はこんな感じなのだ

お気に入りはジムダンロップ製のピックなのだ
弦はご存じのとおりダダリオなのだ
ある意味ではどちらも大定番だといえる
定番といわれる製品のメリットは安心感と安定供給にあると考えている
ちょっと変わった人などは他人と違うマニアックな製品を好む傾向があるようだが・・
メーカーは気まぐれなのだ売れない商品は予告なく打ち切りになる可能性もあるのだ
こんなブログを見かけたことがある
「外国で暮らしている友人から定期的に郵送してもらっている弦なんだけど・・」
おそらく、本人はちょっとした自慢のつもりなのだと思う
本人が思うほど読者は羨ましく感じてはいないと思うのだ
一般的なリスナーや読者は曖昧なネタよりも五感に訴えかけるような音を求めているような気がする
マニアックな弦を使ったショボイ演奏よりも定番ダダリオを使ったカッコいい演奏に興味があるような気がする
如何だろうか?
ピック選びの基準は千差万別だが・・
一般論というものはある
一般的に厚めのピックは上級向け
薄いピックは初心者向けという考えが定着している
正しくもあり間違いでもあるのだ
薄いピックが初心者に好まれる事からこんな噂が定着したのだと思う
薄いピックを使えば弦の上を滑らかに動かすことが出来る
特にストロークやカッティングの時に有効だといえる
弦がピックに勝る・・という状態なのだ
多少妙な握り方をしていてもピックの柔軟性がそれを受け止めてくれるのだ
実は中級以上(キャリアだけ?)になってもこの悪癖が抜けない人が多いのだ
慣れとはある意味恐ろしいものなのだ
薄く柔らかいピックしか使えなくなってしまうのだ
もちろんこれでも上手に弾けるというならば特に問題はないが・・・
薄いピックにもデメリットがある
音質に関していえば、強いアタック感が出ないのだ
さらに経済性として消耗が早いのも難点なのだ
一方の厚いピックは捌きが非常に難しい
まったく反らないピックでオルタネイトのアルペジオを演奏するシーンをイメージしていただきたい
薄いピックならば確実に反るようなケースでも厚いピックは反らないのだ
つまり、薄いピックが弦に負けて反る分を指先の逃がしで対処しなくてはならないのだ
厚いピックに慣れた人はとくにこんな面倒臭いことは考えずに弾いていると思う
メリットはその強いアタック感なのだ
特にソロを力強く弾きたい・・と思っている人は必須なのだ
最強の組み合わせは太い弦と厚いピックなのだ
まさにレスポールの定番なのだ

私も色々と試してみたのだが・・・
私の場合、ソロでは間違いなく厚いピックが好みなのだ

しかしながらカッティングになると話は別なのだ
もう少し、薄いピックの方が音に切れが増すように感じられる
実際、演奏性も向上するような気がするのだ

最近はストラトマスターであるChar氏の影響で昔ながらの三角ピックを使い始めたのだ

ダンロップの場合、厚さを色分けで区別しているのだ
つまり、ティアドロップとおむすびは同じ厚みなのだ
余談だが三角形ならばピックが擦り減っても他の角を使うことも可能なのだ
何だかセコいが・・・
お金に窮しているような人にはお薦めなのだ
ピックの100円を馬鹿にする者は100円に泣くのだ
こんな事を書きながら私は一か所しか使わないが・・
どんなに厚いピックでも必ず消耗するのだ
まったく擦り減らないピックも存在する
メタルピックなのだ

究極に弾き難いピックなのだ
しかしながら、メリットもある
金属特有のギラギラとしたアタック感なのだ
クイーンのブライアンメイがコインを使用しているのは有名な話なのだ
コインが弾き易いはずがない
弾き難さを承知の上で独特の音色を選んだのだと思う
私も硬貨で弾いたことがあるのだが・・
すぐに諦めてしまったのだ
ブライアンメイごっこをする時にメタルピックは必須アイテムなのだ
よりハードな音色のリフを刻む時などにも重宝するのだ
擦り減らないのに何で二枚なのか?
実はエッジ部分に細工しているのだ
あえてヤスリをかけてコインの淵のような状態を作り出しているのだ
もう一枚はノーマル状態で滑りが良い
最近、もう一枚違う厚みのピックを購入したのだ

これは完全なるストロークプレイ専用なのだ
エレキでも使うがアコギのコードプレイに適しているのだ
まぁ、すぐに擦り減ってしまうと思うがその辺りの耐久性も含めて試してみたいのだ
自宅練習、宅録などの場合には演奏を中断することも可能なのだ
カッティングが薄いピック、ソロではもう少し厚みのあるピック・・
という感じで使い分ければ問題はないと思う
しかしながら、友人とのバンド練習、ライブとなると話は別だと思う
基本的にピックと指弾きの使い分けはあるにしてもプレイスタイルでピックを持ち換える人は少ない
周囲の人々やお客さんに気付かれないようなマジック的なテクがある人は良いが・・
バレたらかなり恥ずかしいと思う
演奏中にピックを落としてしまう事の次に恥ずかしい事なのだ
つまりは常日頃からオールマイティに使えるピックを決めておくことが重要なのだ
決めるだけならば、無能な政○家でも出来る
ソロ、カッティング、アルペジオ・・と柔軟に対処できるテクを身に付けておくべきなのだ
ちなみに厚みのあるピックが一番難しいがこれに慣れておけばそれよりも薄いピックには簡単に対応できる
ロックには厚いピック、ブルースやジャズなどには薄いピックと思っている人も多いようだ
単にイメージの話だと思う
実はロック系のギタリストにもバッキングが主体ならば薄いピックを好む人も多いのだ
ソロとは逆に音のムラを少なくする為なのだ
ブルースで重要なのはとにかく音の強弱なのだ
特に強くピックを振り下ろす時に独特のアタック感を得るのだ
この場合に弦に負けるような薄いピックでは『あの音』は出ないのだ
ネットでもピックを研究している人が多いようなので参考にしていただきたい
あまりのマニアックさに引いてしまう人も多いと思うが・・・
こだわる人にとってはそのくらい重要であるという事なのだ
私の場合には現時点で理想のピックに出会った気がしているが・・
今後も良いピックがあれば試してみたいと考えているのだ
奥が深い世界なのだ
今回も簡単な音源を作ってみたのだ
ジムダンロップの厚めのピックで弾いているのだ
心の師匠であるヴァイ氏の楽曲をイメージしてみたのだ

読者の皆さんはどんな基準でピックを選んでいるだろうか?
ピックは意外にもギターの音色に大きな影響を与えるマストアイテムなのだ
弾き易さで選ぶというのも良いが音色&音質で選んでみては如何だろうか?
楽器店では大きさ、厚さ、素材など豊富なピックが販売されている
私もかつては色々なメーカーのピックを試してきたのだ
楽器店のお兄さん推奨のピックも一通り試してみたのだ
結果的に現在はこんな感じなのだ

お気に入りはジムダンロップ製のピックなのだ
弦はご存じのとおりダダリオなのだ
ある意味ではどちらも大定番だといえる
定番といわれる製品のメリットは安心感と安定供給にあると考えている
ちょっと変わった人などは他人と違うマニアックな製品を好む傾向があるようだが・・
メーカーは気まぐれなのだ売れない商品は予告なく打ち切りになる可能性もあるのだ
こんなブログを見かけたことがある
「外国で暮らしている友人から定期的に郵送してもらっている弦なんだけど・・」
おそらく、本人はちょっとした自慢のつもりなのだと思う
本人が思うほど読者は羨ましく感じてはいないと思うのだ
一般的なリスナーや読者は曖昧なネタよりも五感に訴えかけるような音を求めているような気がする
マニアックな弦を使ったショボイ演奏よりも定番ダダリオを使ったカッコいい演奏に興味があるような気がする
如何だろうか?
ピック選びの基準は千差万別だが・・
一般論というものはある
一般的に厚めのピックは上級向け
薄いピックは初心者向けという考えが定着している
正しくもあり間違いでもあるのだ
薄いピックが初心者に好まれる事からこんな噂が定着したのだと思う
薄いピックを使えば弦の上を滑らかに動かすことが出来る
特にストロークやカッティングの時に有効だといえる
弦がピックに勝る・・という状態なのだ
多少妙な握り方をしていてもピックの柔軟性がそれを受け止めてくれるのだ
実は中級以上(キャリアだけ?)になってもこの悪癖が抜けない人が多いのだ
慣れとはある意味恐ろしいものなのだ
薄く柔らかいピックしか使えなくなってしまうのだ
もちろんこれでも上手に弾けるというならば特に問題はないが・・・
薄いピックにもデメリットがある
音質に関していえば、強いアタック感が出ないのだ
さらに経済性として消耗が早いのも難点なのだ
一方の厚いピックは捌きが非常に難しい
まったく反らないピックでオルタネイトのアルペジオを演奏するシーンをイメージしていただきたい
薄いピックならば確実に反るようなケースでも厚いピックは反らないのだ
つまり、薄いピックが弦に負けて反る分を指先の逃がしで対処しなくてはならないのだ
厚いピックに慣れた人はとくにこんな面倒臭いことは考えずに弾いていると思う
メリットはその強いアタック感なのだ
特にソロを力強く弾きたい・・と思っている人は必須なのだ
最強の組み合わせは太い弦と厚いピックなのだ
まさにレスポールの定番なのだ

私も色々と試してみたのだが・・・
私の場合、ソロでは間違いなく厚いピックが好みなのだ

しかしながらカッティングになると話は別なのだ
もう少し、薄いピックの方が音に切れが増すように感じられる
実際、演奏性も向上するような気がするのだ

最近はストラトマスターであるChar氏の影響で昔ながらの三角ピックを使い始めたのだ

ダンロップの場合、厚さを色分けで区別しているのだ
つまり、ティアドロップとおむすびは同じ厚みなのだ
余談だが三角形ならばピックが擦り減っても他の角を使うことも可能なのだ
何だかセコいが・・・
お金に窮しているような人にはお薦めなのだ
ピックの100円を馬鹿にする者は100円に泣くのだ

こんな事を書きながら私は一か所しか使わないが・・
どんなに厚いピックでも必ず消耗するのだ
まったく擦り減らないピックも存在する
メタルピックなのだ

究極に弾き難いピックなのだ
しかしながら、メリットもある
金属特有のギラギラとしたアタック感なのだ
クイーンのブライアンメイがコインを使用しているのは有名な話なのだ
コインが弾き易いはずがない
弾き難さを承知の上で独特の音色を選んだのだと思う
私も硬貨で弾いたことがあるのだが・・
すぐに諦めてしまったのだ
ブライアンメイごっこをする時にメタルピックは必須アイテムなのだ
よりハードな音色のリフを刻む時などにも重宝するのだ
擦り減らないのに何で二枚なのか?
実はエッジ部分に細工しているのだ
あえてヤスリをかけてコインの淵のような状態を作り出しているのだ
もう一枚はノーマル状態で滑りが良い
最近、もう一枚違う厚みのピックを購入したのだ

これは完全なるストロークプレイ専用なのだ
エレキでも使うがアコギのコードプレイに適しているのだ
まぁ、すぐに擦り減ってしまうと思うがその辺りの耐久性も含めて試してみたいのだ
自宅練習、宅録などの場合には演奏を中断することも可能なのだ
カッティングが薄いピック、ソロではもう少し厚みのあるピック・・
という感じで使い分ければ問題はないと思う
しかしながら、友人とのバンド練習、ライブとなると話は別だと思う
基本的にピックと指弾きの使い分けはあるにしてもプレイスタイルでピックを持ち換える人は少ない
周囲の人々やお客さんに気付かれないようなマジック的なテクがある人は良いが・・
バレたらかなり恥ずかしいと思う
演奏中にピックを落としてしまう事の次に恥ずかしい事なのだ
つまりは常日頃からオールマイティに使えるピックを決めておくことが重要なのだ
決めるだけならば、無能な政○家でも出来る
ソロ、カッティング、アルペジオ・・と柔軟に対処できるテクを身に付けておくべきなのだ
ちなみに厚みのあるピックが一番難しいがこれに慣れておけばそれよりも薄いピックには簡単に対応できる
ロックには厚いピック、ブルースやジャズなどには薄いピックと思っている人も多いようだ
単にイメージの話だと思う
実はロック系のギタリストにもバッキングが主体ならば薄いピックを好む人も多いのだ
ソロとは逆に音のムラを少なくする為なのだ
ブルースで重要なのはとにかく音の強弱なのだ
特に強くピックを振り下ろす時に独特のアタック感を得るのだ
この場合に弦に負けるような薄いピックでは『あの音』は出ないのだ
ネットでもピックを研究している人が多いようなので参考にしていただきたい
あまりのマニアックさに引いてしまう人も多いと思うが・・・
こだわる人にとってはそのくらい重要であるという事なのだ
私の場合には現時点で理想のピックに出会った気がしているが・・
今後も良いピックがあれば試してみたいと考えているのだ
奥が深い世界なのだ
今回も簡単な音源を作ってみたのだ
ジムダンロップの厚めのピックで弾いているのだ
心の師匠であるヴァイ氏の楽曲をイメージしてみたのだ