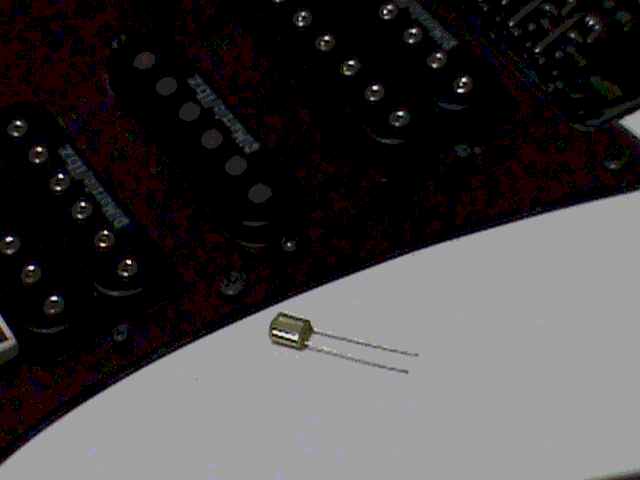私のグラスレスポールのピックアップをダンカンに交換したことはご存じだと思う

デフォルトの安ピックアップからの交換で好みの音になったのだ
車で例えるならばギターのピックアップは心臓部であるエンジンに相当する重要なパーツなのだ
『ギターはバランスだ!』という人も多いが・・・
やはりピックアップによるところが大きいのは否めない事実なのだ
愛用のアリアもダンカンに交換したのだが素性が良いギターだけに
個人制作の高級ギターのような音に生まれ変わったのだ
ピックアップ交換はカスタムの第一歩だといえるのだ
ちなみにデフォルトの状態が良い(気に入っている)という場合はあえて交換はしない方が無難だと思う
コンデンサーなどその他のパーツも同様なのだ
先にも述べたように『バランス重視』というのも考え方の一つだと思う
話をレスポールに戻そう
ダンカンの音色は気に入っていたのだが・・・
オープンタイプのルックスに少々違和感を感じていたのだ
プロでもオープン派は少なくないが・・・
やはりレスポールにはカバータイプのピックアップが似合うように感じていたのだ
カバータイプのトーカイを横に置きながらそんな事を考えていたのだ

カバーは飾りなのか?
諸説あるが・・
飾りではないのだ
ピックでボビンにキズが付くのを防止する
ピックアップのノイズを軽減する
というのが主な役割だと言われているのだ
ピックアップにキズというのも個人差がある
ノイズに関してはもはや過去の話なのだ
ハム系の一号機が開発された時代の名残なのだ
現代のピックアップに関してはオープンでも何の問題もないといえる
ようするに『ルックス』の話になってくるのだ
不思議なものでアイバニーズやアリアにカバーを付けたいとは思わない

この辺りもギターデザインの妙・・なのだ
そんな流れからダンカンに適合するカバーを探していたのだ
純正はもちろん、社外の色々なメーカーからアフターパーツが販売されているのだ
カバーとはいえども四隅の形状やトップの厚み、素材など・・微妙に異なるようだ
元々のピックアップがミリ規格か?インチ規格か?という部分も重要なのだ
以前に安ピックアップのカバーを流用しようとチャレンジしたがサイズ違いで断念したのだ
この辺りは注文(購入)前に十分に調べておくべき部分なのだ
私のレスポールのリアはダンカンのSH-4というタイプをチョイスしているのだが・・
通常タイプと幅広タイプが存在するのだ
当然ながら開封後の返品は不可なのだ
結局、楽器店のお兄さんと相談しながらESP製のパーツに決めたのだ

私のグラスルーツのレスポールはESPの直系ブランドなのだ
偶然だが・・これも何かの縁だと思える
すでの取り付けも完了して音チェックも済んでいるのだ
カバー有り、無しで音の違いが感じられないという人が多々いるららしいが・・・
カバーを取り付けた事で確実に音が変化したのだ
良く言えば・・
”丸みを帯びた音・・”
悪く言えば・・
”音抜けが悪い音・・・”
という感じなのだ
オープンタイプのハムをイメージしていただきたい
オープンならば二連のマグネットが剥き出しの状態なのだ
カバーを被せることで片側のマグネットがカバーに隠れる事になる
これだけでも何の影響もないという方がおかしいのだ
リア側はほど良い感じでマイルドになったのだが・・・
フロントの音が気に入らないのだ
得意のコンデンサー交換で音色を変えようと考えているのだ
ピックアップにカバーを取り付ける、取り外す・・
ピックアップの交換が出来る人にとっては問題ない作業だが多少のコツもいるようだ
その辺りの作業工程なども撮影済みなので近々にご紹介したいと考えているのだ

デフォルトの安ピックアップからの交換で好みの音になったのだ
車で例えるならばギターのピックアップは心臓部であるエンジンに相当する重要なパーツなのだ
『ギターはバランスだ!』という人も多いが・・・
やはりピックアップによるところが大きいのは否めない事実なのだ
愛用のアリアもダンカンに交換したのだが素性が良いギターだけに
個人制作の高級ギターのような音に生まれ変わったのだ
ピックアップ交換はカスタムの第一歩だといえるのだ
ちなみにデフォルトの状態が良い(気に入っている)という場合はあえて交換はしない方が無難だと思う
コンデンサーなどその他のパーツも同様なのだ
先にも述べたように『バランス重視』というのも考え方の一つだと思う
話をレスポールに戻そう
ダンカンの音色は気に入っていたのだが・・・
オープンタイプのルックスに少々違和感を感じていたのだ
プロでもオープン派は少なくないが・・・
やはりレスポールにはカバータイプのピックアップが似合うように感じていたのだ
カバータイプのトーカイを横に置きながらそんな事を考えていたのだ

カバーは飾りなのか?
諸説あるが・・
飾りではないのだ
ピックでボビンにキズが付くのを防止する
ピックアップのノイズを軽減する
というのが主な役割だと言われているのだ
ピックアップにキズというのも個人差がある
ノイズに関してはもはや過去の話なのだ
ハム系の一号機が開発された時代の名残なのだ
現代のピックアップに関してはオープンでも何の問題もないといえる
ようするに『ルックス』の話になってくるのだ
不思議なものでアイバニーズやアリアにカバーを付けたいとは思わない

この辺りもギターデザインの妙・・なのだ
そんな流れからダンカンに適合するカバーを探していたのだ
純正はもちろん、社外の色々なメーカーからアフターパーツが販売されているのだ
カバーとはいえども四隅の形状やトップの厚み、素材など・・微妙に異なるようだ
元々のピックアップがミリ規格か?インチ規格か?という部分も重要なのだ
以前に安ピックアップのカバーを流用しようとチャレンジしたがサイズ違いで断念したのだ
この辺りは注文(購入)前に十分に調べておくべき部分なのだ
私のレスポールのリアはダンカンのSH-4というタイプをチョイスしているのだが・・
通常タイプと幅広タイプが存在するのだ
当然ながら開封後の返品は不可なのだ
結局、楽器店のお兄さんと相談しながらESP製のパーツに決めたのだ

私のグラスルーツのレスポールはESPの直系ブランドなのだ
偶然だが・・これも何かの縁だと思える
すでの取り付けも完了して音チェックも済んでいるのだ
カバー有り、無しで音の違いが感じられないという人が多々いるららしいが・・・
カバーを取り付けた事で確実に音が変化したのだ
良く言えば・・
”丸みを帯びた音・・”
悪く言えば・・
”音抜けが悪い音・・・”
という感じなのだ
オープンタイプのハムをイメージしていただきたい
オープンならば二連のマグネットが剥き出しの状態なのだ
カバーを被せることで片側のマグネットがカバーに隠れる事になる
これだけでも何の影響もないという方がおかしいのだ
リア側はほど良い感じでマイルドになったのだが・・・
フロントの音が気に入らないのだ
得意のコンデンサー交換で音色を変えようと考えているのだ
ピックアップにカバーを取り付ける、取り外す・・
ピックアップの交換が出来る人にとっては問題ない作業だが多少のコツもいるようだ
その辺りの作業工程なども撮影済みなので近々にご紹介したいと考えているのだ