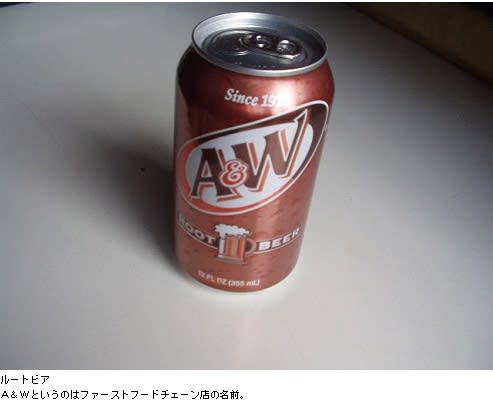おやつになる主食
子供の頃、盆、正月を含め年に数回は母方の実家に遊びに行っていた。車で2、30分のところだったので、遠出というほどのことでも無かった。
夏休みになると2泊3日、あるいは3泊4日の滞在となった。その間、母親が一緒でないときは、祖母が我々(姉と私)の食事の世話をした。ご飯、味噌汁、チャンプルーなどといった普通の食事の他に、祖母が決まって出す料理が二つあった。それらは、今でも私の舌の記憶に残っていて、祖母の料理と言えばこれだと言えるものであった。
その二つとはソーミンプットゥルーとヒラヤーチー。ソーミンプットゥルーについては既に書いたので、今回はヒラヤーチーについて少し。ヒラヤーチーとは、和語で言うと平焼きという意味になる。薄いお好み焼きのようなもの。小麦粉を水で溶いて、玉子とニラ(青ネギでも可)を加える。水溶き小麦粉はお好み焼きと同じくらいの緩さにする。フライパンに薄く油を敷き、タネを回し入れ、薄く敷き詰める。途中、ひっくり返して、焼き色が付いたら出来上がり。醤油、またはソースをつけて食う。
ヒラヤーチーは、おやつとして出されることもあったが、朝食の主食として出されることも多かった。味噌汁とヒラヤーチー2、3枚といったところ。私も姉も喜んで食べた。美味しかったからだ。ニラしか入っていない薄べったいお好み焼きであったけれど、祖母の作るヒラヤーチーはとても美味しかった。私は好きだった。
その後、大人になってから、自分でヒラヤーチーを作る機会は何度もあった。今でもたまに作って食べている。祖母の味を懐かしんでのことだ。自分で作ったヒラヤーチーは美味しい範囲に入るのだが、しかし、祖母のそれとは何か違う。小麦粉が薄力粉なのは母が作るのを見て知っていた。ちなみに、母の作るヒラヤーチーも祖母のとは違う。母のものは私のものに近い。祖母のより1ランク落ちる。いったい何が違うのか?
今、従姉が来たので、その話をした。彼女も、
「そういえばあのヒラヤーチーは美味しかったね。オバーのソーミンプットゥルーも美味しかったね。」と言う。二人でしばし協議した。
「もしかしたら油なんじゃないの。ラードを使っていたんじゃないの?」と私。
「そうだねぇ、ラードかもねぇ。ソーミンもそうだねぇ。コクがあったもんねぇ」と彼女も肯く。というわけで、祖母の作るヒラヤーチーやソーミンプットゥルーの美味しさの秘密はラードにあり、という結論に至った。ヒラヤーチーはラードを用いて焼くと旨い、という実験、及び検証は後日行い、報告することにしましょう。

記:ガジ丸 2004.11.19 →沖縄の飲食目次