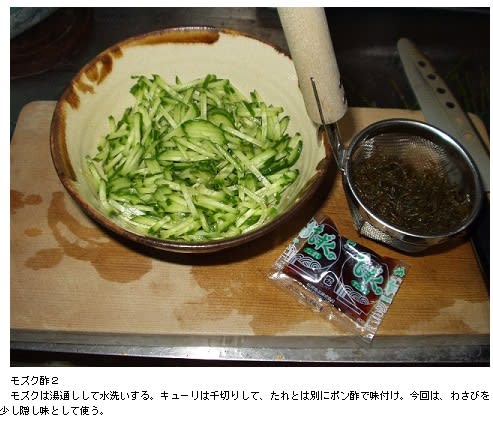最高のソーダ
高校からの友人で、今でも月1回は会っている仲間たちがいる。ここ数年は行っていないが、まだお互いの子供たちが小学生だった頃まではよくキャンプに行っていた。キャンプは、女房子供を入れて総勢30名、多いときは40名ばかりになった。
浜辺でバーベキューをやる。泳ぎ疲れた子供たちが寄ってくる。子供たちは、それまでに何度もオジサンたちと会っているので、それぞれの名前を知っている。それぞれ「○○のオッチャン」と姓名の姓か、または「○○オジサン」と姓名の名で呼ばれる。しかし、ただ一人、名前では無く、「ソーダのおじさん」とあだ名で呼ばれる男がいた。彼はビール大好きオジサンなので、私は彼がソーダを飲んでいるところを見たことが無い。何故、子供たちは彼のことを「ソーダのおじさん」と呼ぶのか。子供たちに訊いた。
「だって、いつも、そーだ、そーだと言っているんだもん。」ということであった。言われてみると確かに「そーだ、そーだ」は彼、Yの口癖のようだ。Yは温厚な性格で、彼の「そーだ、そーだ」はおそらく、「和をもって尊しとする」の精神であろう。
「お父さん、タバコ吸いすぎ」
「そーだ、そーだ」
「お母さん、お肉、もっと焼いて」
「そーだ、そーだ」
などとなる。子供たちの味方である。自分の意見を出さずに他人の意見に乗っかているだけ、との批判もあろうが、多数の意見を後押しするには効果的な「そーだ」である。物事が楽しく、上手く、速やかに流れて行くようにとの彼の心の表れであろう。最高とまでは言えないが、お付き合いのためにはベターな「そーだ」と言えよう。
沖縄には昔、といっても復帰(1972年の本土復帰)の頃だから、ちょっと昔の頃まで、庶民に親しまれた最高のソーダがあった。こちらのソーダは飲み物のソーダのこと。レモン味とかストロベリー味とかラズベリー味とか何種類もあった。子供たちにとってはコカコーラよりペプシよりファンタよりミリンダより馴染み深く、親しみ深いものであった。沖縄産のそのソーダは、残念ながら復帰後の物価高騰などの影響もあって営業不振となり、1975年に休業となる。しかしながら当時、1本5セントという安さもあって、庶民にとっては最高のソーダなのであった。その名もベストソーダといった。

ベストソーダ(『沖縄大百科事典』より)
戦後ハワイから引き揚げてきた屋比久孟吉が1953年11月、宗元寺の一角で営業を開始、(中略)最盛期の70年ころには県内シェア17%、(以下略)
記:ガジ丸 2005.7.19 →沖縄の飲食目次
参考文献
『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行