ドイツでは「車いすスポーツの父(教皇)」と呼ばれ、障害者スポーツの権威であるストローケンデル博士を講師に迎えます。
COILセミナーvol.13
【共生社会】×【スポーツ】×【障害者の社会参加】
~スポーツはいかに障害者の社会参加を促進してきたか?~
障害者スポーツの歴史は、障害者の社会参加の歴史でもあります。スポーツは障害当事者の心身にポジティブな影響を与え、大規模な大会の実施は一般の障害者に対する理解を促進してきました。しかし、大会の高度な競技化によって、大会を実施するだけでは障害当事者のスポーツへの参加が促進できなくなったことが指摘されています。
そのため、東京2020を契機として共生社会を実現するためには、改めてスポーツの可能性を見直し、大会の実施を通したスポーツ活動の促進を通して障害当事者の社会参加を促進する必要があります。
今回のCOILセミナーでは、障害者スポーツの黎明期から国際的に大きな貢献を果たしてきたホルスト・ストローケンデル博士を講師として招聘し、これまでの障害者スポーツの歴史や現在のご活動の紹介などを通して「スポーツと障害者の社会参加の促進」について迫ります。

<開催概要>
日時 2018年3月5日(月)18時30分~20時00分(開場18時10分)
会場 東京国際フォーラム ガラス楝会議室4FG402
講師 ホルスト・ストローケンデル博士
通訳 橋本 大佑(一般社団法人コ・イノベーション研究所 代表理事)
主催 一般社団法人コ・イノベーション研究所
協力 公益社団法人日本フィランソロピー協会
定員 80名
セミナー参加費
超早割(1月28日まで先着20名)3,240円
早割(2月11日まで先着20名)3,780円
前売 4,320円
当日 5,000円
チケット申し込み Peatix http://ptix.at/GZyFG1
※介助者の方は無料です。
<セミナーの流れ>
18時30分~18時35分 開会
18時35分~18時50分 第一部 講演『障害者スポーツとは?』
講師 橋本 大佑(一般社団法人コ・イノベーション研究所)
18時50分~20時20分 第二部 基調講演
『スポーツはいかに障害者の社会参加を促進してきたか?』
講師 ホルスト・ストローケンデル博士
20時20分~20時30分 質疑応答・閉会
21時00分~22時30分 懇親会
※障害のある女性のスポーツ実施率が高いドイツの実践例を通してアクセシビリティと
スポーツ参加の関係性を学びます
<講師紹介>
基調講演講師:ホルスト・ストローケンデル博士

1941年12月8日生まれ(76歳)。1980年代前半に執筆した「車いすスポーツのための機能的なクラス分け」という博士論文が車いすバスケットボールの基礎となり、今日のパラリンピックにも大きな影響を与えた。ドイツの車いすバスケットボール代表チームのヘッドコーチを長く務め、国際車いすバスケットボール連盟技術顧問、国際ストーク・マンデビル車椅子スポーツ連盟役員などを歴任するなど国際舞台で活躍するとともに、ドイツ国内では車いすスポーツ指導者の養成に取り組み、ドイツ国内に300以上車いすスポーツの地域クラブが設立される下地を作った。2006年にケルン大学を退職してからも精力的に世界各国で指導者養成講習や講演を行う。ドイツでは「車いすスポーツの父(教皇)」と呼ばれ親しまれている。
第一部講師及び第二部通訳紹介 橋本 大佑

(一般社団法人コ・イノベーション研究所 代表理事/ドイツ障害者スポーツ協会公認リハビリテーションスポーツ指導者B)
筑波大学で障害児教育を学んだ後、渡独。日系企業に勤めながらストローケンデル博士に師事し、リハビリテーションスポーツ指導者資格(車いすスポーツ)を取得。2009年に日本に帰国した後、2013年に独立。2016年、一般社団法人コ・イノベーション研究所を設立し、代表理事に就任。スポーツを通じた障害者の社会参加促進に取り組み、国内外で障害者スポーツの指導法や、障害理解に関する講師を務める
<今回のセミナーのテーマにある背景>
●障害者スポーツの分類には「3つ目のスポーツ」がある
一般的なスポーツは、心身の健康の維持・増進のために行う「余暇スポーツ」と、特定の目的のためにその範囲を越えて行う「競技スポーツ」に分類される。
しかし、障害者スポーツには「障害者の社会参加を促進するためにツールとして活用するリハビリテーションスポーツ」という3つ目の分類がある。リハビリテーションスポーツには身体訓練として行われる医療における取り組みだけではなく、退院後の孤立を予防し、更なる社会参加を促すための心理的な変化をもたらすことを目的とした地域での取り組みがあり、健康保険の適用範囲が限定された現在では、この地域でのリハビリテーションスポーツが重要度を増している。

●「競技スポーツ」の啓蒙は、障害者スポーツ人口の獲得にはつながらない
2011年のワールドカップで女子サッカーのなでしこジャパンが優勝したことがきっかけで女子のサッカー人口が増加してことが知られている。国際的な「成果」によって「メディアによる広報」が促進することで競技の知名度が上がり、「競技人口が増え(普及)」、それが将来的な「強化」につながり、さらなる「成果」をもたらす、というように「成果」⇒「広報」⇒「普及」⇒「強化」⇒「成果」という競技発展には正のスパイラルモデルがある。
しかし、これは障害者スポーツには当てはまらない。メダルを取ったや近年のオリパラブームで大きく取り上げられた競技で、大きく競技人口が増えているという話はない。実際にパラスポーツとして知られるパラリンピック競技種目が実施できる障害者は、障害者全体の一部でしかなく、我々がオリンピック選手を見て「スポーツがしたい!」と思わないように、多くの障害者もパラリンピック選手を見て「スポーツがしたい!」と思わないことはロンドンパラリンピック以降に行われた障害当事者向けの調査でも明らかになっている。
(ロンドン大会実施後にイギリスで1014名の障害当事者を対象に行われた調査ではパラリンピックを見て「スポーツをしたい!」と感じた人は約10%にとどまった)
スポーツ庁が公開している障害者のスポーツ実施率も19.2%(平成27年度調査)であり、平成25年の18.2%からほとんど増えていない。これは障害者スポーツにおいては、「こういう競技がある」ということを知った後、実際に「やってみる」までに多くのハードルがあるためである。
そしてそのハードルを解消して継続的なスポーツ実施を促すために必要なものこそが「リハビリテーションスポーツ」である。

●ドイツでは地域のリハビリテーションスポーツに健康保険が適用される
ドイツでは、多くの先進国と同様、高齢化による医療費の増加により、中途障害者の入院期間が非常に短くなっている。従来1年から2年程度入院できた脊髄損傷者も現在では3ヶ月で退院を余儀なくされる(日本でも同様)。この短期間では心理的に障害の受容は難しく、退院後の引きこもりは大きな課題となっており、国内の調査でも脊髄損傷を受傷した中途障害者の自殺死亡率は一般の13倍と報告されている。
スポーツ活動をきっかけに外出の機会を作り、失った自尊感情を取り戻すことを目的に、ドイツの地域でのリハビリテーションスポーツは医療行為として認められ、健康保険が適用される。しかし、医療行為の一環として実施されるスポーツであり、スポーツ経験も十分でない(場合によっては苦手意識の強い)方の場合、ちょっとした失敗で二度と参加しなくなってしまうことも多い。身体に動作制限があり、心理的にも自信や動機付けが十分でない人安全に継続参加を促すための場を作って運営し、現場指導をするには特別なノウハウが必要となる。

●ストローケンデル博士の50年間の先進的な取り組み
ドイツにおける障害者スポーツの普及も、全てが上手くいっているわけではない。しかし、今回招聘するストローケンデル博士の所属する車いすスポーツ連盟では350以上の地域クラブを管轄し、そこで7000人以上が週に1回以上のスポーツを実施している。障害者の多くは中途障害者であるため、若年層のスポーツ人口は非常に低く、ドイツ全体の障害者のスポーツ人口の中で21歳以下の割合は8%程度であるが、車いすスポーツ連盟では約25%の登録者が21歳以下である。このように通常スポーツへの導入が難しい層へのスポーツの普及に大きく成功してきた背景には、「地域での社会参加を促すためのリハビリテーションスポーツ」の場作りや運営、現場指導ができる人材を育成してきた歴史があり、その中心となったのがストローケンデル博士である。

●スポーツは共生社会の実現のツールとなり得る
一般の障害への理解を高めることはパラリンピックの大きな効用である。しかし、それだけでは障害者自身の社会参加を促すことができないことは歴史が証明している。共生社会実現のため、障害者の社会参加を促進するためには、今こそ「地域でのリハビリテーションスポーツ」が必要である。本セミナーでは、ストローケンデル博士を招き、スポーツが障害者の社会参加や権利獲得にどのような役割を果たしてきたか、東京2020に向けてリハビリテーションスポーツを含めた障害者スポーツはどのような役割を果たしていくのか、議論を深める。

<COILセミナー>
コ・イノベーションセミナー(COILセミナー)では、人格と個性を尊重して支え合い、多様性を相互に認め合える「共生社会」を解決すべき社会課題として捉え、多様なステークホルダーを巻き込み、解決につなげることで、社会的な価値だけではなく、経済的な価値を創出することを目的として、専門的な知識を持つゲスト講師の講演や、東京2020に関する最新トピックス、新しい時代における人材開発や組織開発に関するセミナーを実施します。
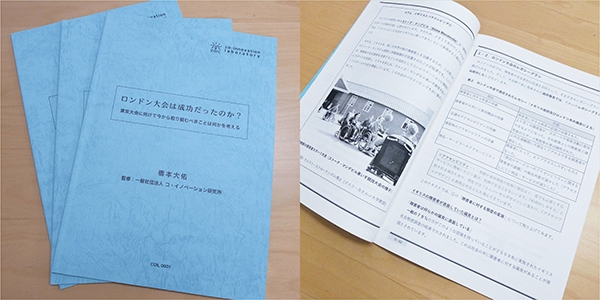
【2020共生社会】×【スポーツ】×【障害者の社会参加】













