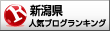園研(園芸研究センター)です。
指導農業士会の園芸部会研修で園芸研究センターを訪問。
指導農業士会と園芸研究センターはとても仲良しなのです。このところ1年おきの訪問。

まずは職員を1匹紹介します。一昨年も紹介したと思うが、、、、
https://blog.goo.ne.jp/hikarabinotiti/e/1f541049ba60160ccceac7ae87d9afe7

最先端の農業はすさまじくシステマチックになっている。
かかるコストと採算性まですべて数値化されて、さあやってくださいと言わんばかりに。
いちご(越後姫)はCO2コントロールで増収益。

画像ではわかりづらいかもしれないがキュウリの溶液栽培。
1株4本立ち上げで弦が伸びたら誘引クリップをずらしながら下げて行く栽培。

まったく同じ位置で花が咲いて同じ位置で収穫、常に同じ光量を当て続けるので同じ実がなる。
温度と養分が続く限りずっと収穫し続けられそうなキュウリ工場。

自分は花卉農家だが柿は好きだ。木に成るものがとても気になる。
感銘を受けたモモの斜立仕立て。
ヒョロッと伸ばした1年苗を植えて翌年からもう収穫。
南向きに斜めに幹を伸ばして短い枝で仕立てるので全ての葉と実に同じように陽が当たる。
なので同じ糖度の実が育つのだそうだ。
蜜植多収穫なのでそつも無く高収益。
もう先祖代々の果樹園なんて時代じゃないんだね。

ぶったまげたのは梨のジョイント栽培。

こんなに蜜植に植えられたル・レクチェ。

幹を横に伸ばして隣の木に接ぎ木する。1列の梨を1本の木として養分コントロールする。
枝は小ぶりに仕立てて十分に陽に当てる。実の大きさや糖度が揃うのだそうだ。恐れ入った。

ル・レクチェは大変病気に弱い梨。
園研では病気の葉をかき集めて土に埋めて蔓延させ無いと言う物理的防除法を農家に普及することによって
病気でのロスや防除回数を大幅に減らした実績があるのだそうだ。
これって我々露地栽培農家にも当てはまるよなぁ。

南向きに幹を仕立てるって我々で言えば南北向きにハウスを建てて均一な日当たりを確保すること。
花栽培に相通じることを果樹から学ばせてもらった。
お約束のシャインマスカット食べ放題。(えげつなく催促しておいたので)
残しておいたと言うくらいなので糖度も熟度も満点、甘いっ。

このハウス、実は稲の育苗ハウスなのだ。
育苗中は弦だけなので苗に陽が当たる。苗が出ると葉が開いてブドウが育つ。
つまり二毛作ハウス。どちらかと言うと中規模複合農家向けだろうか。
さて、我らがユリの畑。おびただしい品種数。

よく見るとマイプレティ、エンジェルリップ、駒の春、秋葉錦、紅姿、あかつき、越の紅、清津紅、、、、
今の後継者たちは全く知らないだろうが昭和50年代我々が育てた懐かしい品種たち。
大事に保持してくれてたんだねぇ。涙が出るほどうれしい。これらが花開くころ訪れてみたい。

室内研修、研究員たちがそれぞれの成果を発表。気合の入り方が半端ない。

質疑、意見交換も盛り上がって1時間近く延長。

当然飲みながらの情報交換会も永遠に続きそうな感じだった。
エンケンと農業士たちはとてもとても仲良しなのです。