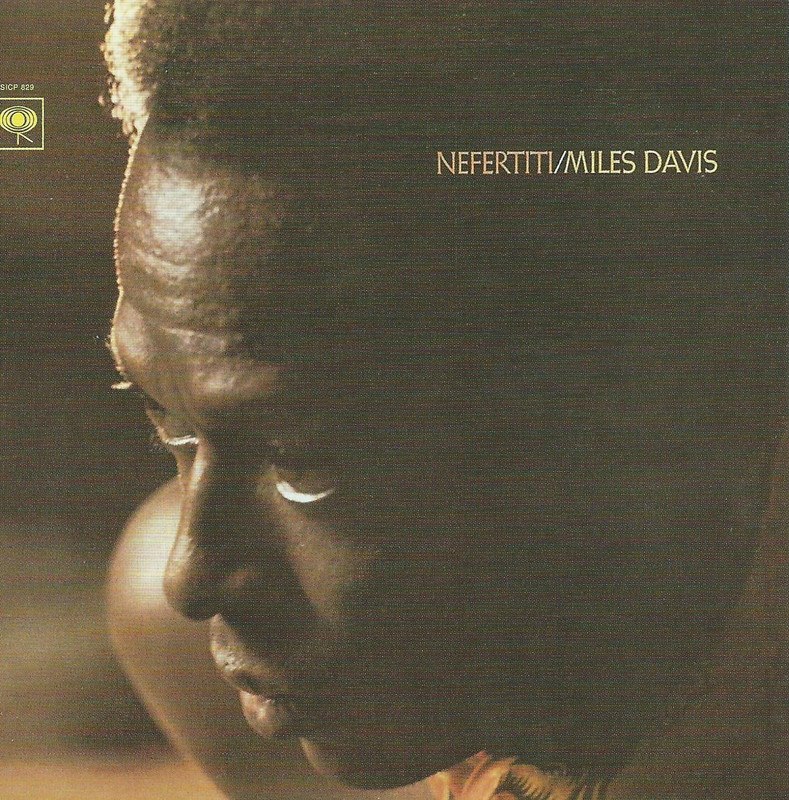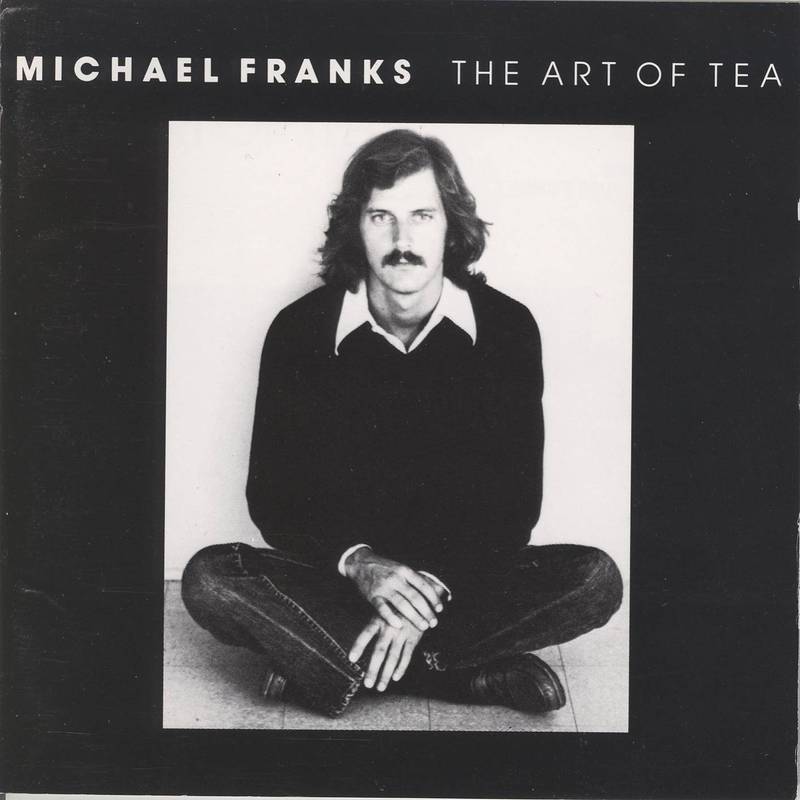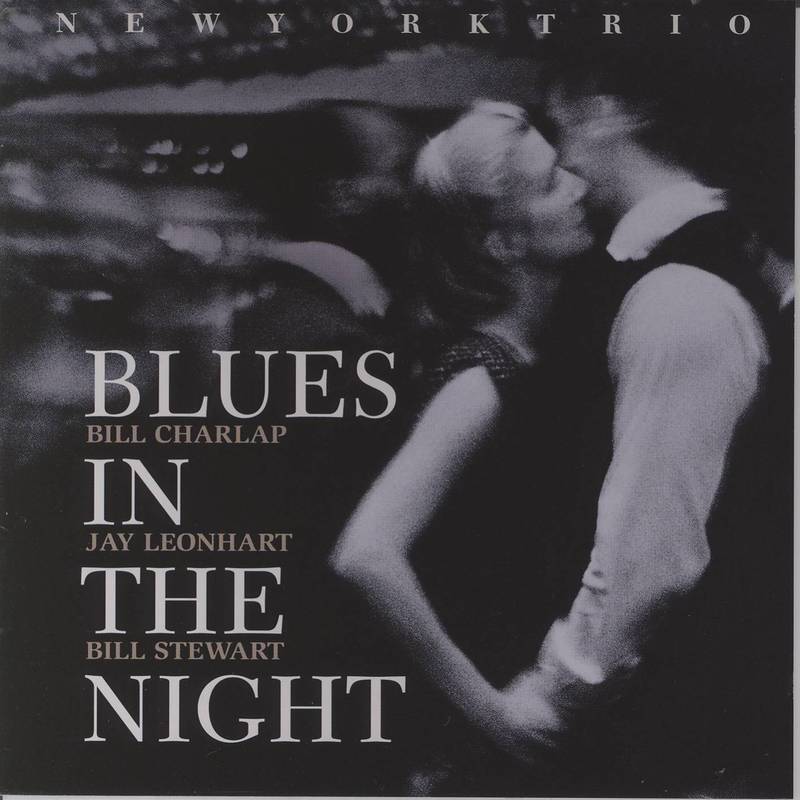●今日の一枚 399●
Neil Young
Harvest

ニール・ヤングを同時代に聴いたことはない。このニール・ヤングの古い代表作の『ハーベスト』は1972年作品だ。私は10歳だったことになる。もちろん、ニール・ヤングなんて知らなかった。私がニール・ヤングを聴きはじめたのはもっとずっと後のことだ。恐らくは、1980年代だと思う。そして年齢を重ねるにつれて、古い二ール・ヤングをますます好きになっていった。40代になってからは加速度的にその傾向が強まっていったように思う。不思議なことだ。ニール・ヤングの作品をそんなにたくさん持っているわけではない。代表作といわれるいくつかのアルバムが中心だ。50歳を過ぎた今、シンパシーを感じ、聴き続ける価値があると考えるロックミュージックはそんなに多くはない。けれども、ニール・ヤングの音楽は確実にその中のひとつだ。聴き続ける価値があると考える稀有なアーティストのひとりだ。
大学生の頃だったろうか。それまでロック・フリークだった私は急速にロック・ミュージックへの興味を失っていった。ジャズに出合ってしまった私自身の問題も大きいと思うが、時代性、すなわちロック・ミュージック自体の質の変化の問題も大きかったのだと思う。そんな私にとって、ニール・ヤングとの出会いと、その後の興味の深まりは例外的なことだ。
何というか、癒されるのだ。癒されて、心が落ち着く。そう、ずっと以前に書いたのだけれど、暖かい毛布で包み込まれたような心地よい感覚だ。同時代に聴いていたわけでもなく、それにまつわる特別の想い出があるわけでもないが、昔どこかで見た懐かしい風景のような、どこかで聴いた懐かしいメロディーのような、そんな思いが心に満ちてくるのだ。
私は、時代から孤立して古いニール・ヤングを聴く。