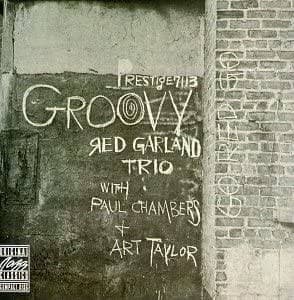◎今日の一枚 563◎
Richie Beirach
No Borders

登米市中田町浅水に「ゆずるの里」というそば処がある。《ゆずる》とは、フィギュアスケートの羽生結弦選手のことだ。羽生選手の父方のおじいさんがこの周辺の出身ということから、命名された店名のようだ。実際、羽生選手も幼少期に登米市に住んだことがあるとも聞く。羽生選手のおじいさんは、元同僚の羽生先生である。もう30年近く前に、M工業高校に勤務していた時の話だ。羽生先生は自動車科の先生で、当時、総務部長をされていた。残念ながら、羽生先生は退職後しばらくして亡くなられたとのことだ。
先日、「ゆずるの里」をローカルのニュース番組が取り上げていた。羽生先生と同級生で元同僚という老紳士がインタビューを受けていた。一目でわかった。同じ社会科でお世話になったK先生である。おそらくはもう90歳近いと思うが、お元気そうに見えた。その穏やかで温かい語り口に、懐かしさがこみ上げ、ほっこりした気持ちになった。
今日の一枚は、リッチー・バイラークの2002年録音盤『哀歌』である。venus盤である。リッチー・バイラークがクラシック曲を奏でるという企画盤である。リッチー・バイラークは好きなピアニストだが、この作品は今一つピンとこず、聴くことが少なかった。今朝、何気なく棚から取り出し、本当にしばらくぶりにCDデッキのトレイにのせてみた。悪くはない。気品のあるタッチである。ピアノの響きも美しい。しかし、やはり何かが違うんだよな、と思ってしまう。アドリブ演奏を展開しながらも構成的な趣の音楽に、ちょっと、考えすぎじゃないかという気がしてしまうのだ。
私がM工業に勤務していたのは、このアルバムがリリースされるよりずっと以前のことだ。当時、羽生先生やK先生は大ベテランで、私は若手だった。
時の流れの速さに立ち尽くすのみである。