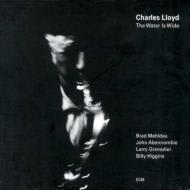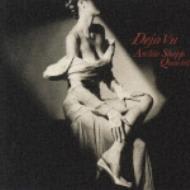今年転勤した高校で女子バスケットボール部の顧問をしている。部員が10人にも満たない弱小チームだ。3月まで勤務していた高校でも男子バスケットボール部の顧問を、また、10年程前にいた高校でも男子の顧問をしていたので、通算すると、バスケットボールの顧問歴は10年以上になる。もともとバスケットボールの経験はなかったが、若い頃は結構一生懸命だったので、本を読んだり、東北大会やインターハイなどを見学に行って勉強した。有名な高校の練習を見せてもらったり、監督さんからいろいろ教えられたりもした。そのせいかどうか、そのころのチームは、ほんの少しだが強くなった。現在のチームはあまり強くはない、というより弱い。けれども選手たちはみなバスケットボールが好きであり、彼女たちなりに一生懸命なので、何とか県大会ぐらいにはつれて行ってやりたいと思っている。無理だろうか……?
ところで、バスケットボールをやる上で、私がいくつかこだわっていることがある。その1つが「モーション・オフェンス」である。モーションとは文字通り「動く」という意味であり、5人が立ち止まることなく、常に動きながらチャンスをねらっていくオフェンスである。現在のバスケットボールの主流であり、基本とされるものだ。そのことを裏付けるように「バスケットボール・マガジン」3月号と5月号では特集が組まれている。しかし、(私が所属するような)ローカルな高校の大会では、このオフェンスをチームの動きのオプションの1つとしているところはもちろんあるが、それをチームの中心的なしかも唯一のシステムとしているところには、あまり出会わない。実際、「バスケットボール・マガジン」5月号で國學院久我山の手塚政則先生が書いているように、このシステムの重要性をみとめつつも、得点するための中心的なシステムとしては採用しないという指導者は多いのではなかろうか。
しかし、私は、これまで指導してきたチームでこのことにこだわり、しつこく指導してきた。わたしのチームにおいては「モーション・オフェンス」は中心的で唯一のシステムである。素人の浅知恵である。というわけで、私のチームの選手は、5人が立ち止まることなく、常に動きながらチャンスをねらっていくことを要求されることになる。
例えばこういうことだ。今、トップのプレーヤーが45度付近にいるプレーヤーにパスしたとしよう。パスを終えたトップのプレーヤーは立ち止まることなく動かなければならないが、動く選択肢は、
①ゴールにカットする
②逆サイドのスクリーンに行く
③ボール保持者のスクリーンに行く(2対2のプレー 、ピックアンドロール)
の3つである。このうち、③はできるだけ行わないよう指導している。理由は、フロアバランスが乱れる上、安易に行いがちなプレーであり、コート全体を見渡す広い視野を育成できないからである。したがって、選手は①か②を選択することになるが、私のチームの選手は常にこの選択と動きを繰り返すことになる。
私はとくに①のプレー(パス・アンド・ランとかギブ・アンド・ゴーとか呼ばれる)をできるだけ多く行うよう指導しているが、それは1つにはパスを終えたプレーヤーがリターンパスをもらってゴールをめざすという積極性を持ってほしいということからであり、もう1つにはパスがもらえなかった場合でも、そのプレーヤがゴールに向ってカットしクリアする(その場をよける)ことによって、ボール保持者の1対1のドライブインやセカンドカッターの侵入のためのスペースができることである。つまり、他のプレーヤーのためにその場をよけ、スペースをつくるわけだ。
このことにこだわるのは、それが選手の心と行動を育てる上でとりわけ重要であると考えるからである。つまり、私はバスケットボールを通じて、自信をもって積極的に行動する勇気と、他者のために自分が犠牲的に行動することの重要性とを選手たちに伝えたいわけだ。私がこれまでバスケットボールの顧問をつとめた学校の生徒たちは、心の発達が未熟で、自分に自信がなく、その裏返しとして他者のことを考えられないという傾向が多かったように思う。バスケットボールという競技を通じて何とかそのことをわかってもらいたかったのだ。実際、この2つのことが理解できたとき、チームは本当に強くなる。
部活動を通じて生徒を育てていく。プロを育成するのでなければ、この視点なしに指導者が部活動に多くの時間を割く意味はない。
とくに他者のために自分が犠牲的に行動するという点は重要だ。よくチームワークというが、チームワークとは何だろう。みんな仲良しなのがチームワークだろうか。そうではないはずだ。バスケットボールにおけるチームワークとはきれい事ではない。それは他者のために具体的に犠牲になることだと私は考える。どんな個人能力のある選手でも、チームメイトが彼にスペースを作ってあげることなしに活躍はできない。したがって、逆に言えば、ある選手がどんなに活躍したとしても、それは彼ひとりの力によるものではない。誰かの犠牲と協力なくしては得点は生まれないわけだ。その意味でいかなる得点もみんなのものだ。そして、それができないとき、チームはみじめな敗北を続ける。
繰り返すが、バスケットボールにおけるチームワークとは、きれい事ではない。それは具体的な自己犠牲と協力の精神であり、それが勝敗に大きくかかわってくる。選手はそのことを身をもって学ぶのであり、それにはっきり結びつくのが「モーション・オフェンス」の考えである。私がいつまでバスケットボール部の顧問を続けるのかわからないが、「モーション・オフェンス」の発想を捨てることはないであろう。
バスケットボールは、思想である。