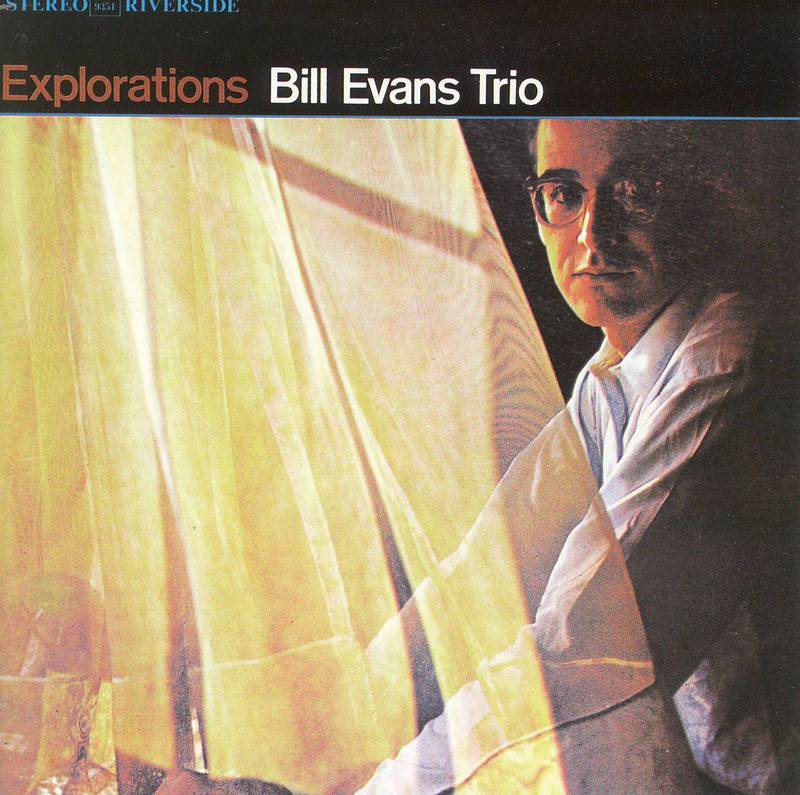太田裕美の1977年作品「しあわせ未満」のシングルレコードがあった。実家の物置から発見されたのである。保存状態もよく、まだまだ十分聴ける代物である。
太田裕美の1977年作品「しあわせ未満」のシングルレコードがあった。実家の物置から発見されたのである。保存状態もよく、まだまだ十分聴ける代物である。
いい曲だ。ジャケットもかわいい。しかし、この詩はなんだ。(今風にいえば)ナンパして同棲をしたが、ピンボーで生活が苦しく、「部屋代のノックに怯え」たり、「指にしもやけ」ができたりした彼女を不憫に思い、「もっと利口な男探せよ」とか「もてない僕をなぜ選んだの」とかいってしまう男の歌なのだ。その女性を気遣う心の純粋さを歌ったものだ。「思いやり」の
しかし、現在という地点から考えれば、生活力も責任感もない男の自己弁護・自己慰安の詩ととらえられても仕方のない部分がある。意地悪くいえば、女性を思いやる「優しい心」が、生活力のない男のみじめさを隠蔽している。以前、他のところでも書いたが、「心の純粋さ」に高値のついた1970年代にしか存立し得ない歌詞だ。
F・ニーチェならば、弱者のルサンチマンにすぎないときって捨てるであろう。そしてそれは、残念ながら、恐らくはあたっている。当時の「心の純粋さ」と社会的な「弱わさ」とは微妙にリンクしていたように思われる。 学生運動などの挫折の後、ちょっとやそっとでは変わりそうもない世界に対する無力感と違和感とが、若者たちを自己のうちに閉じこもらせ、独我論的な方向へと向わせたのである。そういう意味では、体制や世界に対するひ弱な異議申し立てと言えなくもないだろう。自閉した若者たちは、汚れた外の世界との対比において、汚れなき「心の純粋さ」に正義を見出したのである。
にもかかわらず、われわれにとっては大切な歌である。多かれ少なかれ、われわれの世代はそのようなひ弱な「心の純粋さ」を持ちながら、ある者はそれを武器に、ある者はそれと決着をつけずに留保したまま、ある者はそれと格闘して乗り越え、もう一度世界に立ち向かおうとしたのだから……。
歌詞の最後の「あー二人、春を探すんだね」というところが、せめてもの救いである。この二人は、今頃どういう生活を送っているのだろうか。