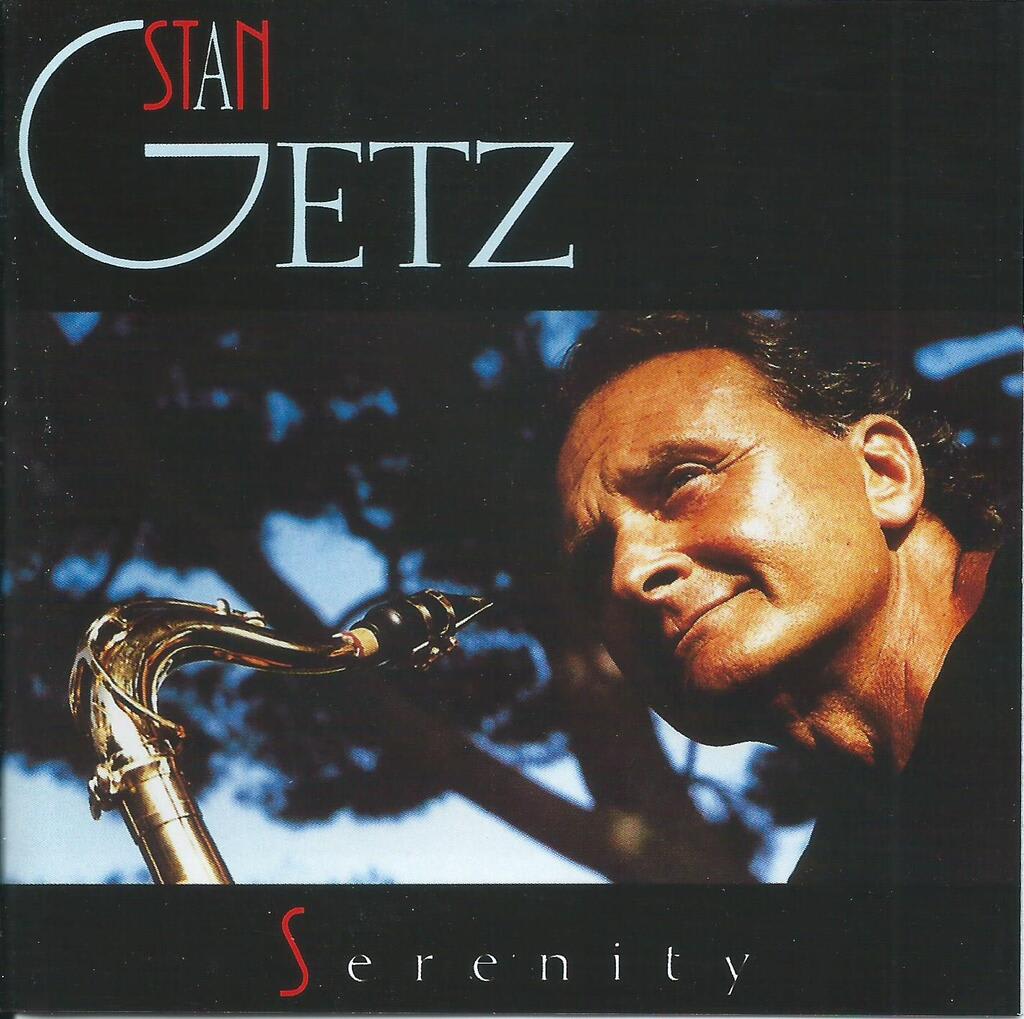◎今日の一枚 556◎
Salena Jones
Mystery Love

「おかえりモネ」の最後の2週、「大人たちの決着」「あなたが思う未来へ」は、非常に印象深い内容であった。いままで放送された内容と結びつき、一挙に疑問が氷解され、いろいろ考えさせられるものだった。
先日、私の住む気仙沼市にある「海の市」という物産施設を訪れた。たまたま用事があって近くに行ったところ、「おかえりモネ展」を開催しているというので立ち寄ってみたのである。どうせ気仙沼市のやる事だからまた中途半端なものだろうという思いもあったが、話のタネにと考え赴いた。ところが結果からいえば、意外と充実したものだったように思う。あまり期待していなかったのでそう思ったのかもしれないが、私のテンションは急上昇だった。
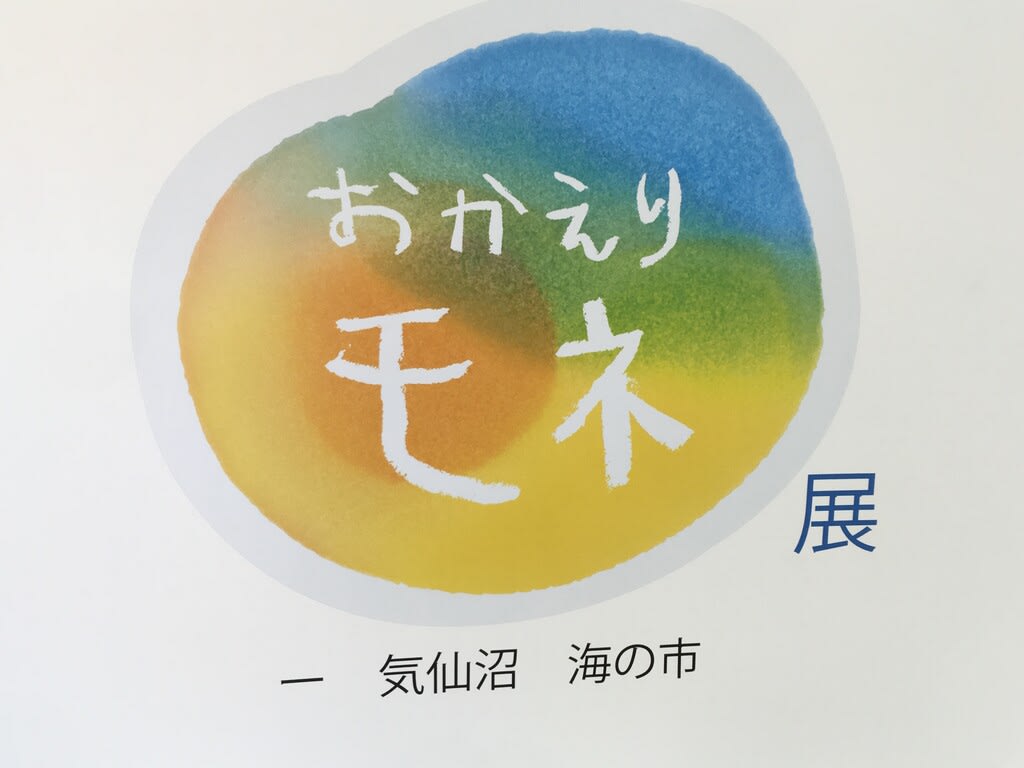
入場は無料である。



大きなパネルやドラマの場面の写真、撮影風景の写真を中心に構成されていたが、中にはこんなものもあった。

テーマソングの映像を模して、ここに入って走るポーズで写真を撮るのである。恥ずかしながら、私もやってみた。こういうものがあると、やってみたくなるのだ。
興味深かったのは、小道具の展示だった。実際に撮影に使われた小道具がいつくも展示されていた。なかなか興味深かった。

「かさいるか」ちゃんと「こさめ」ちゃんである。

チーム鮫島の関連小道具もいくつか展示されていた。

りょうちんの「カンバン」である。このような着物を地元気仙沼ではカンバンという。全国的には「まいわい」というようだ。ずっと以前、網野善彦さんが気仙沼市でこの「まいわい」に関する講演を行ったのを思い出す。もう30年程前のことだ。
最終週のりょうちんがこの「カンバン」を着るシーンは、実に感動的だった。彼は、自分自身の人生を生きる航海へと旅立とうといているのだ。
今日の一枚は、サリナ・ジョーンズの1984年作品、『ミステリー・ラブ』である。サリナ・ジョーンズはLPもCDも持っていない。けれども、このアルバムはよく聴いた。学生時代に貸しレコード屋で借りたものを録音したカセットテープで聴いたのだ。そのテープは今も持っている。サリナ・ジョーンズのことは詳しくは知らないが、このアルバムは好きだ。何度も聴いた記憶がある。このアルバムを手に入れたいが廃盤のようだ。Apple Musicでも見当たらない。いくつかあるベスト盤の一つなのかもしれない。
学生時代以来聴いていなかったサリナ・ジョーンズのことを思い出したのは、数年前、大船渡のあった頃のh.イマジンで聴いてからだ。たまたま訪れたときにかかっていたのである。それがサリナ・ジョーンズであることはすぐに分かった。細胞にインプットされているのである。それほど聴き込んだのだ。音のいいセットで聴くしばらくぶりのサリナ・ジョーンズは、なかなかのものだった。以来、『ミステリー・ラブ』を手に入れたいとずっと思っている。
1. Mystery Love
2. Up Where We Belong
3. Love Is In The Air
4. Still
5. The Way We were
6. Sentimental Journey
7. You've Got A Friend
8. Stuck On You
9. My Love
10. Antonio's Song
11. Lately
※LPから録音したのだが、どこまでがA面なのかわからない。