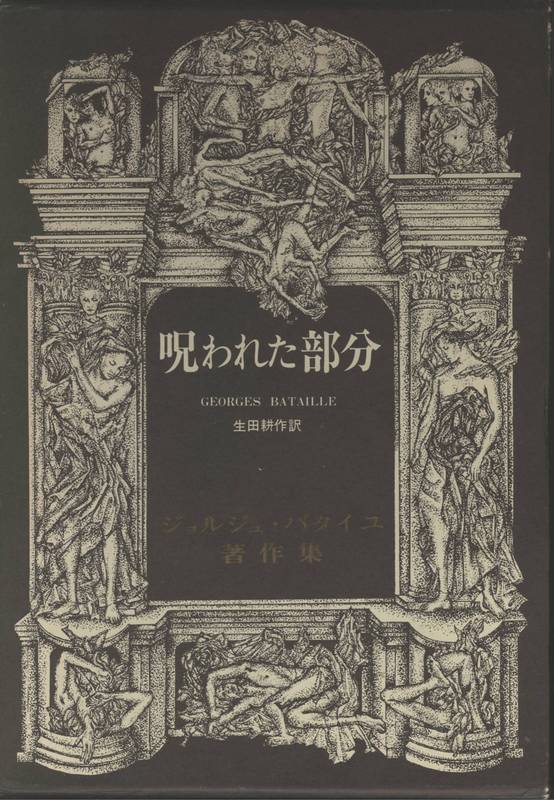●今日の一枚 410●
Queen
Sheer Heart Attack

クイーンが聴きたくなってCDを注文した。1974年リリースの『シアー・ハート・アタック』である。クイーンのレコードやカセットテープはたくさん持っているが、CDは『オペラ座の夜』のみだった。レコードプレーヤーも、カセットデッキも破損したままだったので、ずっと聴くことができなかったのだ。クイーンが聴きたくなって・・・と書いたが、正確には「ブライトン・ロック」が聴きたくなって、といった方が正確だ。「ブライトン・ロック」がクイーンの曲の中で一番好きだ。本当にご機嫌な曲だ。
クイーンはやはりすごいバンドだったのだと思う。知的で、革新的で、実験的でありながら、聴く者を拒絶するような音楽ではない。ポップで、歌心に溢れている。もちろん、だからこそ売れたのであろう。ギター少年だった私は、クイーンを聴く時はいつも、ブライアン・メイのフレーズを追っていたものだ。けれど、追随できるギタリストではなかった。実際私は、ブライアン・メイの完全コピーなどしたことはないし、してみようという考えすらもったことはなかった。エリック・クラプトンがインタビューで、あなたに弾けないフレーズなどないでしょうといわれ、そんなことはない、例えばクイーンのギタリストだ、といったのをいまでもよく憶えている。フェイズシフターやディレイを駆使した複雑なサウンドは、それを前提にしたフレーズの構成と相まって、簡単にまねできるようなものではなかったし、40年以上経過した今日にあっても、圧倒的なオリジナリティーの光を放っている。クイーンとはそういうバンドだったのではないか。そのサウンドはあくまで鑑賞すべき対象だったのであり、ひとつの完結した世界だったのだ。「ブライトン・ロック」は、そのようなブライアン・メイのギター・サウンドのエッセンスが凝縮されたナンバーだと思う。
ところで、「ブライトン・ロック」に続いて2曲目に収録されている「キラー・クイーン」である。ポップで、ギター・アンサンブルが魅力的な、全英2位に輝くヒット曲だ。もちろん、好きな曲だ。いい曲だと思う。この曲の、She's Killer Queen Gunpowder,gelatine いう部分について、大学時代の友人に「キラー・クイーン、がんばれタブチ」って聞えるんだよねといわれてショックを受けたことを昨日のように思い出す。このことは、当時は多くの人たちの間に流布していたようであるが、私にはまったく思いもかけなかったことだった。ある種の芸術性をもった崇高な存在と考えていたクイーンの世界と、漫画のタイトルであり流行語でもあった「がんばれタブチ」が並列的に並べられたことについて、純粋なショックを受けたものだ。それ以来、「キラー・クイーン」を聴くたびに「がんばれタブチ」が想起されるようになり、30年以上たった現在でもそれは変わらない。
げに恐ろしきは大衆であり、民衆的世界である。