昨日は曇り空から時おり雨の降る寒い夕方、5時過ぎから奈良国立博物館

6月9日迄『国宝の殿堂 藤田美術館展 曜変天目と仏教美術のきらめき』へ。

通常の閉館は午後5時までですが金曜日は午後7時迄で、明日からの10連休を
控え、悪天候もあり空いて、ゆっくりと閉館まで鑑賞することが出来ました。

大阪城の目の前にある「藤田美術館」は、明治になり海外へ散逸する古美術品の
数々を憂った明治の実業家・藤田傳三郎氏と子息の三人で私財を投じ収集され、
国宝9件、重要文化財53件を含む日本・東洋美術品の宝庫で、昭和29年に開館、
現在当館は耐震等の改修中で、2022年4月にリニューアルオープンの予定です。
新東館、九章から構成され、前期は国宝6件、重要文化財39件を含む100件
第一章 【曜変天目茶碗と茶道具】
1.交趾大亀香合(こうちおおがめこうごう) 中国・明17世紀 重文
大型の香合で付属の盆に利休居士の花押が、藤田傳三郎氏が亡くなる直前に落札。
 交趾大亀香合
交趾大亀香合
2.白釉油滴天目鉢 中国・金(12~13世紀) 重文
3.菊花天目茶碗 室町時代16世紀 重文
4.御所丸黒刷毛目茶碗 銘 夕陽 朝鮮王朝17世紀 重文
5.本手利休斗々屋茶碗 朝鮮王朝16世紀
6.大井戸茶碗 銘 蓬莱 朝鮮王朝16世紀
7.古瀬戸肩衝茶入 銘 在中庵 室町時代15~16世紀 重文
元は仕覆8種、牙蓋も8種あったそうですが、今回の展示は仕覆4種、蓋6種
さらにこの茶入れのためだけに使用する『在中庵棚』まであるとは・・・
小堀遠州が55回の茶会で使用した愛蔵品
確かに丁度いいくらいにやや大振りで端正な形の撫で肩の肩衝素晴らしい!
8.古銅角木花入 中国・明15~16世紀
9.古伊賀花生 銘 寿老人 安土桃山時代16~17世紀 重文
10.古芦屋春日野釜 室町時代15世紀
11.曜変天目茶碗 中国・南宋12~13世紀 国宝

 曜変天目茶碗
曜変天目茶碗
第2章 【墨蹟と古筆】
12.紫門新月図(さいもんしんげつず) 室町 応永12年1405年国宝
送別の杜甫の詩から描かれ、18人の禅僧が漢詩を寄せ書きする
 紫門新月図
紫門新月図
14.大燈国師墨蹟 偈語 鎌倉時代14世紀 重文
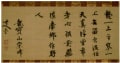 大燈国師墨蹟
大燈国師墨蹟
16.物初大観墨蹟(もつしょ) 山隠語 中国・南宋 1268年 重文
19.深窓秘抄 平安時代11世紀
 深窓秘抄
深窓秘抄
21.古今和歌集巻第十八断簡(高野切) 平安時代11世紀 重文
23.十五番歌合断簡 平安時代11世紀 重文
『今こむと 言ひしばかりに ながつきの
ありあけの月を 待でつるかな』 素性(良峯玄利)
 十五番歌合断簡
十五番歌合断簡
25.古今和歌集断簡 筋切 通切 平安時代12世紀 重文
第三章【物語絵と肖像】
29.阿字義 平安時代12世紀 重文
33.玄奘三蔵絵 巻第一・二 国宝
 玄奘三蔵絵 巻第一
玄奘三蔵絵 巻第一
35.両部大経感得図 藤原宗弘筆 平安時代 1136年 国宝
 両部大経感得図
両部大経感得図
47.駿牛図断簡 鎌倉時代13~14世紀
48.大江山酒呑童子絵巻 菱川師宣筆 江戸時代1692年
部屋を変ります。
第四章 【仏像】
49.地蔵菩薩立像 快慶作 木造彩色・截金 鎌倉13世紀 重文
 地蔵菩薩立像
地蔵菩薩立像
56.空也上人立像 南北朝~室町時代14~15世紀
第五章 【尊像と羅漢】
59.仏像彩画円柱 8本 鎌倉時代13世紀
 仏像彩画円柱
仏像彩画円柱
77.十六羅漢図 詫麿栄賀筆 南北朝時代14世紀 重文
第六章 【荘厳と法具】
87.仏功徳蒔絵経箱 平安時代11世紀 国宝
 仏功徳蒔絵経箱
仏功徳蒔絵経箱
96.金銅密教法具 鎌倉~室町時代13~14世紀 重文
第七章 【仏典】
97.大般若経(薬師寺経)奈良時代8世紀 国宝
 大般若経
大般若経
103.法華経勧発品(装飾経)平安~鎌倉時代 12~13世紀 重文
第八章 【面と装束】
109-1.伎楽面 酔胡従 相李魚成作 奈良時代8世紀 重文
109-2.伎楽面 力士 奈良時代8世紀 重文
第九章 【多彩な美の殿堂】
116.唐鞍 鎌倉時代14世紀 重文
117.山水蒔絵手箱 銘 鹿苑寺 鎌倉~南北朝時代 重文
118.錆絵絵替角皿 尾形乾山作 尾形光琳画 江戸時代18世紀 重文
119.色絵輪宝鶏麿文香炉 伝野々村仁清作 江戸時代17世紀
124.小太刀 銘 国行 鎌倉時代13世紀 重文
127.埴製枕 古墳時代4世紀 重文
128.歯車形碧玉製品 古墳時代4世紀 重文
一気に鑑賞させて頂いたが疲れました。
でも二時間では足りない・・・。

6月9日迄『国宝の殿堂 藤田美術館展 曜変天目と仏教美術のきらめき』へ。

通常の閉館は午後5時までですが金曜日は午後7時迄で、明日からの10連休を
控え、悪天候もあり空いて、ゆっくりと閉館まで鑑賞することが出来ました。

大阪城の目の前にある「藤田美術館」は、明治になり海外へ散逸する古美術品の
数々を憂った明治の実業家・藤田傳三郎氏と子息の三人で私財を投じ収集され、
国宝9件、重要文化財53件を含む日本・東洋美術品の宝庫で、昭和29年に開館、
現在当館は耐震等の改修中で、2022年4月にリニューアルオープンの予定です。
新東館、九章から構成され、前期は国宝6件、重要文化財39件を含む100件
第一章 【曜変天目茶碗と茶道具】
1.交趾大亀香合(こうちおおがめこうごう) 中国・明17世紀 重文
大型の香合で付属の盆に利休居士の花押が、藤田傳三郎氏が亡くなる直前に落札。
 交趾大亀香合
交趾大亀香合2.白釉油滴天目鉢 中国・金(12~13世紀) 重文
3.菊花天目茶碗 室町時代16世紀 重文
4.御所丸黒刷毛目茶碗 銘 夕陽 朝鮮王朝17世紀 重文
5.本手利休斗々屋茶碗 朝鮮王朝16世紀
6.大井戸茶碗 銘 蓬莱 朝鮮王朝16世紀
7.古瀬戸肩衝茶入 銘 在中庵 室町時代15~16世紀 重文
元は仕覆8種、牙蓋も8種あったそうですが、今回の展示は仕覆4種、蓋6種
さらにこの茶入れのためだけに使用する『在中庵棚』まであるとは・・・
小堀遠州が55回の茶会で使用した愛蔵品
確かに丁度いいくらいにやや大振りで端正な形の撫で肩の肩衝素晴らしい!
8.古銅角木花入 中国・明15~16世紀
9.古伊賀花生 銘 寿老人 安土桃山時代16~17世紀 重文
10.古芦屋春日野釜 室町時代15世紀
11.曜変天目茶碗 中国・南宋12~13世紀 国宝

 曜変天目茶碗
曜変天目茶碗第2章 【墨蹟と古筆】
12.紫門新月図(さいもんしんげつず) 室町 応永12年1405年国宝
送別の杜甫の詩から描かれ、18人の禅僧が漢詩を寄せ書きする
 紫門新月図
紫門新月図14.大燈国師墨蹟 偈語 鎌倉時代14世紀 重文
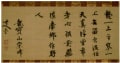 大燈国師墨蹟
大燈国師墨蹟16.物初大観墨蹟(もつしょ) 山隠語 中国・南宋 1268年 重文
19.深窓秘抄 平安時代11世紀
 深窓秘抄
深窓秘抄21.古今和歌集巻第十八断簡(高野切) 平安時代11世紀 重文
23.十五番歌合断簡 平安時代11世紀 重文
『今こむと 言ひしばかりに ながつきの
ありあけの月を 待でつるかな』 素性(良峯玄利)
 十五番歌合断簡
十五番歌合断簡25.古今和歌集断簡 筋切 通切 平安時代12世紀 重文
第三章【物語絵と肖像】
29.阿字義 平安時代12世紀 重文
33.玄奘三蔵絵 巻第一・二 国宝
 玄奘三蔵絵 巻第一
玄奘三蔵絵 巻第一35.両部大経感得図 藤原宗弘筆 平安時代 1136年 国宝
 両部大経感得図
両部大経感得図47.駿牛図断簡 鎌倉時代13~14世紀
48.大江山酒呑童子絵巻 菱川師宣筆 江戸時代1692年
部屋を変ります。
第四章 【仏像】
49.地蔵菩薩立像 快慶作 木造彩色・截金 鎌倉13世紀 重文
 地蔵菩薩立像
地蔵菩薩立像56.空也上人立像 南北朝~室町時代14~15世紀
第五章 【尊像と羅漢】
59.仏像彩画円柱 8本 鎌倉時代13世紀
 仏像彩画円柱
仏像彩画円柱77.十六羅漢図 詫麿栄賀筆 南北朝時代14世紀 重文
第六章 【荘厳と法具】
87.仏功徳蒔絵経箱 平安時代11世紀 国宝
 仏功徳蒔絵経箱
仏功徳蒔絵経箱96.金銅密教法具 鎌倉~室町時代13~14世紀 重文
第七章 【仏典】
97.大般若経(薬師寺経)奈良時代8世紀 国宝
 大般若経
大般若経103.法華経勧発品(装飾経)平安~鎌倉時代 12~13世紀 重文
第八章 【面と装束】
109-1.伎楽面 酔胡従 相李魚成作 奈良時代8世紀 重文
109-2.伎楽面 力士 奈良時代8世紀 重文
第九章 【多彩な美の殿堂】
116.唐鞍 鎌倉時代14世紀 重文
117.山水蒔絵手箱 銘 鹿苑寺 鎌倉~南北朝時代 重文
118.錆絵絵替角皿 尾形乾山作 尾形光琳画 江戸時代18世紀 重文
119.色絵輪宝鶏麿文香炉 伝野々村仁清作 江戸時代17世紀
124.小太刀 銘 国行 鎌倉時代13世紀 重文
127.埴製枕 古墳時代4世紀 重文
128.歯車形碧玉製品 古墳時代4世紀 重文
一気に鑑賞させて頂いたが疲れました。
でも二時間では足りない・・・。









































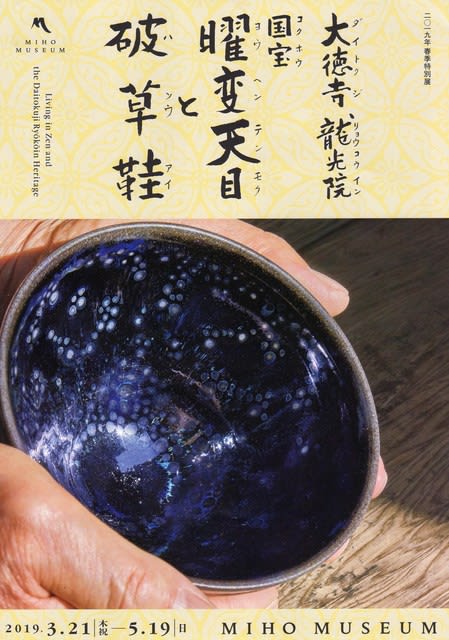



 4/5
4/5













 4/4
4/4










