梅雨明け(したとみられる)は嬉しい
今年は7月19日、平年より一日遅く、昨年より3日早い
気温は高くても日陰に入ると涼しい
梅雨前線が太平洋へと南下し、北の高気圧に覆われたからか
 7/20
7/20 👆若草山 👆御蓋山 👆高円山
しかし やらなくってはいけない事が
梅の土用干し
炉灰は篩にかけて桶に入ったまま
湿し灰作りをしなければ・・・・・
さて七月に入り「名水点」
「洗い茶巾」
「葉蓋」と・・・夏のお稽古を
軸は「瀧直下三千丈」
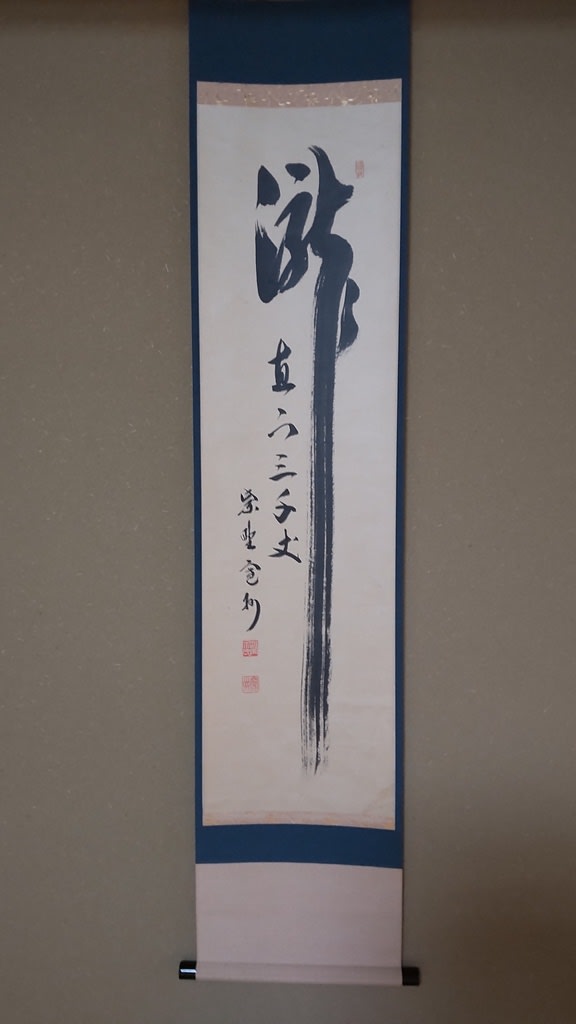
半夏生、八重の木槿を宗全籠に

主菓子は「鵲の橋」
中国の七夕伝説では、織姫と彦星を七夕の日に逢わせるため
たくさんのかささぎが翼を連ねて橋を作ったとされ
天の川をさす言葉から

「観世水・かんぜみず」
水が渦巻いている様子を描く流水文様の1つ
由来は能楽の流派「観世流」の観世太夫が定式文様として使用したことから

文月も残り一週間ほど、祇園さんも24日の後祭の山鉾巡行
24日・25日と大阪の天満宮「天神祭 」と関西は賑わいます
浮かれてばかりでは・・・気を引き締めて
八月にかけては「茶箱」のお稽古をしたいと思います










 2014.7.17
2014.7.17






