

子供様のため、一か月ぶりに、お稽古に来られます。
ジャーマン・アイリスで玄関を飾ってみました。
曇り空なのに、華やかになりました。


ジャーマン・アイリスは別名でドイツアヤメと言われます。
文目(あやめ:菖蒲 綾目)(Siberian iris)
Iris:ギリシャ語で【虹】のこと
ゼウスの妻の侍女「イリス」は、ヘラから7色の首輪を与えられて「虹の女神」となったことから。
文目: 剣形の葉がきちんと並んで生える葉の様子から、文目(筋道、模様の意)と言われる。
綾目: 花弁の基の黄色部分の縞(しま)模様を「綾目」の字で表わしています。
菖蒲:しょうぶとも読まれることもあるが、「文目」と「菖蒲」は別種でややこしいです。
「いずれ文目か杜若」 :区別できないことのたとえとしてよく使われますね。

庭の梶の木(雄花)
数年前に冷泉家が遺す七夕の行事(なごみ、茶のあるくらし 2007.7七夕に遊ぶ)を読み、
梶の葉に和歌をしたためる遊びや、短冊として、いつかは茶事に取り入れたいと思い、
小さな梶の苗木を植えておりました。

日々なにかと忙しく、顧みることがなく、忘れておりましたが、夏のような暑さに、
庭に水を撒いているとき、何気に目に留まりました。
写真を撮り、調べてみると、雌雄あり、我が家の梶の木は雄花です。
古代から神に捧げる神木として尊ばれていた為、神社の境内などに多く生えられ、
主として神事に用い供え物の敷物に使われるそうで、家紋にも取り入れられています。
また和紙の原料(クワ科コウゾ属)にもなるそうです。
後拾遺和歌集』に「天の川とわたる船の梶の葉に思ふ事ことをも書きつくるかな」


可憐な花で、一度茶花に使いたいと思っていましたが、
ハナニラと言います。
臭いのある花はだめなんです。残念!
ニラの花は夏に咲くんですね。
今庭に咲いている花はハナニラで、外見もよく似たネギ科ハナニラ属の標準和名で「花ニラ」(別名アイフェイオン)とされております。この花ニラは食べられません。
同じ名称でややこしいですよね。この園芸で親しまれている花ニラは花茎の先に花が1つ開くのに対し、
食用の花ニラは花茎の先に小さな葱坊主のようなものができ、開くと小さな花が沢山展開します。

この天気に誘われて、カナブンがつつじの花に

今日のお稽古の主菓子で、浮島です。
急いでおり、切り口が・・・
朝は3人の方が、
お昼からはお茶会の御濃茶をしていただくため、練習をされます。
庭のナルコユリ(鳴子ユリ)が咲きました。
お床に使ってみました。


庭の鳴子百合 (なるこゆり)
草姿や花の様子がこの「鳴子(なるこ)」に似ていてユリの仲間なのでこの名があります。
花言葉:「元気を出して」「心の痛みの分かる人」だそうです。
鳴子とは:長い縄に板と竹を結びつけて沢山並べてぶら下げ、
揺らすと音がするようにした道具です。稲を荒らす鳥などを追い払う目的や、
侵入者を知る目的などに使用したものです。
狂言では演目のひとつで、鳴子番をする人物を演じて農業の予祝をしますが、
「引くもの尽くしや 名所尽くし」の謡を聞くうちに、
舞台いっぱいに実り豊かな田園風景が広がるところで終わります。
今朝は自分の御稽古に伺います。
真の行台子の日になってしまいました。
毎日のように時間を見つけて練習はしましたが、抜けることがあるかも。
朝からイメージトレーニングしています。
昨日の続きで失礼します。
英一蝶、という美しい名前をもった画家をご存知でしすか。

僧正遍昭落馬図(江戸時代中期、承応1-享保9)英一蝶
古今和歌集に収められている遍照の和歌が絵画化されています。
名にめでて折れるばかりぞ女郎花 われ落ちにきと人に語るな (古今和歌集秋上)
一蝶が交友した其角は次のように詠んでいます
牛に乗る嫁御落とすな女郎花
疾駆する馬のたくましい力動感
前のめりの落馬した僧正遍昭の姿および表情
見とれた女郎花(おみなえし)の楚々とした風情
:万葉集では「姫押」「美人部師」「佳人部爲」などの字が宛てられているように、容姿の美しい女性に喩えられた花です。
その後、僧をも堕落させる妖しくも美しい女というイメージに変化して行くそうです。
この三位一体のすばらしい構成が江戸中期の美意識を物語りますね
。
このことは英一蝶の生涯にかかわっているのですね。
一蝶と名乗ったのは、三宅島から恩赦をうけ江戸にもどるときの船の中で、一匹の蝶を見つけ、それまでの朝湖の名を捨てて一蝶と名のるようになったということで、英(はなぶさ)は母の姓の花房からとられいるそうです。
俳諧を好み、其角や芭蕉とも交流し、浮世絵も志しており、はたまた遊郭の太鼓持ち、
偽物も多数出回っているぐらい有名だそうです。お気をつけてください。
真の行台子の日になってしまいました。
毎日のように時間を見つけて練習はしましたが、抜けることがあるかも。
朝からイメージトレーニングしています。
昨日の続きで失礼します。
英一蝶、という美しい名前をもった画家をご存知でしすか。

僧正遍昭落馬図(江戸時代中期、承応1-享保9)英一蝶
古今和歌集に収められている遍照の和歌が絵画化されています。
名にめでて折れるばかりぞ女郎花 われ落ちにきと人に語るな (古今和歌集秋上)
一蝶が交友した其角は次のように詠んでいます
牛に乗る嫁御落とすな女郎花
疾駆する馬のたくましい力動感
前のめりの落馬した僧正遍昭の姿および表情
見とれた女郎花(おみなえし)の楚々とした風情
:万葉集では「姫押」「美人部師」「佳人部爲」などの字が宛てられているように、容姿の美しい女性に喩えられた花です。
その後、僧をも堕落させる妖しくも美しい女というイメージに変化して行くそうです。
この三位一体のすばらしい構成が江戸中期の美意識を物語りますね
。
このことは英一蝶の生涯にかかわっているのですね。
一蝶と名乗ったのは、三宅島から恩赦をうけ江戸にもどるときの船の中で、一匹の蝶を見つけ、それまでの朝湖の名を捨てて一蝶と名のるようになったということで、英(はなぶさ)は母の姓の花房からとられいるそうです。
俳諧を好み、其角や芭蕉とも交流し、浮世絵も志しており、はたまた遊郭の太鼓持ち、
偽物も多数出回っているぐらい有名だそうです。お気をつけてください。

名品図録より
婦人像(重要文化財)桃山時代

魯山人が一時所有され、表装も直されておりなかなか斬新な表具であり、
数珠を持たれており法要の様子をあらわしており、辻が花の着物を身に着けた女性の強い視線が、
魯山人の好みだったのでしょう。
婦女遊楽図屏風(松浦屏風、六曲一双)

ほぼ左右対称に描かれ、腰高な女性が背筋を伸ばし背景に影がなく、西洋人的な雰囲気が醸し出されており、キリスト教における受胎告知を表す場面も垣間見られるとのことでした。
学芸員のすばらしい説明は、描かれた時代背景や作者の意図がより深く理解できました。
大和文華館の春をきりとりました。

エントランス:入り口から坂道を上がります。
つつじやしゃくなげが咲きだしております。


ヤマブキ

ハナミズキ
”吾輩は猫である”の挿絵が不折先生だったとは

春 江 漁 楽 図

中村不折画伯
昭和18年に78歳で逝去されておられます。台東区に書道博物館内に不折記念館があるそうです。
なおお稽古は30代の女性お二人の予定が、
子供さんのお病気のためお一人は休みとなりました。
透木釜でお薄の運び点前をしました。

春 江 漁 楽 図

中村不折画伯
昭和18年に78歳で逝去されておられます。台東区に書道博物館内に不折記念館があるそうです。
なおお稽古は30代の女性お二人の予定が、
子供さんのお病気のためお一人は休みとなりました。
透木釜でお薄の運び点前をしました。
禅宗寺院でのお茶は、先人の遺徳を偲び、修道の方便、心のいましめとしていただきたいとのことです。

四頭茶会(よつがしらちゃかい)とは
四人の正客に準じて相伴客が茶をいただく、広間での作法が大体近いそうですが、
一般大衆に呈茶する普茶とは違い、特別にお招きする客のための
天目台と天目茶碗を使う貴人扱いをする特為茶(とくいさ)です。
この茶会では一般公開の形のため、特為茶と普茶の二面を同時に会得できました。
この式に斎飯(おとき)を併用すると、お茶の懐石と比較されて興味あるものになるそうです。
お点前と菓子のお運びなどは、四人の寺僧【供給(くきゅう)】が行います。
水屋と寺僧の間の取り次ぎをする役は【堤給(ていきゅう)】寺務諸役の従業員【行者(あんじゃ)】非僧が当たっていました。
正客と相伴客が所定の位置につくと、

座席配置図というべき照牌(しょうはい)が室外に用意されているので席に入る前に自分の位置がよくわかります。

【侍香(じこう)】役の僧が入堂し、
正面ご開山の画像の前で一香を献じられ、
中央卓前へ退いて、左右両手で一度ずつ焼香して席を清められました。
【供給】は
縁高に入った菓子と、お茶の入った天目茶碗とを運ばれました。
各々の客の前でお点前をされました。
*正客と相伴客との区別は
正客 の前:胡跪(こき)【左立膝の姿勢】していました。
相伴客の前:立ったままでした。
飾り付け
写真が撮れないので下図を参照してください。
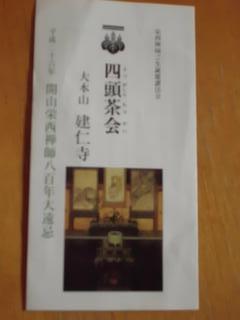
中央の掛け軸はご開山栄西禅師のお姿絵【頂相(ちんそう)】で、
のちの禅僧の墨跡や、茶道家元等の書におきかえられたそうです。
頂相の左右には龍虎図、室町時代の画家秋月筆だそうです。
室正面中央に螺鈿の前卓あり、
中央に中国から渡来した螺鈿の香炉台と青磁の香炉が飾られています。
他の写真です。






雨の中、牡丹が咲き始めていました。

四頭茶会(よつがしらちゃかい)とは
四人の正客に準じて相伴客が茶をいただく、広間での作法が大体近いそうですが、
一般大衆に呈茶する普茶とは違い、特別にお招きする客のための
天目台と天目茶碗を使う貴人扱いをする特為茶(とくいさ)です。
この茶会では一般公開の形のため、特為茶と普茶の二面を同時に会得できました。
この式に斎飯(おとき)を併用すると、お茶の懐石と比較されて興味あるものになるそうです。
お点前と菓子のお運びなどは、四人の寺僧【供給(くきゅう)】が行います。
水屋と寺僧の間の取り次ぎをする役は【堤給(ていきゅう)】寺務諸役の従業員【行者(あんじゃ)】非僧が当たっていました。
正客と相伴客が所定の位置につくと、

座席配置図というべき照牌(しょうはい)が室外に用意されているので席に入る前に自分の位置がよくわかります。

【侍香(じこう)】役の僧が入堂し、
正面ご開山の画像の前で一香を献じられ、
中央卓前へ退いて、左右両手で一度ずつ焼香して席を清められました。
【供給】は
縁高に入った菓子と、お茶の入った天目茶碗とを運ばれました。
各々の客の前でお点前をされました。
*正客と相伴客との区別は
正客 の前:胡跪(こき)【左立膝の姿勢】していました。
相伴客の前:立ったままでした。
飾り付け
写真が撮れないので下図を参照してください。
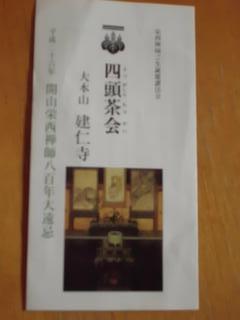
中央の掛け軸はご開山栄西禅師のお姿絵【頂相(ちんそう)】で、
のちの禅僧の墨跡や、茶道家元等の書におきかえられたそうです。
頂相の左右には龍虎図、室町時代の画家秋月筆だそうです。
室正面中央に螺鈿の前卓あり、
中央に中国から渡来した螺鈿の香炉台と青磁の香炉が飾られています。
他の写真です。






雨の中、牡丹が咲き始めていました。
四頭の作法は、茶道を志す人は勿論のこと、日本の古文化に多少でも関心のある人の必見の儀式だそうで、機会があれば行きたい茶会でありました。
建仁寺四頭茶会は

建仁寺で四頭式という珍しい伝統技法で茶会が開かれ、 もともとは栄西禅師は中国から茶の種を持ち帰り、喫茶の作法を広め、茶祖としても知られ、 その生誕日に茶会で遺徳を偲ぶものだそうです。

今朝もまた雨、着物を着ていくつもりが、平服で失礼しました。
八百人ほどの参列者の予定だそうです。
八時半過ぎにつき、受付を済まし、四頭本席の受付に急ぎましたが、雨のためやや遅れており、案内もあり
復席へと伺いましたが、もうすでに次席となり、右往左往しました。

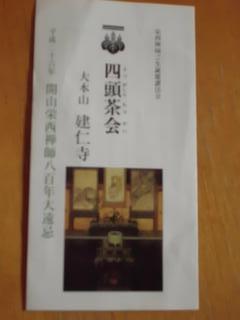
境内は広いですね。

四頭本席拝服、大方丈にて

主菓子:そば粉と抹茶餡

復席は2席あり、霊洞院で表千家様と久昌院では裏千家さまが担当されていました。

煎茶席、両足院にて花月菴家元
茶碑前番茶席:抹茶樹徳せんべい、祇園辻利

帰りついたら5時過ぎでした。
【追加】4月22日にも、次のように記しております。
『四頭茶会とはどんなものなんでしょうか』2.24.2016
建仁寺四頭茶会は

建仁寺で四頭式という珍しい伝統技法で茶会が開かれ、 もともとは栄西禅師は中国から茶の種を持ち帰り、喫茶の作法を広め、茶祖としても知られ、 その生誕日に茶会で遺徳を偲ぶものだそうです。

今朝もまた雨、着物を着ていくつもりが、平服で失礼しました。
八百人ほどの参列者の予定だそうです。
八時半過ぎにつき、受付を済まし、四頭本席の受付に急ぎましたが、雨のためやや遅れており、案内もあり
復席へと伺いましたが、もうすでに次席となり、右往左往しました。

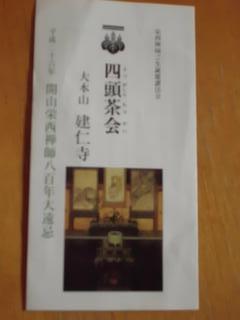
境内は広いですね。

四頭本席拝服、大方丈にて

主菓子:そば粉と抹茶餡

復席は2席あり、霊洞院で表千家様と久昌院では裏千家さまが担当されていました。

煎茶席、両足院にて花月菴家元
茶碑前番茶席:抹茶樹徳せんべい、祇園辻利

帰りついたら5時過ぎでした。
【追加】4月22日にも、次のように記しております。
『四頭茶会とはどんなものなんでしょうか』2.24.2016













