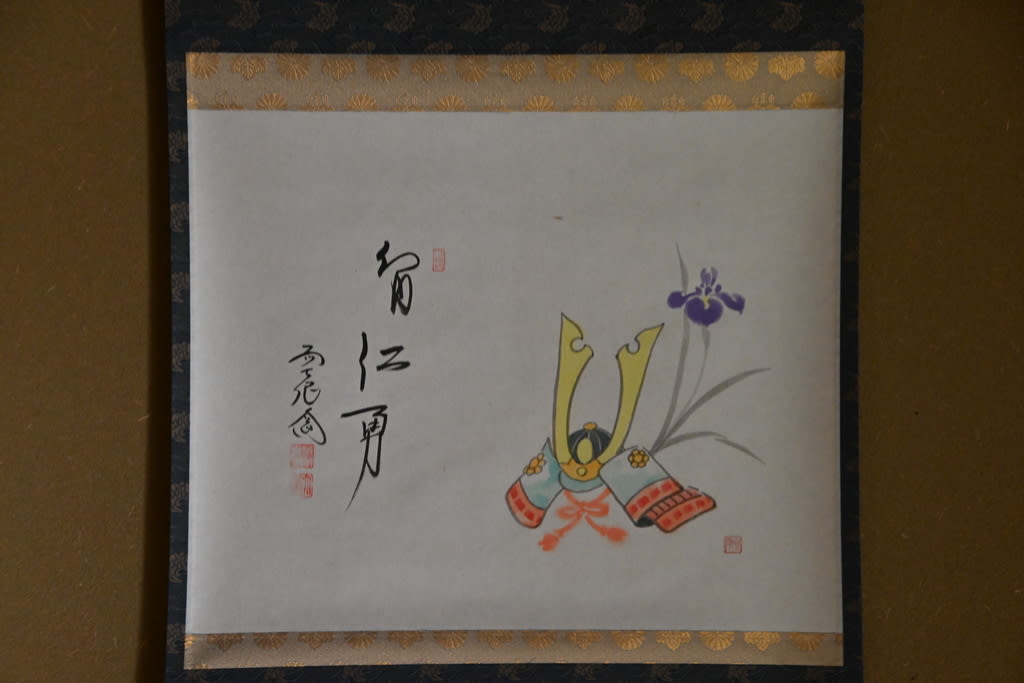今年も桜の季節に訪れられなかった吉野山
梅雨の晴れ間に、歩きにやってきました
近鉄橿原神宮前駅から吉野線に乗り換えて
急行に乗ったはずなのに
神宮前からは各駅停車、小一時間の旅
岡寺→飛鳥→壷阪→市尾→葛→吉野口→薬水→福神→
大阿太→下市口→越部→六田→上市→吉野神宮→吉野

コトコト揺られながらこの歌を思い出しました
『倭は 国の真秀ろば たたなづく
青垣 山籠れる 倭しうるわし』
「倭建命」が亡くなる前に故郷大和を思って詠んだ歌
大和は緑が美しい 特にこの季節は最高
そして目的地である吉野山
ここも歴史に上る話題がいっぱい

吉野の桜の由来は『役行者』で
修行によって日本独自の仏『金剛蔵王権現』を
祈り始めた時その姿を山桜の木で刻まれた事にあり

金峯山寺蔵王堂、金剛蔵王権現
その後 信者たちにより献木として
植えつづけられ花の吉野ができたと
平安時代には桜の名所に
西行も吉野に籠り

西行庵
西行を慕う芭蕉も二度も訪れた苔清水・・・

左に「松尾芭蕉」の句碑がある。
「春雨の 木下(こした)につたふ 清水哉」芭蕉(笈の小文より)
「春雨の 木下(こした)につたふ 清水哉」芭蕉(笈の小文より)

古代においては「大海人皇子」が吉野に潜行
"大海人皇子が勝手神社の社殿で琴を奏でたところ、
天女が舞い降り、袖を振りながら舞を披露したと
勝手神社の背後の山は「袖振山」です。
義経と静御前のつかの間の逢瀬も・・・
金峰神社左奥の方にある『義経隠れ塔』がある
追手から屋根を蹴破り逃げたことから
『蹴破りの塔』という別名もあるが
時間の都合上、今回は訪れていない
一人静御前は吉野山で捕らえられ、
勝手神社・神楽殿で舞った「舞塚」も境内にある。
謡曲「二人静」の筋書きは
謡曲「二人静」の筋書きは
「勝手神社」で 静御前の霊が、菜摘女に取り憑いて
舞を舞い、回向を頼んで消えて行くと・・・
二人静・フタリシズカの花の名の由来はこの謡曲からと
フタリシズカの花言葉は「いつまでも一緒に」
静御前の切ない思いが・・・
吉野水分神社境内から奥の千本にかけたくさん見られた。


大塔宮護良親王が鎌倉幕府倒幕のため挙兵し
楠木正成と吉野を城塞化のため堀を築いたとされる
一万の敵の軍勢を3000人で一週間持ちこたえたが
高野山へ落ち延びられ、その後討幕するも・・・
足利尊氏に捕らえられ、鎌倉で亡くなっている
ケーブル吉野山駅の近くにその堀跡がある
現在は朱塗りの橋が架けられていた
その先に高野山と伊勢への分かれ道になる

吉野山を訪れれば、日本史の勉強にもなりますね