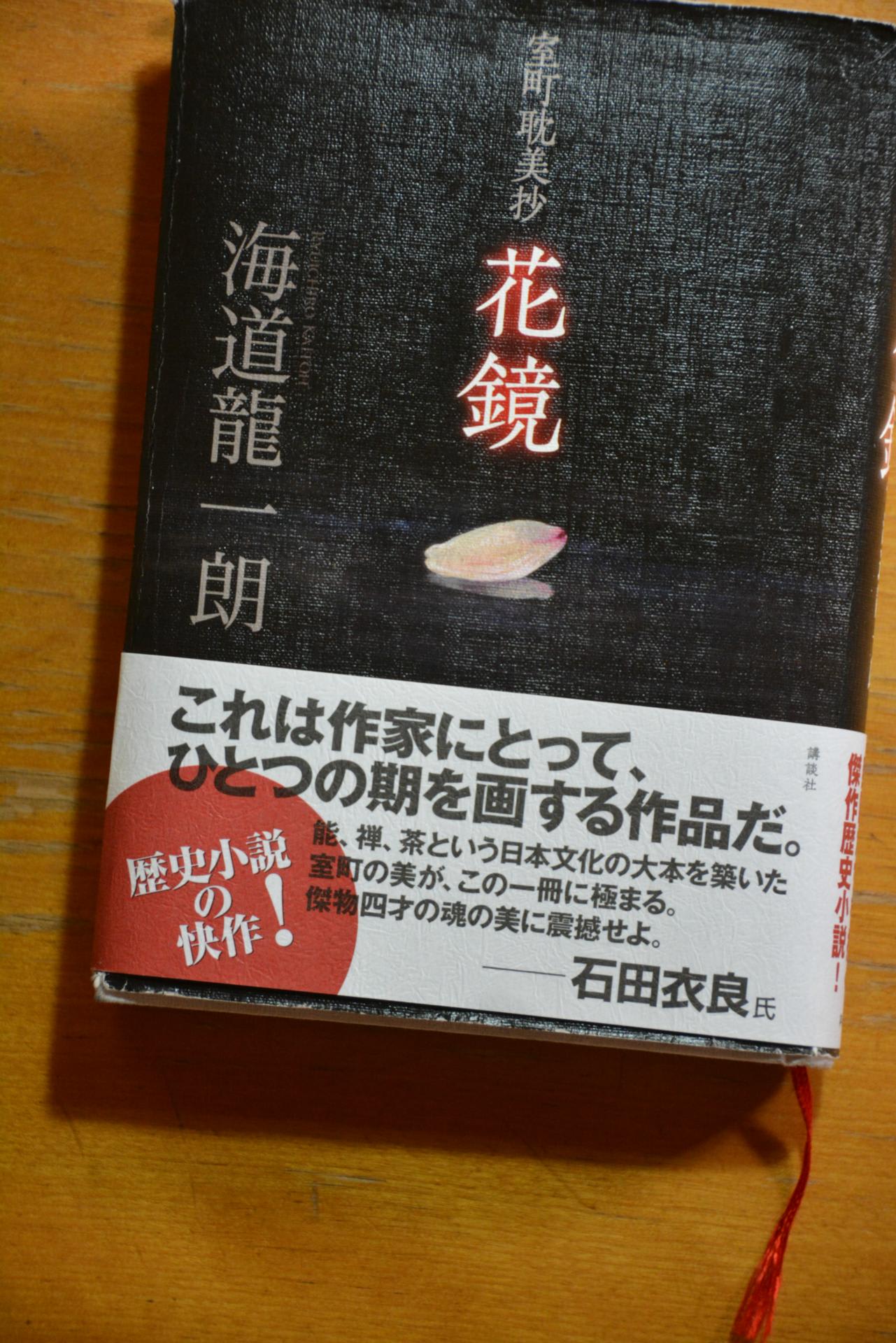お稽古日の変更の電話が入り、明日の午後からでしたら
私にも空いた時間があり、お稽古をすることに。



お軸は『春嬉』
鈴香合は炷儘入で、可愛くてつい手元に。
干菓子は、柴舟と『のし柿』(つちや、大垣)を


『のし柿』の表包装は、赤地に白抜きの文字が。
『旅人の縁(よすが)と なりて久し のし柿』




柿色の『のし柿』が1包みに2枚入っており、
薄い板状でゼリー様を呈しています。
口の中では、素朴な甘さとともに、
ほんのりと柿の風味が懐かしい味です。
のし柿は「干し柿の王様」と呼ばれる堂上蜂屋柿を
羊羹と共に練り上げて作られており、
以前いただいたことのある、竹を割った容器入りの
有名な『柿羊羹』が思いだされました。
”お構いできませんが、またおいで下さい”
なお大垣は、松尾芭蕉の「奥の細道」むすびの地ですね。
結びの句としは
『蛤の ふたみにわかれ 行秋ぞ』
を遺しております。
また『笈日記』では、
『香を探る 梅に家見る 軒端哉』
と詠まれ、梅の開花には少し早いですが、
床に合っていますね。


私にも空いた時間があり、お稽古をすることに。



お軸は『春嬉』
鈴香合は炷儘入で、可愛くてつい手元に。
干菓子は、柴舟と『のし柿』(つちや、大垣)を


『のし柿』の表包装は、赤地に白抜きの文字が。
『旅人の縁(よすが)と なりて久し のし柿』




柿色の『のし柿』が1包みに2枚入っており、
薄い板状でゼリー様を呈しています。
口の中では、素朴な甘さとともに、
ほんのりと柿の風味が懐かしい味です。
のし柿は「干し柿の王様」と呼ばれる堂上蜂屋柿を
羊羹と共に練り上げて作られており、
以前いただいたことのある、竹を割った容器入りの
有名な『柿羊羹』が思いだされました。
”お構いできませんが、またおいで下さい”
なお大垣は、松尾芭蕉の「奥の細道」むすびの地ですね。
結びの句としは
『蛤の ふたみにわかれ 行秋ぞ』
を遺しております。
また『笈日記』では、
『香を探る 梅に家見る 軒端哉』
と詠まれ、梅の開花には少し早いですが、
床に合っていますね。