今年の十五夜は満月より一日早い9月17日
唐招提寺でお月見
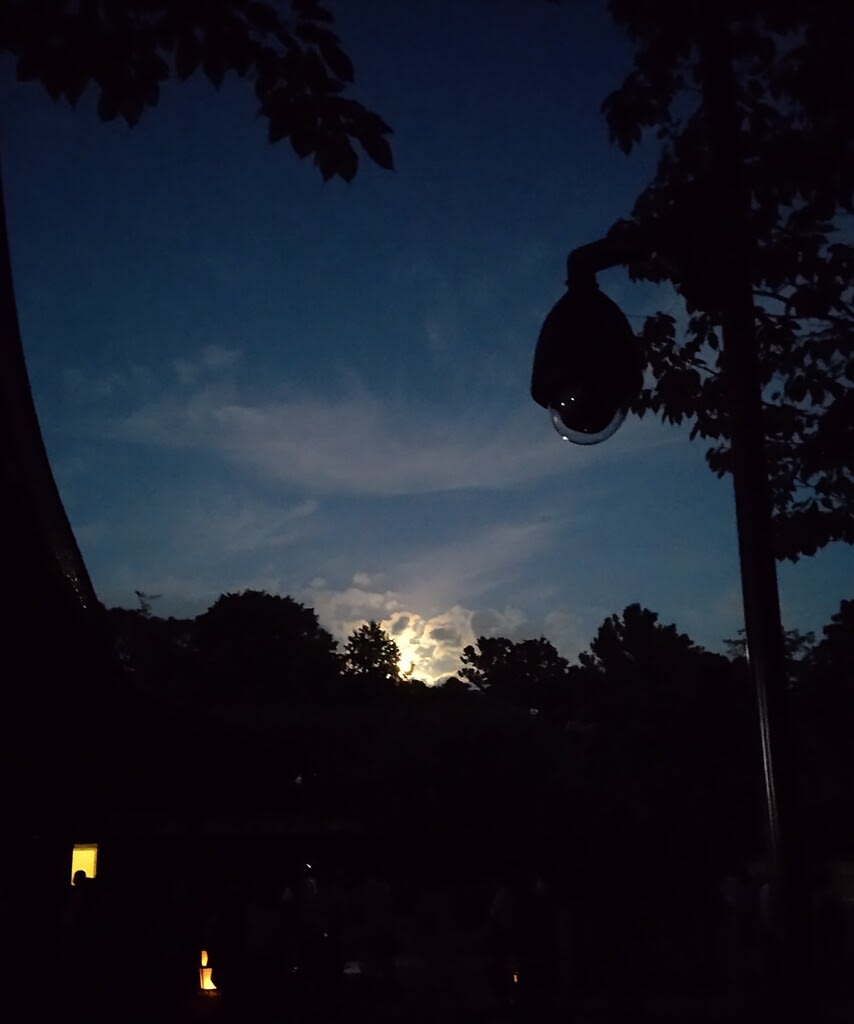
翌18日の満月は、若草山の北の山稜から

7月、8月は茶箱点前が主でしたので
電熱で失礼させていただいた社中のお稽古
涼しくなってきましたので
久しぶりに風炉の灰を切り
炭を熾し濡れ釜かければ
ぱちぱち炭の音に匂い
やはり落ち着きますね
今月の上のお稽古は「大円の草」
四ヶ伝のお稽古は「和巾」「盆点」
小習のお稽古は「長緒」「大津袋」「荘り物」
とお稽古してきましたが
もう神無月「中置」になりますね
「大円の草」
唐物茶入れと和物茶入れ二種の濃茶
大円盆に茶入れ二種、台天目を載せ
水指;瀬戸一重口、蓋置;竹、建水;唐金、茶杓;行
「和巾」
古帛紗に由緒のあるお点前
古帛紗の上に仕覆を着せた献残中次を載せ
人数分の濃茶を入れ水指正面に荘る
仕覆は和巾をもって作ったものでもよいが
別のものでもよいということです
このお点前は古帛紗に載せた献残中次の扱いが
なかなか綺麗にできなく、和物なので肩衝茶入れと
同じように清めるのですが回し拭きがやりにくい
九月後半の主菓子、定番となります
「月見上用」 餡の中に栗を
 月見上用
月見上用「栗金団」 栗餡に白餡を同量混ぜた金団
 栗金団
栗金団お彼岸に「お萩」も作りましたが
写真を撮るのを忘れました
皆様に見ていただけないのが残念です
お花は相変わらずの「木槿」
「撫子」{秋海棠」「風船蔓」
花入れは末廣籠

社中でも大円の草のお稽古ができるようになり
四ヶ伝のお稽古も誰もができるようになってきた事
大変嬉しく思ってます
私も修練あるのみです














 大風
大風 撫子の錦玉
撫子の錦玉 秋空金団
秋空金団 こぼれ萩
こぼれ萩 着せ綿
着せ綿

