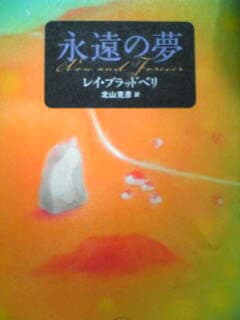
大げさにいえば、ブラッドベリ体験があるかないかで、その人の小説観はかなり違ったものになってしまうのかもしれない。もう少し、大げさにいってしまえば、現実感も変わってしまうのかも。
と、いいながらボクはそんな体験をしていないのだが、そんなことをいいたくなるくらいに、オリジナリティの強さがある作家なのだ。しかも、その強さは押しつけがましさやこれみよがしなところがなく、すいと小説の愉悦のようなものを感じさせてくれるのだ。
『バビロン行きの夜行列車』の短編たちには、うなった。そして、この『永遠の夢』。二つの中編が収められている。2007年刊行と書かれているから、作者87歳かな。それも驚き。で、この二編、訳者あとがきによれば、「ひとつはファンタジー、ひとつはSF」となる。
ストーリーをどこまで語るか。ここはブックカバー裏の紹介文による。
まず、「どこかで楽隊が奏でている」は、
「夢と詩にみちびかれ、記者カーディフは、アリゾナ州の小さな隠れ里サマートンに降りたった。不思議なことにそこでは子どもが遊ばず、住民のだれも年をとらない……。魔法に魅せられながら、やがて崩壊する町の謎をさぐる中編」。
萩尾望都の傑作に『ボーの一族』というのがあったが、それを思い出した。ただ、アリゾナの平原の先が、ちょっと渇いたイメージを運んでくれて、テイストはかなり違う。「永遠の時間」とは、人にとって何なのかをさらりと、しかし切なく語ってくれる。ああ、もしかしたら作家と作品の関係も、作家という有限の生身の人間と、その作品や読者との関係も情感含めて語れば、こうなるのかなとも思えた。アレクサンドリアの図書館の挿話がよかった。
「わたしたちは時間の旅人ですから、永遠への旅路の途中で救えるものは救って、なおざりにされれば失われるものは保存して、遠く旅するわたしたちの長い人生のなにがしかをささやかながらつけ加える、それを当然のことと考えたのです。」
「夏はいつも角をまがったすぐ先にあって、秋は道のどこか遠くにあるもの、その噂さえなかったのだわ。」
詩と思索がありなす抒情に酔うことができる小説だった。
もう一編、「2099年の巨鯨」。
「メルヴィルの「白鯨」における帆船を宇宙船に、白鯨を白い彗星におきかえて描かれた」、「乗組員たちが、深宇宙へ飛びたち、運命、永遠、そして神そのものに接触する」。
主人公イシュメイル、心に語りかけるクモのような異星人クエル、船長エイハブなど人物が魅力的で深い。そして、時間との闘いと共生を語るような哲学的な内容の難解さがなぜか心地いい小説である。
どっちの小説が好きかな。今は、「どこかで楽隊が奏でている」の方かな。小説として、よくできていたし。
で、挿入詩の一節。
どこかで楽隊が奏でている
そこでは月は空にけっして沈むことなく
そしてだれも夏に眠ることなく
そしてだれも死に落ちこむこともない
そこで〈時〉はまさに永久に進みつづけ
そこで心臓は鼓動をつづける
古い月の太鼓の打ち鳴らす音と
〈永遠〉の足のすべるような歩みに合わせて
と、いいながらボクはそんな体験をしていないのだが、そんなことをいいたくなるくらいに、オリジナリティの強さがある作家なのだ。しかも、その強さは押しつけがましさやこれみよがしなところがなく、すいと小説の愉悦のようなものを感じさせてくれるのだ。
『バビロン行きの夜行列車』の短編たちには、うなった。そして、この『永遠の夢』。二つの中編が収められている。2007年刊行と書かれているから、作者87歳かな。それも驚き。で、この二編、訳者あとがきによれば、「ひとつはファンタジー、ひとつはSF」となる。
ストーリーをどこまで語るか。ここはブックカバー裏の紹介文による。
まず、「どこかで楽隊が奏でている」は、
「夢と詩にみちびかれ、記者カーディフは、アリゾナ州の小さな隠れ里サマートンに降りたった。不思議なことにそこでは子どもが遊ばず、住民のだれも年をとらない……。魔法に魅せられながら、やがて崩壊する町の謎をさぐる中編」。
萩尾望都の傑作に『ボーの一族』というのがあったが、それを思い出した。ただ、アリゾナの平原の先が、ちょっと渇いたイメージを運んでくれて、テイストはかなり違う。「永遠の時間」とは、人にとって何なのかをさらりと、しかし切なく語ってくれる。ああ、もしかしたら作家と作品の関係も、作家という有限の生身の人間と、その作品や読者との関係も情感含めて語れば、こうなるのかなとも思えた。アレクサンドリアの図書館の挿話がよかった。
「わたしたちは時間の旅人ですから、永遠への旅路の途中で救えるものは救って、なおざりにされれば失われるものは保存して、遠く旅するわたしたちの長い人生のなにがしかをささやかながらつけ加える、それを当然のことと考えたのです。」
「夏はいつも角をまがったすぐ先にあって、秋は道のどこか遠くにあるもの、その噂さえなかったのだわ。」
詩と思索がありなす抒情に酔うことができる小説だった。
もう一編、「2099年の巨鯨」。
「メルヴィルの「白鯨」における帆船を宇宙船に、白鯨を白い彗星におきかえて描かれた」、「乗組員たちが、深宇宙へ飛びたち、運命、永遠、そして神そのものに接触する」。
主人公イシュメイル、心に語りかけるクモのような異星人クエル、船長エイハブなど人物が魅力的で深い。そして、時間との闘いと共生を語るような哲学的な内容の難解さがなぜか心地いい小説である。
どっちの小説が好きかな。今は、「どこかで楽隊が奏でている」の方かな。小説として、よくできていたし。
で、挿入詩の一節。
どこかで楽隊が奏でている
そこでは月は空にけっして沈むことなく
そしてだれも夏に眠ることなく
そしてだれも死に落ちこむこともない
そこで〈時〉はまさに永久に進みつづけ
そこで心臓は鼓動をつづける
古い月の太鼓の打ち鳴らす音と
〈永遠〉の足のすべるような歩みに合わせて










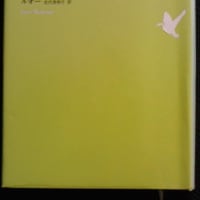
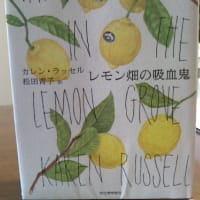
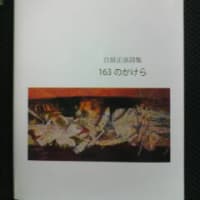
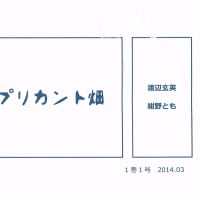
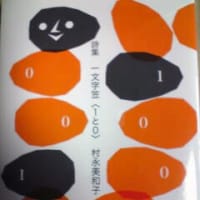
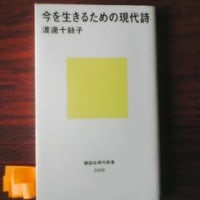




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます