
丘の上には月。そして、かがり火。かがり火が燃やすもの。かがり火が明るみに出すもの。「わたし」の追憶は月の光に映しだされる。追憶は映しだされては、燃やされていく。過ぎていった時間。それを包み込む季節の移り変わりの不変さ。情感は、叙事的記述の背後に抑え込まれる。故郷を離れた「わたし」は、「わたし」の共有した時間の追憶に自らのなくしてしまった時間を見いだす。取り戻せない時の弔いだろうか。そして、自らが不在だった時も過ぎていった丘の時間が、故郷に残ったものから告げられるとき、「わたし」は喪失した故郷の前で、自らが抱える空白を寄る辺ないわたしの不在として感じるしかないのかもしれない。追憶だけが誠実に生きられる時間。しかし、それが作りだす場所は単に追憶だけの世界ではなく郷愁を伴った人が生きる場所として現れる。すでに、人は大戦の悲惨の中でお互いの無惨さと誠実さと、そして狂気と正気を裏返し反転させながら生きたのかもしれない。日々の暮らしの中で、あるいはファシズムとそれへの抵抗の中で、翻弄される生。生き抜くしたたかさと、脆弱な人間の運命。そこにある人が生きていることの証しが、静かに綴られていく。小説を貫く緊張感は、張りつめていながら、突きつけてくるようなものではない。その緊張感が読者を引っぱるのだ。問うことがただの問いにならない。むしろ作者の自らへの問いのようなものが、ボクらを引きつける引力になる。彷徨う心が行き着く場所は、どこなのだろう。ボクらがボクらの生活の場所の中でうずたかく積み上げていく時間の堆積。抗いながら、抗いがたく、ある故郷のイメージ。イメージとしての故郷は喪失されたのだろうか。故郷を離れたあとの「多くの土地を知っているということは、また、だれも知らないということだった。」という表現と、故郷に戻ってから、故郷を記述する「わたしはこの白い、乾いた土に見おぼえがあった。丘の小径の踏みしだかれた、滑りやすい草。日の光のもとではやくも収穫の香りがする丘やぶどう畠のあの酸いような匂い。空には風の吹き流す長い縞模様、うっすらと白い泡のような雲が浮いていた」という表現のどちらもが心に残る。そう、そして、故郷のこの表現の続きに、「子供のころ、雲や星の行く道を眺めていたときから、わたしはもう自分でも知らないうちに放浪の旅を始めていたのだと気がついた。」で、あっ、この「わたし」にとって故郷は離れるべき場所だったのだということを、それまでの動機付け以上に納得させられるのだ。その結果として抱えこむ痛さとともに。1949年にこの小説を脱稿し、翌年パヴェーゼは自殺している。彼はこの小説の先に何を見たのだろうか。そこにも、丘にあがるかがり火が見えるような気がするのだ。










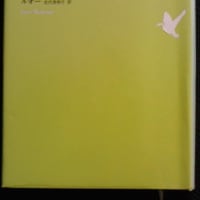
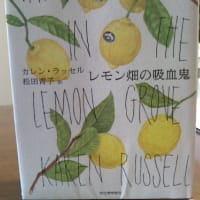
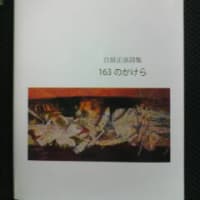
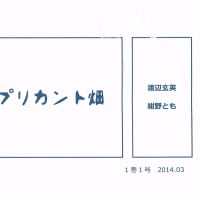
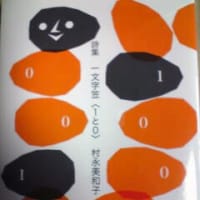
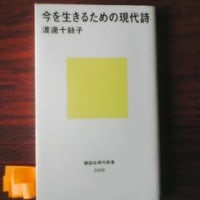




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます