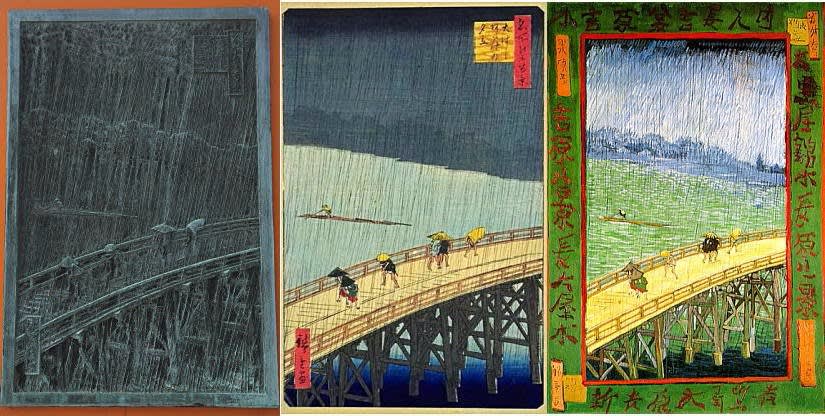芭蕉庵というのは文京区関口にもある、
芭蕉は若いころ神田上水工事の現場監督みたいな仕事をしていた。
その時の住まいが文京区の方でそのあと江東区のこの芭蕉庵で過ごした、
そしてこの地から奥の細道へと旅立って行ったのである。

新大橋を渡ったら信号を右折、万年橋通りへ、
ちょっと歩いて右に「江東区芭蕉記念館」。

この辺は下町中の下町、この光景は23区内とは思えない。
そして芭蕉の街、どこを見ても芭蕉が溢れている。

そのまま歩いてすぐ万年橋のたもとを右へ入ると「芭蕉稲荷」、
芭蕉庵があった所。
とにかくお江戸は稲荷が多い、どこにでもお稲荷さん
「伊勢屋、稲荷に犬のクソ」江戸に多いものを詠んだ戯れ句もある。
伊勢屋は伊勢から来た商人が多かったのね、今でも質屋さんは伊勢屋 !?。
万年橋もいいね、一日歩いて記事にしたい所だ。

足を踏み入れるのもはばかられるような小さな境内に「芭蕉庵跡」の碑。
カエルはいるけど飛びこむ池がない。

急な石段を上がると芭蕉の像、
どこを見ているのだろう、何を見ているのだろう。

上がった所はこんな感じ、いろいろな資料が展示されている。
芭蕉の背中は「万年橋」、小名木川はここで隅田川に注ぎこむ。
実は芭蕉は奥州へ旅立つ前に芭蕉庵を売り払いこの近くの仮屋から旅立った、
それなりの覚悟のもとに旅立ったのだろうか。

芭蕉の場所からは見えないがちょっと移動すると新大橋が見える、
芭蕉は毎日橋の進行状態を見ていたのかな。

逆光気味なので表情はイマイチだけど柔和な顔みたい。

清洲橋をバックに何思う、
芭蕉はこの清洲橋の袂あたりから旅立ったと言われている。
「奥の細道」紀行文によれば、元禄2年(1689年)3月に船で隅田川を北上し千住の地に上陸、
千住より奥州へと旅立った。矢立初めの句“行く春や 鳥啼き 魚の目は泪”を詠む。芭蕉 46歳だった。
旅の支度は防寒用の紙子(衣服)、ゆかた、雨具、筆墨 剃りあげた坊主頭に
墨染めの僧衣姿といういでたちだったという。
このあと素盞雄(すさのお)神社へ行く予定があるので
もしかしたらそこから続編を、、、ということになるかも。
2月22日 芭蕉庵を訪ねて

芭蕉は若いころ神田上水工事の現場監督みたいな仕事をしていた。
その時の住まいが文京区の方でそのあと江東区のこの芭蕉庵で過ごした、
そしてこの地から奥の細道へと旅立って行ったのである。

新大橋を渡ったら信号を右折、万年橋通りへ、
ちょっと歩いて右に「江東区芭蕉記念館」。

この辺は下町中の下町、この光景は23区内とは思えない。
そして芭蕉の街、どこを見ても芭蕉が溢れている。

そのまま歩いてすぐ万年橋のたもとを右へ入ると「芭蕉稲荷」、
芭蕉庵があった所。
とにかくお江戸は稲荷が多い、どこにでもお稲荷さん
「伊勢屋、稲荷に犬のクソ」江戸に多いものを詠んだ戯れ句もある。
伊勢屋は伊勢から来た商人が多かったのね、今でも質屋さんは伊勢屋 !?。
万年橋もいいね、一日歩いて記事にしたい所だ。

足を踏み入れるのもはばかられるような小さな境内に「芭蕉庵跡」の碑。
カエルはいるけど飛びこむ池がない。

急な石段を上がると芭蕉の像、
どこを見ているのだろう、何を見ているのだろう。

上がった所はこんな感じ、いろいろな資料が展示されている。
芭蕉の背中は「万年橋」、小名木川はここで隅田川に注ぎこむ。
実は芭蕉は奥州へ旅立つ前に芭蕉庵を売り払いこの近くの仮屋から旅立った、
それなりの覚悟のもとに旅立ったのだろうか。

芭蕉の場所からは見えないがちょっと移動すると新大橋が見える、
芭蕉は毎日橋の進行状態を見ていたのかな。

逆光気味なので表情はイマイチだけど柔和な顔みたい。

清洲橋をバックに何思う、
芭蕉はこの清洲橋の袂あたりから旅立ったと言われている。
「奥の細道」紀行文によれば、元禄2年(1689年)3月に船で隅田川を北上し千住の地に上陸、
千住より奥州へと旅立った。矢立初めの句“行く春や 鳥啼き 魚の目は泪”を詠む。芭蕉 46歳だった。
旅の支度は防寒用の紙子(衣服)、ゆかた、雨具、筆墨 剃りあげた坊主頭に
墨染めの僧衣姿といういでたちだったという。
このあと素盞雄(すさのお)神社へ行く予定があるので
もしかしたらそこから続編を、、、ということになるかも。
2月22日 芭蕉庵を訪ねて