毎日いろんなことで頭を悩ましながらも、明日のために頑張ろうと自分を励ましています。
疲れるけど、頑張ろう!
「マンダラ塗り絵」
家に「マンダラ塗り絵」(春秋社)という本がある。マンダラ(曼荼羅)というのは、「密教の複雑な教義を図式化したもので、密教界における全ての仏様の地位を整然と図形に表したもの。その他、仏画や物語を図式化したものなどを総称して<曼荼羅>と呼んだりもしている」と説明されているが、この本はそれを塗り絵としたものである。『大切なのは気楽に楽しく塗ることです』と背表紙にあったので試しにやってみた。使い方の説明があったので、それに従ってみた。
①パラパラめくって、気に入ったマンダラ画を見つけましょう。
②カラーペン、色鉛筆、絵の具など、色を塗る画材を用意しましょう。
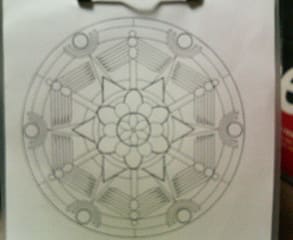
上のマンダラ画を選び、画材は「サクラ・クーピーペンシル」を使用することにした。選んだマンダラ画をコピーして塗っていくことにする。
③画材が決まったら、あまり考え込まず、感じるままに自由に塗っていきましょう。


中央から塗っていくことにする。色合いに拘らないが、心を落ち着け、整然と塗っていこうと思った。
④塗っているうちにだんだん楽しくなってきます。できれば1枚の絵は一度に仕上げてしまいましょう。(もちろん、疲れたらやめてけっこうです)

確かに、どんな色を選ぼうかとか、色がはみ出さないようにしようとか、塗っているうちに集中してくる。色の選択次第によって、同じ下絵でも様々に違った印象を抱かせるだろうなと思う。今の私の気持ちなら、この色だが明日だったら違う色を選ぶだろうなと思うと、自分の心のありようが映し出されてくるようで興味深い。
⑤完成したら、マンダラ画をすこし離れた所から眺めてみましょう。塗っていたときとはいくぶん違った雰囲気の絵が浮かび上がってくるはずです。
⑥達成感や解放感がえられ、もう1枚塗りたくなるかもしれません。

1時間ほどで完成した。思ったほど時間はかからない。今回は12色で塗ったのだが、何も塗らないままにしておくことができず、白い部分を残すことができなかった。
余り気持ちが晴れないときに塗ったものだから、何だか弱い色調になってしまったが、次にはマジックを使用してもっとはっきりしたマンダラ画を完成したいと思う。
くせになりそうな気がする塗り絵だ。
①パラパラめくって、気に入ったマンダラ画を見つけましょう。
②カラーペン、色鉛筆、絵の具など、色を塗る画材を用意しましょう。
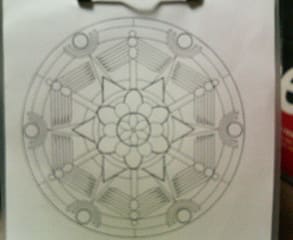
上のマンダラ画を選び、画材は「サクラ・クーピーペンシル」を使用することにした。選んだマンダラ画をコピーして塗っていくことにする。
③画材が決まったら、あまり考え込まず、感じるままに自由に塗っていきましょう。


中央から塗っていくことにする。色合いに拘らないが、心を落ち着け、整然と塗っていこうと思った。
④塗っているうちにだんだん楽しくなってきます。できれば1枚の絵は一度に仕上げてしまいましょう。(もちろん、疲れたらやめてけっこうです)

確かに、どんな色を選ぼうかとか、色がはみ出さないようにしようとか、塗っているうちに集中してくる。色の選択次第によって、同じ下絵でも様々に違った印象を抱かせるだろうなと思う。今の私の気持ちなら、この色だが明日だったら違う色を選ぶだろうなと思うと、自分の心のありようが映し出されてくるようで興味深い。
⑤完成したら、マンダラ画をすこし離れた所から眺めてみましょう。塗っていたときとはいくぶん違った雰囲気の絵が浮かび上がってくるはずです。
⑥達成感や解放感がえられ、もう1枚塗りたくなるかもしれません。

1時間ほどで完成した。思ったほど時間はかからない。今回は12色で塗ったのだが、何も塗らないままにしておくことができず、白い部分を残すことができなかった。
余り気持ちが晴れないときに塗ったものだから、何だか弱い色調になってしまったが、次にはマジックを使用してもっとはっきりしたマンダラ画を完成したいと思う。
くせになりそうな気がする塗り絵だ。
コメント ( 14 ) | Trackback ( 0 )
とら (2)
 とらが死んだ。
とらが死んだ。 2月22日にとらが猫エイズを発症したことを書いたが、それから3週間、私たちは一生懸命看病し、とらも本当によく頑張ったが、とうとう力尽きてしまった。
診断後、4、5日入院して処置をしてもらって帰って来たとらは、2週間ほど小康状態を保っていた。散歩にも出かけ、庭で日向ぼっこをしている姿もよく見かけた。このままうまくエイズと付き合ってくれればいいなと家族で話し合っていたが、3月2日に急に元気がなくなり、獣医につれていったところ、もう危ないかもしれないと言われ、家で最期を看取るために連れて帰って来た。全く動かず、弱く息をしているだけの状態だったので、本当にだめなものと覚悟を決めていた。帰省中の娘と学年末試験中の息子が、夜通しとらに付き添っていた。その甲斐あってか持ち直し、私たちはとらの生命力の強さに感嘆した。2日経つと、ヨタヨタとではあるが散歩に出かけられるまでに回復し、娘も安堵して、今週の月曜日に京都に戻って行った。しかし、ずっととらのことが気にかかるようで、毎日欠かさず電話をしてきて容態を聞いていた。「私は帰るけど、頑張るんだよ」と出掛けに、とらに話しかけていた姿が忘れられない。
ところが、4日前、私たちが買い物から帰って来ると、全身ずぶ濡れになったとらが座っていた。びっくりして体を拭いたり、ドライヤーで乾かしたりしたが、どうも外へ出ようとして、開いていた風呂場の窓に跳びかかったところ、失敗して湯船に落ちたようだ。そのまま溺死しなくてよかったと胸をなでおろしたが、そんな元気があるのかと感心もした。だが、それが影響したのか、その日の夜からまた元気がなくなってしまった。余り身動きしなくなりじっと寝ていることが多くなった。獣医と緊密に連絡を取っていた妻は、様子を報告したところ、インターフェロンも投与してできる限りの処置はしてあるから、あとはとらの最期をどうやって迎えてやりたいと私たちが思っているかだとアドバイスされた。妻が、自宅で最期を看取ってやりたいと答えると、獣医も賛成してくれた。
8日から息子が修学旅行に出発した。息子は旅行中にとらが死んでも連絡をくれるなと言い残していったが、あれだけ可愛がっていたとらを残して旅行に行くのはさぞや辛かっただろう。家を出るときには最後のつもりでとらに話しかけて言っただろうが、帰宅したらどんなにか悲しむことだろう。その夜遅く、塾を終えて帰宅した私に妻は、「とらが口から血を流すようになった」と告げた。腎不全の末期症状として、粘膜から血が滲み出て来ているようだ。部屋一面にペット用のシートを敷き詰めてあるが、ところどころに血のしみがついている。とらを見ると前足に血がこびりついている。妻は無言で自室に上げって行ったが、その様子でとらの命が長くないのを悟った私は、寝る前に、「息子が帰ってくるまでは何とか頑張れよ」、と声をかけたが、とらは何の反応も示さなかった。
朝目覚めて階下へ行くと、シーツが全て片付けられていた。うっと息が詰まったが、妻の泣き腫らした目を見ればとらが死んだのは明らかだった。妻が、「朝早くに死んだ」とだけ言ってあとは声を上げて泣いた。とらは陽の当たるベランダに寝かせてあると聞いて、見に行くと安らかに横になっていた。タオルでくるまれ、気持ちよさそうに日向ぼっこをしているようだった。死に顔は立派だった。よく頑張った。うめき声をもらすこともなく、苦しげな様子も見せなかった。本当に偉い猫だ!
とらの亡骸は、火葬にはせず、家の敷地内に埋めようということになった。できるだけ華やかに送ってやろうと、花屋でチューリップやカーネーションなどをたくさん買ってきた。ダンボール箱に納めたとらを花で一杯に飾ってやった。大好きだったイカや魚も入れてやった。ショートケーキも入れた。娘も息子もいない私と妻だけの弔いだったから、とらも寂しかったかもしれない。でも、妻が写真を何枚も撮って後から子供たちに見せるから、きっととらも許してくれるだろう。とてもきれいだった。
車庫の裏の桜の木の下に埋めようと、父が穴を掘ってくれた。そこにとらを置いて土をかぶせた上にろうそくを立て、皆でとらの成仏を祈った。「これからはとらが桜の花をきれいに咲かせてくれるようになるんだな」と、妻が呟いた。悲しいけど、とてもいい言葉だと思った。
さようなら、とら。
コメント ( 23 ) | Trackback ( 0 )
公立高校入試
2006年03月09日 / 塾
 今日から愛知県の公立高校入試が始まった。愛知県の公立高校入試は、「複合選抜」と呼ばれる方式をとっており、少々ややこしい。かいつまんで説明すると、愛知県を尾張地域と三河地域に大別する。私の市は尾張部に属するので、尾張地域の学校しか受験することはできない。尾張地域は全部で、76校あるが、それを1群、2群と分ける。さらに、各群をAグループ、Bグループに分ける。従って、どの高校も○群の□グループという仕分けがされることになる。受験生は、受験校を決めるのにまず群を選ばなければならない。例えば1群を選んだとすると、その中のAグループから1校、Bグループから1校の各2校を受験することが可能となる。そして、どちらかを第一志望校、もう一方を第二志望校と決める。(勿論、Aグループの高校しか受けないということは可能である)これは、普通科高校の区分けであって、これに専門科高校も、Aグループ・Bグループに分けられていて、普通科高校と組み合わせることはできる。(例えば、第一志望を普通科高校の1群のAグループの高校、第二志望を専門科高校のBグループの学校とすることは可能)
今日から愛知県の公立高校入試が始まった。愛知県の公立高校入試は、「複合選抜」と呼ばれる方式をとっており、少々ややこしい。かいつまんで説明すると、愛知県を尾張地域と三河地域に大別する。私の市は尾張部に属するので、尾張地域の学校しか受験することはできない。尾張地域は全部で、76校あるが、それを1群、2群と分ける。さらに、各群をAグループ、Bグループに分ける。従って、どの高校も○群の□グループという仕分けがされることになる。受験生は、受験校を決めるのにまず群を選ばなければならない。例えば1群を選んだとすると、その中のAグループから1校、Bグループから1校の各2校を受験することが可能となる。そして、どちらかを第一志望校、もう一方を第二志望校と決める。(勿論、Aグループの高校しか受けないということは可能である)これは、普通科高校の区分けであって、これに専門科高校も、Aグループ・Bグループに分けられていて、普通科高校と組み合わせることはできる。(例えば、第一志望を普通科高校の1群のAグループの高校、第二志望を専門科高校のBグループの学校とすることは可能) 要するに2校受験が可能となるわけだが、もう施行されて10年近くなると、志望校の選択パターンが定着して、2校受験というメリットはさほど感じられなくなってきた。それに、今年は9日がBグループの学力検査、10日が面接、13日がAグループの学力検査、14日が面接と結構長丁場の試験であり、発表がA、B同時に22日に行われるため、開始から合計2週間近くになり、生徒も父兄も、勿論学校・塾関係者もなかなか辛いものがある。まあ、私たちは毎年繰り返されることであるから、多少の慣れはあるが、生徒たちは針の筵にそれだけ長く座らされることになり、かなりのストレスを感じるようである。
こんな説明だけだと何だか難しそうに思えるが、要は入試で合格点を取ればいいだけの話だが、ここ数年の公立高校の入試では得点を取るのが年々難しくなっている。というのは、内申点が相対評価から絶対評価に変更されたために、内申点が全体的に高くなった。最難関校では、9教科の内申点がオール5の合計45という生徒がゴロゴロいて、内申点だけでは差がつかなくなってしまった。そこで試験当日の点数で合否を判定せざるを得なくなり、得点に差をつけるために入試問題が年々難しくなってきている。さらに、学校によって、内申点を重視、試験当日の得点を重視、対等に評価の3種類を選べるようになったため、難関校ほど当日点を重視するようになり、その結果ますます問題が難化してしまった。
国語は文が長くなり、数学はひねりが加えられ単純に答えが出なくなった。英語も単語数が増え、設問も複雑になった。理科・社会は記述問題が増え、記号問題でも4択ばかりだったのが、6択の問題も多くなり、生徒はかなり惑わされる。昨年はあまりに難化したものだから、地元の中堅校など100点満点中50点も取れば合格できた。(5年程前には65点は合格に必要だった)新指導要領になって、教科書が薄っぺらになり授業時間も減って、生徒の学力の低下が著しいのに、入試問題がやたら難しくなったのだから生徒たちができないのは当たり前だ。あまりにギャップがありすぎて、生徒たちはただただ戸惑うばかりである。
そればかりが原因ではないだろうが、私の塾の今年の中3生は今まで一緒に受験勉強を重ねてきたのだが、手ごたえがはっきりつかめない。やる気があるのかないのかはっきりしない生徒が多い。気持ちがないわけではないだろうが、私にはそれが感じられない。「笛吹けども踊らず」というか、生徒たちから感じる「やる気」というものが年々希薄になっているように思えて仕方がない。学校全体にそういうダラーッとした雰囲気が蔓延しているのだろうか、と心配になる。思い過ごしであればいいのだが・・・
なんだか不安で仕方ないが、ここまで来たら生徒一人一人が自分の持つ力を十二分に発揮してくれるのを祈るしかない。さすがに呑気者ばかりでも、やるときにはやるところを見せてくれるものと信じている。頑張れ!!
コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )
写真を何枚も貼ろう!
この goo ブログでは、写真は1枚しか掲載できないものだとずっと思ってきた。もう少し写真が載せられたら面白くなるのにな、と何度思ったかしれない。OCNのブログ人や、niftyのココログでは、ファイルを貼り付けることもできるし、写真だって何枚も載せられる。どうして goo にはそんなサービスがないのだろうとずっと不満に思っていた。
ところが、ボネさんのブログで知り合ったコメさんという方に、先日 goo のブログの記事にも写真を複数枚載せられないだろうか、とお尋ねしたら、いとも簡単にその方法を教えてくださった。PCの素人である私にはいささか難しかったが、何回か失敗するうちに何とかその技術を習得できた(と思う)ので、ここに私なりに理解した方法を説明させていただく。(こんな立派なことが言えるのもコメさんのお陰だ。コメさん感謝しています、本当にありがとう!)
①載せたい画像を「マイピクチャー」に取り込んでおく。
②記事を書き、画像を載せたい箇所になったら、一旦記事を下書きで投稿しておく。
③編集メニューから「画像フォルダ」を開く。
④画像ファイルの「参照」をクリックして、「マイピクチャー」から載せたい画像を選び、「開く」をクリック。
⑤「現在使用できる画像一覧」にその画像がアップされるので、その画像を左クリックする。拡大された画像のURLが示されるのでそれをコピーする。
⑥記事の編集画面に戻り、画像を載せたい箇所に次のように入力する。
全て半角で、<img src=”ここにコピペしたURLを貼り付ける”>
(ここでは、<>や=、””は全角にしてあるが、必ず半角にすること。ここでは半角にすると文字が消えて写真が載ってしまうのでわざと全角にしてある)
⑦⑥の<img src=”・・・・”>をコピーする。
⑧コピーしたものを記事の編集画面の「トラックバックURL」の所に貼り付け、下書きのまま「投稿」をクリックする。
⑨プレビューに写真が貼り付いたはずだ。Enter キーで写真は下げることができるし、写真の上下に文字も入れられる。
⑩これを繰り返せば、写真が何枚でも貼り付けられる。
⑪あとは、記事を完成で投稿すれば反映されるはず。
例えば、
デジカメ

お雛さん

DSライト

スノボー

ほら、できた! 素晴らしい!!!
ところが、ボネさんのブログで知り合ったコメさんという方に、先日 goo のブログの記事にも写真を複数枚載せられないだろうか、とお尋ねしたら、いとも簡単にその方法を教えてくださった。PCの素人である私にはいささか難しかったが、何回か失敗するうちに何とかその技術を習得できた(と思う)ので、ここに私なりに理解した方法を説明させていただく。(こんな立派なことが言えるのもコメさんのお陰だ。コメさん感謝しています、本当にありがとう!)
①載せたい画像を「マイピクチャー」に取り込んでおく。
②記事を書き、画像を載せたい箇所になったら、一旦記事を下書きで投稿しておく。
③編集メニューから「画像フォルダ」を開く。
④画像ファイルの「参照」をクリックして、「マイピクチャー」から載せたい画像を選び、「開く」をクリック。
⑤「現在使用できる画像一覧」にその画像がアップされるので、その画像を左クリックする。拡大された画像のURLが示されるのでそれをコピーする。
⑥記事の編集画面に戻り、画像を載せたい箇所に次のように入力する。
全て半角で、<img src=”ここにコピペしたURLを貼り付ける”>
(ここでは、<>や=、””は全角にしてあるが、必ず半角にすること。ここでは半角にすると文字が消えて写真が載ってしまうのでわざと全角にしてある)
⑦⑥の<img src=”・・・・”>をコピーする。
⑧コピーしたものを記事の編集画面の「トラックバックURL」の所に貼り付け、下書きのまま「投稿」をクリックする。
⑨プレビューに写真が貼り付いたはずだ。Enter キーで写真は下げることができるし、写真の上下に文字も入れられる。
⑩これを繰り返せば、写真が何枚でも貼り付けられる。
⑪あとは、記事を完成で投稿すれば反映されるはず。
例えば、
デジカメ

お雛さん

DSライト

スノボー

ほら、できた! 素晴らしい!!!
コメント ( 8 ) | Trackback ( 0 )
咳
 10日くらいずっと風邪が治らない。と言っても、熱があるわけでもないし、だるいわけでもない。ただ、咳がなかなか抜けない。毎日薬を飲んでいるのだが、治らない。朝起きるとしばらくは咳が止まらない。時間が経つにつれだんだんと治まり、塾の授業中はほとんど出ない。だから、調子に乗って夜更かししてしまうから、体調が完全に戻らず、また翌朝には咳で苦しめられる。悪循環を繰り返しているだけだ。日曜くらい早く寝ればいいのに、いつもと同じ時間まで起きているのだから、どうしようもない。「もっと早く寝て、早く治してよ」と妻には毎日怒鳴られているが、それも当然なことなので何にも言えない。
10日くらいずっと風邪が治らない。と言っても、熱があるわけでもないし、だるいわけでもない。ただ、咳がなかなか抜けない。毎日薬を飲んでいるのだが、治らない。朝起きるとしばらくは咳が止まらない。時間が経つにつれだんだんと治まり、塾の授業中はほとんど出ない。だから、調子に乗って夜更かししてしまうから、体調が完全に戻らず、また翌朝には咳で苦しめられる。悪循環を繰り返しているだけだ。日曜くらい早く寝ればいいのに、いつもと同じ時間まで起きているのだから、どうしようもない。「もっと早く寝て、早く治してよ」と妻には毎日怒鳴られているが、それも当然なことなので何にも言えない。 しかし、風邪の治りが年々悪くなっている。言い訳になってしまうだろうが、治そうと思ってもなかなか治ってくれない。擦り傷が簡単にふさがらなくなったのはずいぶん前から気付いていたが、風邪まで治りが悪くなってしまうと、正直イヤになる。いっそのこと、ガッーと高熱が出てしまった方が一気に治るだろうかなどとバカなことを考えてしまうが、ぐずぐず症状が続くのは自分のことながらイラ付いてくる。今年の冬は何とか風邪をひかずに乗り切れそうだなどと楽観したのがいけなかったのか、冬も終りかける今になって風邪にかかってしまうのは情けない。私立中学入試という山を越えた安心感からちょっと、心に油断が生じたのかもしれないが、まだ高校入試という最後の一山が残っているのだから、気を引き締め直さなければいけない。
もともと私は体が頑健ではない。中学・高校と腎臓病で長期入院していた。大学に入って、無茶苦茶な生活を繰り返すうちに体に適応力ができたのか、それ以来寝込むようなことは一度もなかった・・、いや、一度だけあった。それは今から13年ほど前のことだ。当時私の地元の中学校で風疹が流行り出し、塾生も一人、大きな体をした男の子が風疹にかかったと言って塾を休んだ。その時は、大して気にもしていなかったのだが、数日後私の体が突然だるくて仕方なくなった。熱を測ると38度を越えていた。そんな高熱など滅多に出たことがなかった私は、塾を終えるとすぐに寝た。しかし、翌朝目覚めてみると全身に赤い発疹が点々とできていた。「なんだこれは!」と叫びながら、妻に見せると、「風疹じゃないの」と言う。「えっ!うつったのか!」とびっくりして、慌てて医者に行ってみた。医者は一目見るなり、「風疹ですね。治るまで1週間は仕事に行っちゃいけませんよ、伝染病ですから」と診断した。
しかし、塾を休むわけには行かないので、手伝いをしてくれている大学生たちに電話をして、私がいない一週間、なんとか授業を続けていけるようにあれこれ指示を出した。とてもいつもどおりにないかなかっただろうが、生徒たちに事情を話しながら一週間乗り越えてくれた。今思えば、我が塾最大のピンチだったのかもしれないが、こうしたことはいつ何時起こるか分からないものであるから、危機管理を普段からしっかり準備しておかなければならない。と思いはするものの、なかなかそこまで手が回らないのは、我ながら情けない。泥縄式で、「何かあってから対処の仕方を考える」ようではいけないと、常に思っているのだが・・・
この時の私の風疹はすごかった。「大人がかかると症状が重いよ」と妻が言ったが、高熱がなかなかひかず、ずっとボーっとしていた。だが、それよりも最初は点々だった発疹が次第に数が多くなり、発疹自体も大きくなって、最後には私の全身が真っ赤になってしまったのには心底驚いた。海水浴に行って日焼けしたときよりも、もっともっと赤くてとても他人に顔合わせができるような状態ではなかった。私の記憶にある中では、一番の大病だった。記念に写真を撮っておけばよかったのにと今なら思えるが、その時はそんなことなど全く考えもせず、ただひたすら「早く治れ!」と願うばかりだった。
それを思えば、ちょっとくらい咳き込むぐらいどうってことないように思えるが、やっぱり早く治したいのは同じだ。健康で元気でいるのが全ての基本だなと身に沁みるこの頃である。
コメント ( 14 ) | Trackback ( 0 )
未来予測
 「10年後の日本」(「日本の論点」編集部編、文芸春秋社)という本を買った。
「10年後の日本」(「日本の論点」編集部編、文芸春秋社)という本を買った。「消費税二桁化、団塊世代の大量定年、学力衰退、500万人のフリーター、年金崩壊、熟年離婚ラッシュ。『日本の論点』編集部が豊富なデータを駆使し、47項目の社会問題を取り上げ、その未来を簡潔にやさしく解説」
と、カバーにまとめが書いてあるが、まだ読み終えていない。飛ばし読みしかしていないので偉そうなことを言う資格はないが、読んでいて10年後の自分(もし生きていられたら)の悲惨な姿が思い描かれ、なんとも気の重くなる内容だ。「衝撃の大予測。あなたは生き残れるか」などとセンセーショナルな言葉が帯に踊っているが、「私には無理でしょう」と答えたくなってくる。これから少しずつ気になる箇所を読み続けていくことになるだろうが、この予測がどれだけ当たるのか、興味のあるところだ。
しかし、未来予測という点で言うなら、小学6年生の教科書(東京書籍版)に「百年前の未来予測」(横田順彌著)と言う文の中で紹介されている「二十世紀の預言」の精度の方が驚きである。
これは、報知新聞1901年(明治34年)1月2・3日付けの紙面に発表されたものである。これからの100年間にどんなことが起こるか、どんなことができるようになるかを23項目にわたって予測したものである。書いた人は分からないが、これらの予測が驚くほどよく当たっている。実現したものとほぼ実現したものと言えるものを合わせると、18項目にもなる。以下に実現したと思われるものをいくつか挙げてみる。
「無線電信及電話」--- 国際電話が可能になると予測
「遠距離の写真」--- カラーテレビの登場を予測
「寒暑知らず」--- エアコンの登場を予測
「植物と電気」--- 植物の品種改良が進むこを予測
「人声十里に達す」--- テレビ電話の登場を予測
「買物便法」--- カタログ販売の普及を予測
「鉄道の速力」--- 時速240kmになり、東京・神戸間を2時間半で走れるようになると予測
「医術の進歩」--- レーザーメスの登場を予測
「自動車の世」--- 自動車の全盛時代の到来を予測
(自動車が初めて輸入されたのはこの記事のわずか3年前)
「電気の輸送」--- 国内隅々まで電気が行き渡ることを予測
100年前に、現代の生活様式をこれほど的確に予測できたことは驚嘆に値する。こうした予言を可能にした背景には、当時、電話も自動車もすでにアメリカやヨーロッパの国々で発明され、その科学技術が発展の途中にあったという事実があるようだ。しかし、当時の日本にはまだそうした科学の先端技術が広まっていたわけではないので、外国文明の発達ぶりを目の当たりにした人が、技術の進歩に期待を込めて予測したものではないかと、教科書には述べられている。「人と獣の会話自在」とか、「暴風を防ぐ」とかドラえもんの世界のようなことが予測されているのはご愛敬だとしても、この預言を書いた人が相当の慧眼の持ち主であることは確かなようだ。
100年前には、科学技術に全幅の信頼を寄せ、バラ色の未来社会の到来を思い描くこともできたであろう。しかし、100年たって21世紀となった今、その科学技術の進歩によってもたらされた、いわば負の遺産と言うべき多くのものによって、我々の生活は深甚なダメージを受けている。環境問題などを挙げるまでもないだろう。その結果、わずか10年後を予測するだけで暗い見通ししか立てられなくなってしまった。果たして「10年後の日本」からこうした真っ暗な近未来予測を押し付けられて、「いやそんなことはない、未来は我々自分たちの力で切り拓くものだ」と反発するだけの力が今の私たちにあるのだろうか。
何ともやりきれない気持ちになる。
コメント ( 10 ) | Trackback ( 0 )
デジカメ
 とうとうデジカメを手に入れた。ブログを始めてから、画像を貼り付けるのにどうしても欲しかった念願がやっと叶った。と言っても、新品をかったのではない。いや、買ったのだが、新品は娘のものになり、私は娘が使っていたものをもらったのである。いわば娘のお下がりを私が使えることになった。娘が持っていたデジカメは、Panasonic の LUMIX であるが、このデジカメには相当の思い入れが私にはある。
とうとうデジカメを手に入れた。ブログを始めてから、画像を貼り付けるのにどうしても欲しかった念願がやっと叶った。と言っても、新品をかったのではない。いや、買ったのだが、新品は娘のものになり、私は娘が使っていたものをもらったのである。いわば娘のお下がりを私が使えることになった。娘が持っていたデジカメは、Panasonic の LUMIX であるが、このデジカメには相当の思い入れが私にはある。 娘の大学受験の結果発表が2年前のちょうど今頃に行われた。張り出される結果発表を見るため、京都まで行くつもりで日程調整をしていた私に、「何でわざわざ京都まで行く必要があるの。レタックスが頼んであるから、それを待っていればいいよ」と禁足令が出てしまった。それを振り切ってまで行くほど結果に自信がなかった私は、娘の言葉に従うしかなかった。しかし、いつ届くか分からない郵便をイライラしながら待つのも我慢できそうもないから、郵便局に早く確実に受け取る方法はないものかと問い合わせてみた。すると、局留め扱いにすれば、午後1時発表の結果をほぼリアルタイムで受け取ることが出来るとの返事をもらった。ならば、そうしようと手続きを取って、当日1時過ぎに妻と娘の3人で、郵便局に着いた。駐車場に私たちを残して、窓口までレタックスを取りに行った娘が、満面の笑みを浮かべながら走ってきた姿を見たとき、私は頭の中が真っ白になった。「やった、やった!」と狂喜乱舞する娘の横で、私と妻は安堵の溜息をついた。妻の目からあふれ出す涙を見て、私の目頭もジーンと熱くなった。半ば放心状態で、「よし、合格祝いにデジカメを買いに行こう」と合格した折には、買ってやると約束してあったデジカメを買うために電機店に向かった。そのときに買った記念の品が、この LUMIX だ。
いわば、私たちの喜びを凝縮させたこのデジカメは、2年間娘と共にあったのだが、ここ最近充電機能が低下してきたと娘が不満を訴えた。「前だったら、1回充電すれば4,5日持ったのに、最近は1日くらいしか持たない」と言う。この言葉を聞いた私に妙案がひらめいた。「じゃあ、新しいのを買ってやるから、そのデジカメを俺にくれ」という私の提案に娘が飛びついた。「いいの?本当?それは嬉しいな」さらに、買うことが出来なかった任天堂DSライトの代わりの誕生日プレゼントだという名目まで付けて、私と娘の思惑がすべて丸く収まるような形をとることができた。私はいくつかの懸案事項を一挙に解決できる案を見つけた自分に満足して、「じゃあ、これで買って来い」とカードを渡した。
で、娘が買ってきた機種は FUJIFILM の 「Fine Pix Z2」 という物だった。私は Canon の IXY DIGITAL を勧めておいたのだが、娘いわく「IXY は店の人にも勧められたんだけど、皆が持ってるし、中田英寿のCMが頭に残っててどうしても買う気になれなかった」そうだ。さらに、「Panasonic の新しい機種にしようかなと思ったけどそれじゃあ芸がないかなと思ってやめた。SONY のCyber Shot は初めから買う気がなかった。そうすると、これぐらいかなと思って・・」と、何だか本当に気に入って買ったのかどうか分からない解説をしてくれた。私が見るに、小振りでシルバーの色合いがなかなか洒落ている。できれば私だってこちらの方がいいに決まっているが、たまには父親らしく鷹揚に構えなければいけない。「それじゃあ、Lumix はもらうよ」とかなり傷んだ、青色のデジカメを受け取った。
さあこれで、今までよりもきれいな写真をこのブログに貼り付けることができる。しかし、問題は果たして私がこのデジカメを使いこなすことができるかどうかだ。写真を撮ることくらいはさすがの私にもできる。だが、画像をPCの中に取り込むことができるだろうか。「USBを使うんだよ」とヒントはくれたが、娘はもうすぐ京都に戻ってしまう。
本当に大丈夫だろうか。「おい、ちゃんと使い方くらい教えてくれよ!」
コメント ( 15 ) | Trackback ( 0 )
「君といつまでも」
先週の土曜日、バスの運転をしながらラジオを聴いていたら、加山雄三の「君といつまでも」が流れてきた。岩谷時子作詞、弾厚作作曲のこの歌は、名曲だと思う。つい、一緒に口ずさんでしまった。
二人を夕闇が 包むこの窓辺に
明日も素晴らしい 幸せが来るだろう
君の瞳は星と輝き
恋するこの胸は 炎と燃えている
大空染めて行く 夕陽色あせても
二人の心は 変わらないいつまでも
いいよなあ、恋の絶頂期にある二人の心を歌った歌としては最高だ。二人の心がしっかりと通じ合っていると信じているからこそ歌える歌だ。
「幸せだな
僕は君といる時が
一番幸せなんだ
僕は死ぬまで
君を離さないぞ
いいだろう?」
「でもなあ、このセリフがあるんだよな、この歌には・・」私は思わず自分に突っ込みを入れてしまった。これが歌詞だったら、まだいいのかもしれない。しかし、セリフとなると聞いていて恥ずかしくて仕方がない。いくら加山雄三が指で鼻をこすりながら言っていても、聞いている方が恥ずかしくなってしまう。何も私が恥ずかしがる必要はないのだが、何故か恥ずかしいし、照れてしまう。どうしてなんだろう。
同じようなことが、私が高校生の頃「少年マガジン」に連載されていた、梶原一騎原作の「愛と誠」の中で、学校一秀才の岩清水弘がヒロイン早乙女愛に向かって叫ぶ有名なセリフ、
「早乙女愛よ、岩清水弘はきみのためなら死ねる!」
についても言える。この言葉自体は、岩清水クンの抑え切れない激情のほとばしりであると解釈すればいいのだろうが、何故か読むたび、聞くたびにこちらが恥ずかしくなってしまうセリフであった。いまの時代、こんなことを言おうもんなら、ストーカーと思われ、気持ち悪い男と罵られるのがオチである。
「羞恥心はどこへ消えた?」(菅原健介著、光文社新書)という本がある。人間がなぜ「恥らう」のか、羞恥心は何の役に立っているのかについて論証しているが、残念なことに、「君といつまでも」や、岩清水クンのセリフから私が感じるような恥ずかしさや照れについて説明してくれていない。仕方がないから、自分なりに菅原氏の考えをアレンジしてみた。
恋愛期間中に、心の中で「君を離さないぞ」とか「君のためなら死ねる」と思い込むことは程度の差こそあれ、誰にもあることではないだろうか。ただ、大多数はそんなことを口に出して言わないし、言わないからこそお互いの心を探りあい、恋愛の喜び・苦しみが味わえるのかもしれない。そうした秘めやかな心もようを、あまりにストレートに表現してしまう人がいると、私たちは「ちょっと待ってよ」と自己抑制をかけ、「あんなことはとても真似できない、恥ずかしい」と思うのではないだろうか。羞恥心が働き、恥をかかないよう、自己の行動を抑制するのである。
この考えがあながち間違っていないことを裏付けるような、加山雄三に関する1つの「事件」がある。2004年9月6日、対オリオールズ戦で、ヤンキースがサヨナラ勝ちを収め、グラウンドでチームメイトと喜び合った松井秀喜が一塁側ダッグアウトに下がろうとしたとき、すぐ上の席にいた加山雄三が松井を呼び止め、写真撮影をせがんだのだ。松井は断るわけにはいかずポーズをとっていたが、私はこの映像を一部始終見ていて、「加山雄三ってすごい人だな」と思った。さすが超有名人だけあって、試合終了直後の松井に平気で無理が言えるんだなと感心してしまった。「いいなあ」と思わず羨ましくなったが、同時に何だか恥ずかしい気分になったのも覚えている。自分だったら、そんな図々しいこと恥ずかしくてとてもできないと思ったのだが、それは「そんなことをしたら自分が恥をかくだけだよ、そんなことをしちゃいけないよ」、と羞恥心が自己抑制をかけたのかもしれない。
でもなあ、世間になんと思われようと、そんな松井とのツーショットの写真があったら自慢できるよな。いいなあ、加山雄三は・・
二人を夕闇が 包むこの窓辺に
明日も素晴らしい 幸せが来るだろう
君の瞳は星と輝き
恋するこの胸は 炎と燃えている
大空染めて行く 夕陽色あせても
二人の心は 変わらないいつまでも
いいよなあ、恋の絶頂期にある二人の心を歌った歌としては最高だ。二人の心がしっかりと通じ合っていると信じているからこそ歌える歌だ。
「幸せだな
僕は君といる時が
一番幸せなんだ
僕は死ぬまで
君を離さないぞ
いいだろう?」
「でもなあ、このセリフがあるんだよな、この歌には・・」私は思わず自分に突っ込みを入れてしまった。これが歌詞だったら、まだいいのかもしれない。しかし、セリフとなると聞いていて恥ずかしくて仕方がない。いくら加山雄三が指で鼻をこすりながら言っていても、聞いている方が恥ずかしくなってしまう。何も私が恥ずかしがる必要はないのだが、何故か恥ずかしいし、照れてしまう。どうしてなんだろう。
同じようなことが、私が高校生の頃「少年マガジン」に連載されていた、梶原一騎原作の「愛と誠」の中で、学校一秀才の岩清水弘がヒロイン早乙女愛に向かって叫ぶ有名なセリフ、
「早乙女愛よ、岩清水弘はきみのためなら死ねる!」
についても言える。この言葉自体は、岩清水クンの抑え切れない激情のほとばしりであると解釈すればいいのだろうが、何故か読むたび、聞くたびにこちらが恥ずかしくなってしまうセリフであった。いまの時代、こんなことを言おうもんなら、ストーカーと思われ、気持ち悪い男と罵られるのがオチである。
「羞恥心はどこへ消えた?」(菅原健介著、光文社新書)という本がある。人間がなぜ「恥らう」のか、羞恥心は何の役に立っているのかについて論証しているが、残念なことに、「君といつまでも」や、岩清水クンのセリフから私が感じるような恥ずかしさや照れについて説明してくれていない。仕方がないから、自分なりに菅原氏の考えをアレンジしてみた。
恋愛期間中に、心の中で「君を離さないぞ」とか「君のためなら死ねる」と思い込むことは程度の差こそあれ、誰にもあることではないだろうか。ただ、大多数はそんなことを口に出して言わないし、言わないからこそお互いの心を探りあい、恋愛の喜び・苦しみが味わえるのかもしれない。そうした秘めやかな心もようを、あまりにストレートに表現してしまう人がいると、私たちは「ちょっと待ってよ」と自己抑制をかけ、「あんなことはとても真似できない、恥ずかしい」と思うのではないだろうか。羞恥心が働き、恥をかかないよう、自己の行動を抑制するのである。
この考えがあながち間違っていないことを裏付けるような、加山雄三に関する1つの「事件」がある。2004年9月6日、対オリオールズ戦で、ヤンキースがサヨナラ勝ちを収め、グラウンドでチームメイトと喜び合った松井秀喜が一塁側ダッグアウトに下がろうとしたとき、すぐ上の席にいた加山雄三が松井を呼び止め、写真撮影をせがんだのだ。松井は断るわけにはいかずポーズをとっていたが、私はこの映像を一部始終見ていて、「加山雄三ってすごい人だな」と思った。さすが超有名人だけあって、試合終了直後の松井に平気で無理が言えるんだなと感心してしまった。「いいなあ」と思わず羨ましくなったが、同時に何だか恥ずかしい気分になったのも覚えている。自分だったら、そんな図々しいこと恥ずかしくてとてもできないと思ったのだが、それは「そんなことをしたら自分が恥をかくだけだよ、そんなことをしちゃいけないよ」、と羞恥心が自己抑制をかけたのかもしれない。
でもなあ、世間になんと思われようと、そんな松井とのツーショットの写真があったら自慢できるよな。いいなあ、加山雄三は・・
コメント ( 12 ) | Trackback ( 0 )
おこしもん
今日は桃の節句、おひな祭りの日だ。我が家にも雛人形が飾られた。
当地では、雛人形のお供えとして、菱餅・雛あられなどの他に、「おこしもん」と呼ばれる餅を各家庭で作ってお供えする風習がある。今は店で買ってきて代用する家庭が多いようだが、我が家では3、4年前まで妻が子供たちとずっと作ってきた。子供たちが大きくなったここ数年は作っていなかったが、今年は私が作ってみようと思い立った。先日のケーキ作りが幻に終った雪辱もかねて試してみようと妻に打診したら、「これならやってもいいよ」と意外と簡単に承諾してくれた。ただし、「自分ひとりで作ってね。後片付けまできちんとしてよ」という条件つきだけれど。
【材料】
米の粉(上新粉)1kg
熱湯(量は少なめの方がよい)
砂糖(今回はサトウキビからとったものを使用。スプーン5杯くらい)
木型(板をくりぬいて、型にしたもの。我が家には、鯛・筍・梅・桃・海老・キティーちゃんを型どった6種類ある)
【作り方】
①米の粉(打ち粉用にひとつかみ程度別に取っておく)を乳鉢にいれ、砂糖を混ぜる。よく混ざったら、湯を入れる。


②熱いので最初は割り箸で混ぜ、粉が馴染んだら手でこねる。(湯は粉の半分ほどが丸まった状態でやめておく。なるべく少なめに)


③良くこねると出来上がりの歯ごたえが良くなるので、30分以上はただひたすらこねる。途中から、粘り気が強くなってきて結構大変だが、文句を言わずにこねる。


④木型の上に必ず粉をまぶしてから、一掴みちぎって平らになるように木型に詰めていく。今回は少し水分が多かったようで、詰め込んだものを取り出すのが大変だったが、何とか形を崩さずに取り出す。(もう少し水分が少ないと、木型をトントン叩くと取れてくる)
 熱中してしまって、ここの写真を撮るのを忘れた、残念・・。
熱中してしまって、ここの写真を撮るのを忘れた、残念・・。
⑤型から出した「おこしもん」に色を付ける。色粉(食用色素)を少量水に溶かしたものを割り箸につけて、思い思いの色を付ける。

⑥蒸し器に熱湯を沸かし、沸騰したら布を敷いた上に「おこしもん」を乗せる。(生まれて初めて蒸し器を使った私は勝手が分からず、少々手間取る)
⑦蒸し器で20分ほど蒸したあとで、ザルにあげて一応出来上がり!!我ながら、まあまあ上出来!

【食べ方】
あたたかいうちにしょう油、砂糖しょう油をつけて食べると美味しい。
冷めたら焼いてお焦げが出来てまた美味しい。しょう油をつけて食べるのがやはりいい。
http://hipee.moe.hm/uplon/196.jpg
ラップでぴったり包んで冷凍保存も出来る。
あ~あ、疲れた。30分以上わき目も振らずに米の粉をこねるのはさすがに疲れた。妻は横から手順のアドバイスはしてくれたものの、全く手は出さなかった。型に入れるのは娘が面白がって一緒にやったが、さすがに年季が違う、きれいな形に仕上げる。私は「へたくそ」と馬鹿にされながらも頑張ってみた。
これで、ケーキの雪辱が果たせたかは微妙なところだが、ただ1つ分かったことがある。準備から後片付けまで自分ひとりでこなすのはとても大変だ。やっぱり私には台所仕事は向いていない、と今さらながらの結論に達した。
当地では、雛人形のお供えとして、菱餅・雛あられなどの他に、「おこしもん」と呼ばれる餅を各家庭で作ってお供えする風習がある。今は店で買ってきて代用する家庭が多いようだが、我が家では3、4年前まで妻が子供たちとずっと作ってきた。子供たちが大きくなったここ数年は作っていなかったが、今年は私が作ってみようと思い立った。先日のケーキ作りが幻に終った雪辱もかねて試してみようと妻に打診したら、「これならやってもいいよ」と意外と簡単に承諾してくれた。ただし、「自分ひとりで作ってね。後片付けまできちんとしてよ」という条件つきだけれど。
【材料】
米の粉(上新粉)1kg
熱湯(量は少なめの方がよい)
砂糖(今回はサトウキビからとったものを使用。スプーン5杯くらい)
木型(板をくりぬいて、型にしたもの。我が家には、鯛・筍・梅・桃・海老・キティーちゃんを型どった6種類ある)
【作り方】
①米の粉(打ち粉用にひとつかみ程度別に取っておく)を乳鉢にいれ、砂糖を混ぜる。よく混ざったら、湯を入れる。


②熱いので最初は割り箸で混ぜ、粉が馴染んだら手でこねる。(湯は粉の半分ほどが丸まった状態でやめておく。なるべく少なめに)


③良くこねると出来上がりの歯ごたえが良くなるので、30分以上はただひたすらこねる。途中から、粘り気が強くなってきて結構大変だが、文句を言わずにこねる。


④木型の上に必ず粉をまぶしてから、一掴みちぎって平らになるように木型に詰めていく。今回は少し水分が多かったようで、詰め込んだものを取り出すのが大変だったが、何とか形を崩さずに取り出す。(もう少し水分が少ないと、木型をトントン叩くと取れてくる)
 熱中してしまって、ここの写真を撮るのを忘れた、残念・・。
熱中してしまって、ここの写真を撮るのを忘れた、残念・・。⑤型から出した「おこしもん」に色を付ける。色粉(食用色素)を少量水に溶かしたものを割り箸につけて、思い思いの色を付ける。

⑥蒸し器に熱湯を沸かし、沸騰したら布を敷いた上に「おこしもん」を乗せる。(生まれて初めて蒸し器を使った私は勝手が分からず、少々手間取る)
⑦蒸し器で20分ほど蒸したあとで、ザルにあげて一応出来上がり!!我ながら、まあまあ上出来!

【食べ方】
あたたかいうちにしょう油、砂糖しょう油をつけて食べると美味しい。
冷めたら焼いてお焦げが出来てまた美味しい。しょう油をつけて食べるのがやはりいい。
http://hipee.moe.hm/uplon/196.jpg
ラップでぴったり包んで冷凍保存も出来る。
あ~あ、疲れた。30分以上わき目も振らずに米の粉をこねるのはさすがに疲れた。妻は横から手順のアドバイスはしてくれたものの、全く手は出さなかった。型に入れるのは娘が面白がって一緒にやったが、さすがに年季が違う、きれいな形に仕上げる。私は「へたくそ」と馬鹿にされながらも頑張ってみた。
これで、ケーキの雪辱が果たせたかは微妙なところだが、ただ1つ分かったことがある。準備から後片付けまで自分ひとりでこなすのはとても大変だ。やっぱり私には台所仕事は向いていない、と今さらながらの結論に達した。
コメント ( 11 ) | Trackback ( 0 )
トリノ五輪閉幕
 トリノオリンピックが終った。荒川静香選手だけが印象に残ったオリンピックだった。私が期待した安藤美姫選手は15位に終ってしまったが、4年後にもきっとチャンスは巡ってくる。それまで、心技体いずれも磨いて、ぜひ雪辱を果たしてもらいたい。他にも惜しい選手はいた。スピードスケートの加藤条治選手は、メダル間違いなしとの前評判だったが、オリンピックのプレッシャーに負けてしまったようだ。彼も21歳、たゆまぬ努力を続ければ栄冠を手にすることはできるだろう。
トリノオリンピックが終った。荒川静香選手だけが印象に残ったオリンピックだった。私が期待した安藤美姫選手は15位に終ってしまったが、4年後にもきっとチャンスは巡ってくる。それまで、心技体いずれも磨いて、ぜひ雪辱を果たしてもらいたい。他にも惜しい選手はいた。スピードスケートの加藤条治選手は、メダル間違いなしとの前評判だったが、オリンピックのプレッシャーに負けてしまったようだ。彼も21歳、たゆまぬ努力を続ければ栄冠を手にすることはできるだろう。 私が日本人選手のTV中継をまともに見たのは荒川選手の演技ぐらいであるから、選手個々のパフォーマンスの出来不出来について論評することはできない。しかし、閉会式での日本人選手の映像は見た。皆、楽しそうだった。驚いたのは人間が空中を飛んでいたことだ。ものすごい風圧を下からかけて空中にとどまらせていたのだが、回転したり、スノーボードをはいて真っ直ぐに立ったりと、素晴らしい妙技を見せてくれた。一緒に見ていた妻と娘が「いいなあ、やってみたいなあ」と騒いだのも頷けるほど、見ている者を爽快な気持ちにさせてくれた。それと、リッキーマーティンが歌い始めたら、場内がディスコ会場のようになったのにも驚いた。リッキーマーティンを見るのは久しぶりだったが、やっぱりかっこいい。
それにしても、金1個だけという結果は正直言って寂しい。いくらオリンピックは参加することに意義があると言っても、日頃の精進が納得いく結果で報われなかったのだから、選手諸君も悔しいことだろう。見通しが甘かったと反省の弁が連日報道されたが、昔の名前で出ていた選手が余りにも多かったので、この結果も致し方ないのかもしれない。競技者の新旧交代がうまく行っていなかった感は否めないだろう。
などと言いながら、国別のメダル獲得数を眺めていると結構面白い。全競技終了した結果、ドイツが金11銀12銅6の合計29個で最多。そのあと、アメリカ・アーストリア・ロシア・カナダと続いていく。韓国はショートトラックの8種目のうち6種目を制したため、金6銀3銅2の合計11個を獲得した。国と企業が一体化して強化を進めた成果だということだが、素晴らしいことだと思う。中国も北京五輪に向けての国と企業が連携した強化策が実り、金2銀4銅5の計11個と健闘した。面白いのは南半球の国であるオーストラリアが、男子モーグルで金1個、女子エアリアルで銅1個を獲得したことだ。北半球とは季節が逆だから調整するのは難しかっただろうから、この活躍は素晴らしい。
さらに見ていくと、エストニア・ベラルーシ・ウクライナ・ラトビアという旧ソ連に属する国々もメダルを獲得している。ロシアが金8個を含む22個を獲得したのはさすがだが、エストニアがスキーの距離競技で金を3個獲得した。旧ソ連が解体して15の国に分かれて今年で15年になる。バルト3国(エストニア・ラトビア・リトアニア)はEU入りを果たし、他の12カ国は独立国家共同体(CIS)を組織した。しかし、武力紛争や少数民族地域の分離という事態に直面している国もあり、発展度合いには濃淡があるようだ。その中でも最も豊かな国がエストニアと言われているが、そうした経済的な余裕がオリンピックでの成績に如実に現れているように思う。
しかし、オリンピックの閉会式はいつ見ても楽しい。戦い終えた選手たちが皆リラックスした表情で最後のイベントを楽しもうとしている姿がいい。あちこちで選手が手を取り合っている姿はまさしく平和の祭典だ。新聞には「面白くない五輪などない」という記者の言葉が載っていた。私がTVで見たのはほんのわずかな時間であったが、それでも選手の真剣な表情には思わず見入ってしまった。(ショートトラックの男子5000メートルリレーは息をもつかせぬ迫力で、思わず最後まで見てしまった)
今頃になって、もうちょっとしっかり見ておけばよかったと悔やんでいる。北京五輪が待ち遠しい。
コメント ( 18 ) | Trackback ( 0 )
| « 前ページ | 次ページ » |




