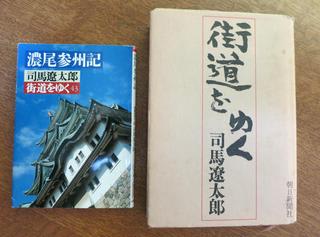秋を探しに東光院を訪れました。

東光院は大阪の豊中市にあります。阪急曽根駅から5分ほどのところです。

住宅地の中にあるお寺ですが、中に入ってしまえば街の中にあることを感じさせません。

ちょうど今日から「萩まつり道了祭」が開かれていました。

このお寺には正岡子規も訪れたことがあるようで、子規の句碑もありました。

「ほろほろと 石にこぼれぬ 萩の露」と詠んでいます。

そんな関係もあってか、今日は俳句の集いも行われていました。

私も一句ひねればよかったのですが、うかばないので、写真でご勘弁ください。

萩も見頃で、こぢんまりとした、いいお寺でした。

秋ですね。

東光院は大阪の豊中市にあります。阪急曽根駅から5分ほどのところです。

住宅地の中にあるお寺ですが、中に入ってしまえば街の中にあることを感じさせません。

ちょうど今日から「萩まつり道了祭」が開かれていました。

このお寺には正岡子規も訪れたことがあるようで、子規の句碑もありました。

「ほろほろと 石にこぼれぬ 萩の露」と詠んでいます。

そんな関係もあってか、今日は俳句の集いも行われていました。

私も一句ひねればよかったのですが、うかばないので、写真でご勘弁ください。

萩も見頃で、こぢんまりとした、いいお寺でした。

秋ですね。










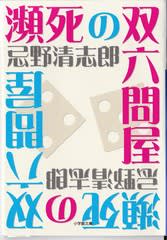
 (記念館の玄関)
(記念館の玄関) (ゆったりとした書斎です)
(ゆったりとした書斎です) (書斎の前から眺めるお庭)
(書斎の前から眺めるお庭) (いかにも安藤忠雄の設計です)
(いかにも安藤忠雄の設計です)