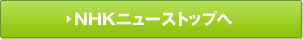日本軍がハワイ・真珠湾を奇襲して太平洋戦争が勃発してから、8日で70年を迎える。終戦までの3年8カ月の間に、日本人だけで約300万人が命を奪われた。補償を求める裁判が続くなど、戦争は今日にまでつながっている。大日本帝国の政府、軍部とも、アメリカとの戦争に勝つことはできないと承知していた。ではなぜ、開戦に踏み切ったのか。また、引き返す道はなかったのか。12・8から70年を前に、検証したい。【栗原俊雄】
●分水嶺、三国同盟
太平洋戦争に至った原因としては明治以来の大陸膨張政策や満州事変などさまざまな指摘がある。今回は平和と戦争の分水嶺(ぶんすいれい)の一つとなった、日独伊三国同盟(1940年)以降を中心にみてみよう。
欧州で独伊の、アジアで日本の指導的地位を相互に認め、第三国(事実上アメリカ)との武力衝突の際は相互に軍事的支援を行う--これが三国同盟の内容だ。
須藤眞志・京都産業大名誉教授(国際関係史)によれば「日本近代外交史上、最悪の選択」だった。「米国にとって最大の敵、ドイツと同じファシズムの国と認定されてしまった」からだ。井口治夫・名古屋大教授(日米関係史)も「フランスをあっという間に破ったドイツと日本が組めば、米国にとって脅威。日本は同盟を結ばず、その脅威をカードに対米交渉を続けるべきだった」と指摘する。
なぜ同盟を結んだのか。山田朗・明治大教授(近現代軍事史)は「第二次世界大戦初頭のドイツの華々しい勝利で日本、特に軍部は幻惑された。イギリスを屈服させられると信じた」と解説する。ドイツ勝利でアジアにおける植民地再分割に参加できる、との期待があった。
また、時の松岡洋右外相は、同盟で対米交渉を優位に進めようとし、ソ連を含めた4カ国同盟も想定していた。だが独ソ開戦で、松岡の構想は空中分解する。
●独頼みの戦争構想
日米間には圧倒的な国力差があった。独力で米国を屈服させることは不可能と、当時の日本政府、軍首脳とも承知していた。では、どのように戦争を構想したのか。
開戦直前の41年11月15日、大本営政府連絡会議で「戦争終結構想」が決定された。主な内容は(1)南方作戦で戦略的自給圏を確保する(2)中国の蒋介石政権への圧力を強める(3)独伊と連携し英国を屈服させる(4)それによって米国の戦意を失わせ、講和に持ち込む--といったものだ。対英戦争の主力は独軍だが、海軍力に乏しく、英軍を屈服させられるかは未知数。実現しても、それで米国が戦意を失うとは限らない。仮定の上に仮定を重ねた空想のような「戦争構想」で、日本は戦争へと進んでいく。
●仏印進駐が「引き金」
日本の中国侵略に対し、米国は対日経済制裁を強めた。日本はさらに40年9月23日、フランスの植民地だった北部仏印(現ベトナム北部)に進駐。すでにフランスはドイツに敗北しており、日本にとっては石油など戦略資源が豊富な南方を獲得する好機だった。英米などによる蒋介石政権への支援物資補給路(援蒋ルート)を断つ目的もあった。
これに米国は、くず鉄など戦略物資の禁輸で応じた。日本は翌年7月2日の御前会議で、南進を優先し、状況に応じ北進(対ソ戦)することを決めた。一方米国は、在米日本資産を凍結してしまった。
それでも同月28日、日本軍は南部仏印に進駐し、米側は対日石油輸出を全面的に禁止。日本の政府、軍首脳は、これを全く予想していなかった。
当時、日本は石油の大半を米国からの輸入に頼っており、打撃は大きかった。軍部の見立てでは石油備蓄量は2年分しかなかった。オランダの植民地だった蘭印(現インドネシア)からの輸入交渉も、うまくいかなかった。
「日本側は、北部と南部ではたいした違いがないとみていた。ところが米国にとっては南部進駐で(アジアにおける米軍の拠点)フィリピンが脅かされると感じた」と、等松春夫・防衛大学校教授(政治外交史・戦争史)。米国はこの時点で対日戦を決意した、とみる研究者が多い。
●「開戦決意」御前会議
国策については、政府や統帥部(陸軍参謀本部、海軍軍令部)首脳による「大本営政府連絡会議」で話し合い、その決定は天皇が臨席する御前会議で裁可された。会議では、天皇は発言しないのが習わしだった。
だが9月6日の御前会議で天皇は、明治天皇の和歌を読み上げた。「四方(よも)の海皆同胞(はらから)と思ふ世になど波風の立ち騒ぐらむ」。「避戦」のための、異例の発言だった。
だが、この日決定された「帝国国策遂行要領」には、10月下旬をめどに対米英蘭戦争の準備を完成させること、とある。また外交を進める一方、10月上旬ごろまでに要求貫徹のめどが立たない場合は「直ちに開戦を決意」することを決めた。戦争への、大きな前進--。
天皇の発言について戦中派の作家、五味川純平は後に「詩歌は感傷的感慨の表現手段でしかない」「朕(ちん)は戦争を欲せず、と言ったらどうであったか」と嘆息している。
●「切り札」東条内閣
対米交渉の鍵は中国撤兵だった。だが東条英機陸相ら陸軍強硬派は「多大な犠牲を払った中国から撤兵できない」と猛反対。日米交渉の見通しを失った近衛文麿首相は、内閣総辞職を選ぶ。
内大臣の木戸幸一は、後任首相として東条を天皇に推薦。陸軍ににらみがきく者を首相に据え、強硬派を抑える狙いだった。天皇は「『虎穴に入らずんば虎児を得ず』だね」と応じた。すでに米国という虎の尾を踏んでいたことに、日本の為政者は気づかなかった。
天皇は東条に、9月6日の決定を白紙に戻すように指示。東条は国策の変更を模索するが、国家が平和へとかじを切り直すことはなかった。
天皇が戦争回避を望んでいることを知った統帥部は、説得工作を進める。兵器や船舶確保の見通しについて具体的データを示し、対米英戦争は可能、とした。天皇は説得された。
山田教授は「甘い見通しだったが、軍官僚たちも安心材料が欲しかった。自分たちが作ったデータを信じるようになり、催眠術にかかったように『何とかなる』と思い込んだ」とみる。11月5日の御前会議で対米英蘭戦争を決意し、「武力発動の時期を12月初頭と定め」た。ただ、対米交渉が同月1日午前0時までに解決すれば、武力発動は停止することが確認された。
●拒否できぬ海軍
対米戦は、海軍が「ノー」と言えば始められない。自らの意思で「避戦」を貫くことのできない近衛や、陸軍の一部も、それに期待した。だが及川古志郎海相は「戦争をするかしないかは政府の決めること」と判断を回避。永野修身・軍令部総長はより強硬な対米開戦論者だった。
井上寿一・学習院大教授(日本政治外交史)は「海軍は対米戦を想定して軍備を拡張してきた。いざという時『戦えない』とは言えなかった」とみる。現代史家の秦郁彦氏も「時がたつほど国力の差が出てしまう。石油も心もとない。やるなら今、ということだった」と解説する。
井上教授は「軍部に複雑な国家運営を任せるのは無理。また明治憲法体制下では天皇親政は否定されている。本来なら政党が責任を果たすべきだった」と指摘する。だが2大政党、政友会と民政党は、腐敗や政争のため国民の支持を失った。さらに大政翼賛会に参加するため、解党してしまった。「権力の核が陸軍と海軍、外務省などに細胞分裂のように広がり、誰も調整できないまま戦争に突き進んでしまった」(井上教授)
●ハル・ノート
対米妥協を模索する東条内閣は、米側との交渉で11月7日に「甲案」を提示。主な内容は(1)日中間の平和が確立した場合、最大25年をめどに中国から撤兵する(2)仏印の進駐軍は、日中戦争の解決か極東平和の確立とともに撤兵する--だったが、事実上拒否された。さらに20日、乙案(日本が仏印以外の南東アジア、南太平洋地域には進駐しない代わりに米側は日米関係を資産凍結以前に戻す)を提示した。中国撤兵問題という懸案を棚上げするものだ。この時点で日本政府は、これを切り札かつ最終案と認識していた。
米側は結果的に「ハル・ノート」で応じた。主な内容は(1)中国、仏印からの撤兵(2)汪兆銘政権の否認(3)三国同盟の空文化。日本側の主張とかけ離れており、戦争を避けたがっていた東郷茂徳外相でさえ「もはや立ち上がるより外はない」と覚悟する内容だった。運命の開戦が決まった。
アメリカ側にも誤算があった。「対日強硬派は弱者(日本)は強者(米)に立ち向かわない、と読んだ。『窮鼠(きゅうそ)、猫をかむ』という発想はなかった」(須藤名誉教授)のだ。現実の歴史では日本は直ちに立ち上がり、米軍は緒戦に大きな痛手を受ける。日米は互いに、相手の譲れない一線を読み違えていた。
●誤算続き、日米交渉
井上教授は「日米間には開戦を不可避とするような対立点はなかった」とみる。ではどの時点なら、戦争への道を引き返せたのか。
日米関係の改善のための交渉は41年4月から本格化し、野村吉三郎駐米大使によって日米「諒解(りょうかい)案」の内容が本国に伝えられた。日本政府は、それが米側の提案であると認識した。内容は(1)日本軍の中国撤兵などを条件として、米国が満州国を承認、日中和平交渉を仲介する(2)日米通商航海条約の実質的復活(3)米側は三国同盟を防衛的なものとして解釈し容認する--など。
日本に大きく配慮した内容で、天皇は「我国が独伊と同盟を結んだからとも云(い)える、総(すべ)ては忍耐だね、我慢だね」と喜んだ。
だが同案は、実は日米の民間人らが作成した試案だった。米側のハル国務長官の真意は(1)他国領土保全と主権尊重(2)内政不干渉(3)通商上の機会均等(4)太平洋の現状維持--との「4原則」で、日本の希望とはかけ離れていた。ただハルも、暫定案を交渉のたたき台として認めてはいた。
ところが、頭越しの交渉を知った松岡外相が反発。日本政府の回答は遅れ、しかも松岡の意を受けてはるかに後退したものになった。諒解案は雲散霧消する。
対米交渉に行き詰まった近衛首相は、米側にルーズベルト大統領との直接交渉を申し入れた。中国撤兵を約束し、あとで天皇の認可を得るというもくろみだった。
しかし米側はこれを拒否。近衛の指導力、日本の外交そのものへの不信感もあった。須藤名誉教授は「近衛は天皇の許可を得ていた節がある。実現していれば、日米交渉は続いたのでは」と言う。
日本の乙案提示後、米側は(1)民需用石油に限り禁輸を暫定的に3カ月停止し、その後は交渉次第で延長する(2)日本軍は南部仏印から撤兵する--という「暫定協定案」を用意していた。だが中国が強く反対。チャーチル英首相も同調し、結局提示は見送られた。スティムソン陸軍長官から、日本の大輸送船団がインドシナへ向け航行中であることを聞いたルーズベルト大統領が激怒したため、という説もある。東条は敗戦後、「あれ(協定案)が来ればなあ」と悔やんだという。
●避戦の可能性
ハル・ノートが開戦につながる「最後通告(通牒(つうちょう))」だったかどうかは、当時から議論がある。外務省を退職していた吉田茂は「最後通牒ではない」と、東郷外相に交渉継続を訴えた。問題の中国撤兵も「事実上、満州は除外されていた」(井上教授)。秦氏も「中国からすぐに出て行けという内容ではない。国際情勢をにらみながら対応していれば、活路が見えた」と話す。
真珠湾奇襲の直前、ソ連軍は独軍への反転大攻勢を始めていた。ハル・ノートをたたき台として交渉を続けていれば、独軍の苦戦が明らかになり、日本の戦略は足元から揺らぐ。日本は開戦に踏み切れなかったかもしれない。
●暴走の教訓とは
70年前、破滅的な戦争へと突き進んだ歴史から、後世の私たちは何を学ぶべきだろうか。
国策決定者たちは、自分たちに好都合な情報を集め、希望的観測を続けた。その結果、独ソ戦の勃発や米国による石油禁輸など「想定外」の事態によって、窮地に追い込まれた。彼らが戦争へと前のめりになる中で、避戦を模索し続けた者も、少数ながらいた。国家は、それをくみ取れなかったのだ。
今年、東京電力福島第1原発の事故が発生。国策である原発推進の危険性を指摘する声は昔からあったが、生かされなかった。「原発は安全」という希望的観測は、「想定外」の巨大地震と大津波で崩壊した。
国策決定者・組織は時に、取り返しのつかない判断ミスを犯すものだ。しかし、今昔のミスに違う点もある。
開戦という国策決定には軍官僚や宮廷政治家ら、国民が選ぶことのできない者たちが大きな役割を占めた。当時、女性に参政権はない。国策に反対する言論の自由もなかった。
戦後、国民の権利は増大した。国家を運営する官僚は選べないが、政治家と政党を選ぶことはできる。戦前に比べ権限が強化された首相も、間接的にではあるが選出が可能だ。
それだけに、私たち選ぶ側の責任は大きい。戦争の惨禍で今も多くの人々が苦しんでいるように、選択失敗のツケは後世にまで累を及ぼすことを肝に銘じたい。
==============
◇「生きて帰れぬ」覚悟--真珠湾攻撃隊
前田武さん(90)は空母「加賀」の97式艦上攻撃機(艦攻、3人乗り)の偵察員だった。艦攻は800キロの魚雷を抱いていた。
真珠湾の深さは平均およそ12メートル。魚雷は投下すると50メートル程度潜るため攻撃は不可能だが、日本海軍は浅深度魚雷を開発した。さらに海面10メートルほどの低空から投下するため、搭乗員に猛訓練を課した。鹿児島湾などでの訓練は「土曜も日曜もなかった。嫌になるほど繰り返しやった」。
「浅深度魚雷は40本ほどしかなく、必ず当てられる者しか乗れなかった。名誉でしたね」。出航前、上官に「家族とお別れしてこい」と言われ、「戦争だ。シンガポール攻撃か」と話し合った。11月26日、機動部隊は択捉島の単冠(ひとかっぷ)湾を出撃した。そこで目的地を知らされたが、「アメリカとの和平が成立すれば帰る」とも言われた。「戦争はしない方がいい」と思った。
発艦するとき「生きては帰れないだろうな」と覚悟した。狙いは米戦艦ウェストバージニア。「魚雷が当たった瞬間、泥水がばーっと上がってきて、飛行機の中に入った。ふつうなら青い水が上がってくるのに」。「奇想天外な作戦」は成功した。
前田さんはその後ミッドウェー沖海戦、沖縄戦も生き抜いた。
◇「政府広報機関」新聞の責任
東京日日新聞(現毎日新聞)は8日の夕刊(日付は9日)で、1面トップに昭和天皇の詔勅を掲載した。詔勅は中国の蒋介石政権を「東亜ノ平和ヲ攪乱(かくらん)」、米英を「東洋制覇」をもくろんでいると批判。「東亜永遠ノ平和ヲ確立シ以(もっ)テ帝国ノ光栄ヲ保全セムコトヲ期ス」などとした。続いて「英米の暴政を排し/東亜の本然を復す」との見出しの記事で「軍官民一体となって国難を突破する用意は全く成った」「真の平和を期待する明日の世界のために不退転の決意と不屈の努力を傾倒する」と記した。政府声明をそのまま載せ、政府支持一色の紙面だ。
ノンフィクション作家の保阪正康さんは開戦の経緯における新聞の責任を鋭く指摘する。「当時の新聞社は政府の広報機関。多少の例外はあるが、記者はジャーナリストではなく宣伝要員だった。同情すべき点もあるが、今日の教訓にすべきだ」
==============
◇主な参考文献(順不同)
新名丈夫編「海軍戦争検討会議記録」(毎日新聞社)▽五味川純平「御前会議」(文春文庫)▽半藤一利、加藤陽子「昭和史裁判」(文芸春秋)▽吉田裕「アジア・太平洋戦争」(岩波新書)▽井口武夫「開戦神話」(中公文庫)▽古川隆久「昭和天皇」(中公新書)▽山田朗「昭和天皇の軍事思想と戦略」(校倉書房)▽須藤眞志「日米開戦外交の研究」(慶応通信)▽保阪正康「昭和陸軍の研究(上)」(朝日文庫)▽秦郁彦「統帥権と帝国陸海軍の時代」(平凡社新書)▽防衛庁防衛研修所戦史室編「戦史叢書 大本営陸軍部 大東亜戦争開戦経緯<5>」(朝雲新聞社)▽寺崎英成、マリコ・テラサキ・ミラー編著「昭和天皇独白録」(文芸春秋)▽コーデル・ハル「回想録」(朝日新聞社訳・朝日新聞社)▽参謀本部編「杉山メモ(上)」(原書房)▽ジョセフ・C・グルー「滞日十年(下)」(石川欣一訳・毎日新聞社)


 出典●http://www.mitene.or.jp/~kakoya/p/hisi.html
出典●http://www.mitene.or.jp/~kakoya/p/hisi.html