

いやあ。
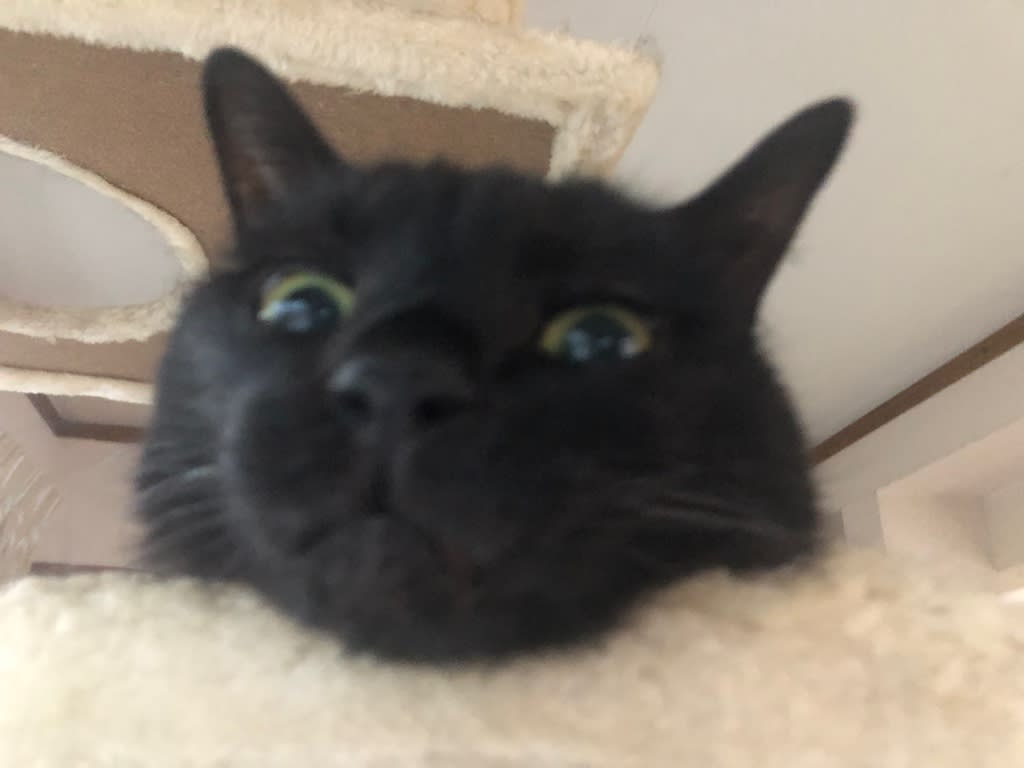


部屋を整理していたら、昔の

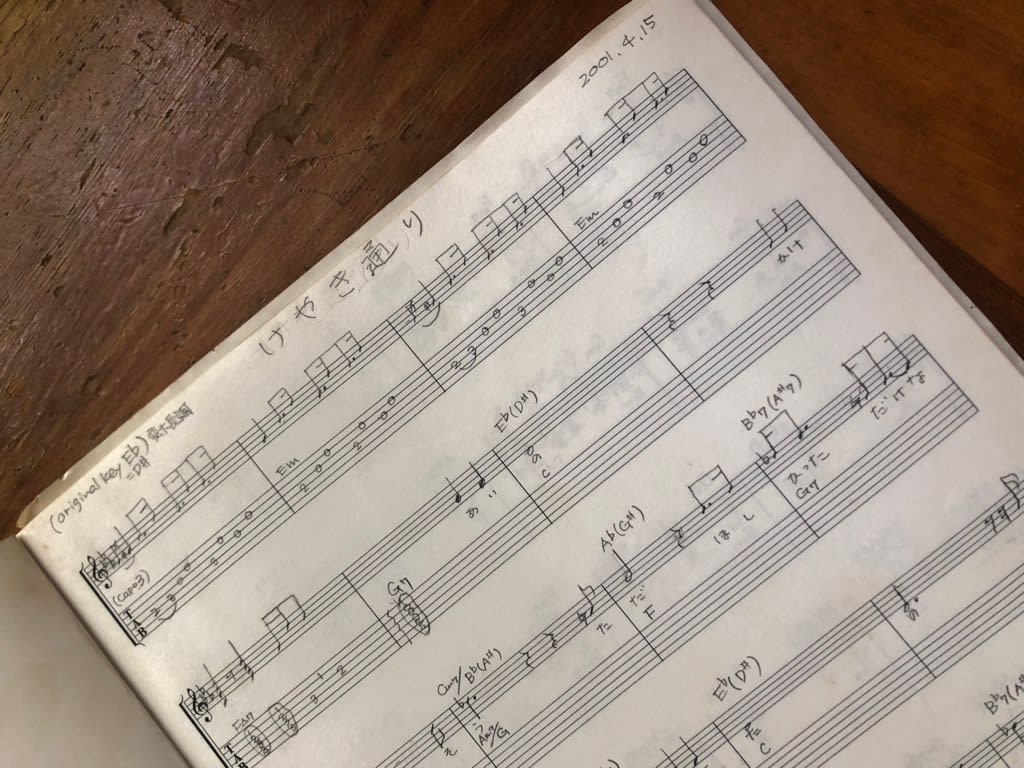






現在の日本の包丁の形は地球上
の万国のスタンダードとなって
いる。
世界中の包丁が日本をお手本に
して日本が世界を牽引している
訳だが、この現在の日本の包丁
の形状が成立したのは幕末の
文化文政年間のことだ。
それまでの日本の包丁は正倉院
に残っているような、いわば
日本刀の小刀や短刀形状の物を
料理包丁として使っていた。
つまり、柄の延長線上に刀身が
ある物だった。これは江戸期
中期頃まで続いた。(例外あり)
(正倉院に残る古代の包丁)
(江戸期の包丁。この形が
幕末まで一般的だった)
初ガツオをさばく女性
『十二月の内 卯月初時鳥』
(豊国作/国立国会図書館蔵)
現在の包丁は、平和な世になり、
堺の鉄砲鍛冶が鉄砲製造の仕事
が激減したため包丁鍛冶に転じ
たことを嚆矢として、各地の刀
鍛冶も包丁鍛冶に転じたりした
ことにより一気に発達した。
『日本山海名物図絵 巻之三 堺包丁』
(平瀬徹斎著/長谷川光信画/
宝暦四年-1754年)
この堺の包丁には、出刃包丁と
刺身包丁等が図示されている。
さらに「まな箸」と「たばこ包丁」
も名物として紹介されている。
幅が広い菜切も見える。
ただし、これらは、1754年時点
でまだ「名物」であるので、一般
的に全国的に普及するのは1800
年代に入ってからであるとする
のは、各種文献等や江戸期から
続く現代包丁のメーカーの論に
蓋然性があるし首肯できる。
現代に続く日本の包丁の形状が
ほぼ確立されるのは、幕末に入
ってからというのがどうやら
歴史事実のようだ。
私個人は、それまで一千年以上
続いた日本の短刀形の包丁が、
なぜ幕末に一気に現在の形状に
なったのかという疑問がある。
短刀はこのような太刀・刀の
ごとき使い方はしない。
短刀も包丁も片手で使うが、
包丁は幕末期に現在のような
柄の延長線から下方に身と刃が
伸びた形状になった。

私はふと思いついたが、これは
包丁を造る鍛冶職人が、それ
までの刀とは別形状の物を考
案して、物理的に使い勝手の
よいことを思いついて新規導
入した結果、現在まで続く形
状になったのではなかろうか。
そして、その形状は何からヒント
を得たかというと、鍛冶職自身
が使うこれだ。


通常の玄翁(トンカチ)とは
異なり、鍛冶職が使用する鎚=
ハンマーは効率良く力が伝達
できるようにするため、長年
の経験から柄部分よりも下方
向に本体の身が伸びた形状に
なっている。
この鍛冶が使う手槌の形を刃物
に置き換えたのが江戸幕末~
現代の日本包丁の形状だったの
ではなかろうか。
それまでの包丁はいってみれば
ナイフと同じで、このようなシ
ルエットとなる。
あるいはこちら。(上側が刃。
これは片刃小刀)
このような形状は、ゴボウの
ような物を手に持って削るに
はよいが、まな板を使って食
材を切断したり、細かい加工を
するのにはかなり不便である
ことが現代包丁(江戸幕末に
発明された形の包丁)を使用し
てみるとよくわかる。
(現代包丁)
私は思うのだ。
この幕末に考案された堺の鉄砲
鍛冶から始まり、各地刀鍛冶が
その流れに合流して形成されて
きた日本の包丁の形状は、鍛冶
職が使用する鎚を見て、ある時
どこかのだれかの鍛冶が「これだ」
と思いついて実行し、それが世
に広まったのではと。
そして、その包丁は日本の常識
となり、21世紀の現在、地球上
でのスタンダードとなっていっ
たのでは、と。
だとするならば、最初に「あ、
これは・・・」と思いついた
鍛冶職は歴史的足跡を残した。
(この形からコミのあるアゴ
の出た包丁の形状を思いつい
たのでは)
今の日本の包丁というのは、
本当に実に使いやすい刃物だ。
まな板の上で作る料理に最適な
形をしている。
この包丁の形状の劇的な変化
(緩やかな変化ではなく革命
的とも呼べる一挙的な変化)の
現象は、鉄砲鍛冶、刀鍛冶職
が転職を余儀なくされた時代
背景、大衆食文化の絢爛化、
まな板の普及発達、といった
社会背景の大きな転換点に
発生している。
現行に繋がる日本文化のほとん
どが江戸中期~幕末期に形成さ
れたが(着物なども江戸初期の
物ではなく、中期以降幕末期の
物が現代まで継続している)、
やはり幕末に大きな転換が日本
社会の各方面に見られる。
包丁の変化も、その社会現象と
リンクする文化史の側面を形成
する一現象のように捉えること
ができると私は思うのである。
そうした大局から俯瞰すると、
「包丁はなぜあの形になった
のか」ということも薄っすらと
おぼろげながらシルエットが
見えてくる。
もっと早い時期(例えば南北
朝時代とか)に現行の包丁の
形状になってもよかったとは
思いがちだが、江戸期に平和
産業へ転じた武器鍛冶の存在、
時代の大きな変化と要請という
ものがなければ、現行の包丁の
カタチというものは登場しな
かったのではなかろうか。
その日本の包丁が現在世界各国
の包丁に影響を与えている。
三徳と呼ばれる包丁の形状は
SANTOKU という固有名詞と
なって、KIMONO のように
日本文化の定番として海外では
認識されるに至った。
文化包丁と呼ばれる、文化年間
に確立した今ではどこにでも見
られる一般的な家庭用料理包丁
がいわゆるそれである。
現在、日本の料理文化=包丁文
化が世界を席巻し、世界中に影
響を与えて世界の食文化に利便
性を提供している。
社会情勢の変化が背景にあった
とはいえ、もし、今の包丁の
カタチを思いついて考案したの
が名もない一鍛冶職だったと
すると、その鍛冶職は、とてつ
もないことをやってのけた人だ
と私は思う。
ただし、日本刀型短刀系の旧
包丁の形状に近い包丁も現代
には存在する。
それは精肉を作る際に使用す
る「骨スキ」と呼ばれる包丁
だ。
刀身に微妙な反りもあり、反り
により現行狩猟用洋式ナイフの
スキナーの役目も果たし、さら
に柄の延長線上に刃があること
で肉の削ぎ落しや解体に便利な
力を加えやすい形状となって
いると見受けられる。
しかし、大型家畜である牛や豚
の精肉業が大規模に始まるのは
明治以降であるので、これが
旧和包丁の短刀型形状を継承し
た物であるか否かは私は知らな
い。
(骨スキ包丁。肉塊解体専用の包丁)









クリームソーダというとメロン

実はクリームソーダにはいろん

最近は居酒屋でも出し始めた





































