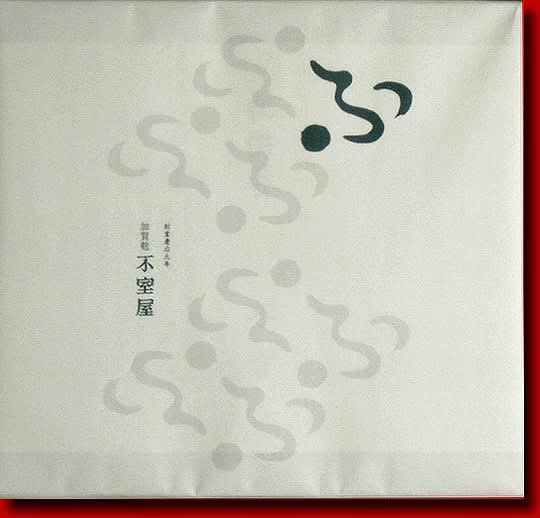今日は、2月のお供えを買いに行った時のことです。
●冬の季節菓子「宗家 源吉兆庵 柚子そうめん(とこよ)」

ゆずには、夏の旬である7月~8月に収穫される「青ゆず」と
冬の旬である10月~12月の黄色く熟した「黄ゆず」があります。
気になる名前の「とこよ」は
永久に変わらない神域を意味する「常世」からでは・・・?

黄ゆずの、ほろ苦い風味の柚子皮は酸味や甘さが強くなるので
ジュースや柚子茶として飲まれることが多くなります。
この時期が、私には一番おいしいゆずを頂けるように思います。
●春の季節菓子「叶 匠壽庵 あも(桜)」

「あも」は、このブログに何度も掲載していますが
この「あも(桜)」は初めてです。

叶匠寿庵へ行くと
店先に、季節限定のあも「春は 桜」が置かれていました。
kiko
「えっ! あもに(桜)があるの~?」
店員さん
「(桜)は、塩漬けした桜葉を羽二重餅に練り込んでいます。」
塩漬けした桜葉を楽しみたくて買ってきました。(美味)
前までは、甘いものを欲しがらない人だったのですが・・・
最近はお下がりが待ち遠しくなり、美味しく頂いてます。
●冬の季節菓子「宗家 源吉兆庵 柚子そうめん(とこよ)」

ゆずには、夏の旬である7月~8月に収穫される「青ゆず」と
冬の旬である10月~12月の黄色く熟した「黄ゆず」があります。
気になる名前の「とこよ」は
永久に変わらない神域を意味する「常世」からでは・・・?

黄ゆずの、ほろ苦い風味の柚子皮は酸味や甘さが強くなるので
ジュースや柚子茶として飲まれることが多くなります。
この時期が、私には一番おいしいゆずを頂けるように思います。
●春の季節菓子「叶 匠壽庵 あも(桜)」

「あも」は、このブログに何度も掲載していますが
この「あも(桜)」は初めてです。

叶匠寿庵へ行くと
店先に、季節限定のあも「春は 桜」が置かれていました。
kiko
「えっ! あもに(桜)があるの~?」
店員さん
「(桜)は、塩漬けした桜葉を羽二重餅に練り込んでいます。」
塩漬けした桜葉を楽しみたくて買ってきました。(美味)
前までは、甘いものを欲しがらない人だったのですが・・・
最近はお下がりが待ち遠しくなり、美味しく頂いてます。