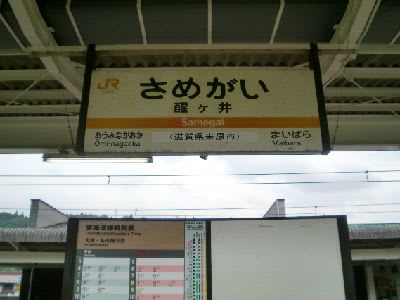滋賀県には、忘れられない水の上に浮かぶ芸術作品のような「佐川美術館」と
さらに山中へ入ると、海外からも注目を集める「MIHO MUSEUM」があります。

MIHO MUSEUM (ミホミュージアム) は、滋賀県甲賀市信楽町にある
滋賀県の登録博物館で、運営は公益財団法人秀明文化財団です。
神慈秀明会の会主・小山美秀子氏のコレクションを展示するため
1997年(平成9年)11月に開館しました。
コレクションは、ギリシア、ローマ、エジプト、中近東、ガンダーラ
中国、日本など、幅広い地域と時代に渡る優品2000点以上が含まれ
日本の私立美術館のコレクションとしては有数のものだそうです。

レセプション棟と展示館の間を往復している電気自動車がありますが
私たちは、桜の季節には絶景だろうと思われる桜並木を歩いて行きました。

少し行くと、聞いていた名物のトンネルがありました。

トンネルの中は思っていた以上に
広くて長くゴミ一つ落ちていませんでした。

トンネルの出口からは、吊り橋とその先に広がる景観から
海外からも注目を集める展示館が見えました。

これは、利用者の移動の便のためと環境にあわせた電気自動車です。

周囲の自然景観保全に配慮して、建築容積の8割が地下に埋没しています。
建物設計は、ルーヴル美術館の「ガラスのピラミッド」、ワシントンの
ナショナル・ギャラリー東館で有名な建築家の、イオ・ミン・ペイ氏です。

設備設計は、多くの建築設備設計を行っている森村設計が担当して
美術品の価値や存在意義を維持するのに最適な環境を構築しています。

展示館に入り・・・振り返ると見えたのは
いま、私達が通ってきた 「トンネルと吊り橋」でした。 (2012年 撮)
〒529-1814 滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷300
さらに山中へ入ると、海外からも注目を集める「MIHO MUSEUM」があります。

MIHO MUSEUM (ミホミュージアム) は、滋賀県甲賀市信楽町にある
滋賀県の登録博物館で、運営は公益財団法人秀明文化財団です。
神慈秀明会の会主・小山美秀子氏のコレクションを展示するため
1997年(平成9年)11月に開館しました。
コレクションは、ギリシア、ローマ、エジプト、中近東、ガンダーラ
中国、日本など、幅広い地域と時代に渡る優品2000点以上が含まれ
日本の私立美術館のコレクションとしては有数のものだそうです。

レセプション棟と展示館の間を往復している電気自動車がありますが
私たちは、桜の季節には絶景だろうと思われる桜並木を歩いて行きました。

少し行くと、聞いていた名物のトンネルがありました。

トンネルの中は思っていた以上に
広くて長くゴミ一つ落ちていませんでした。

トンネルの出口からは、吊り橋とその先に広がる景観から
海外からも注目を集める展示館が見えました。

これは、利用者の移動の便のためと環境にあわせた電気自動車です。

周囲の自然景観保全に配慮して、建築容積の8割が地下に埋没しています。
建物設計は、ルーヴル美術館の「ガラスのピラミッド」、ワシントンの
ナショナル・ギャラリー東館で有名な建築家の、イオ・ミン・ペイ氏です。

設備設計は、多くの建築設備設計を行っている森村設計が担当して
美術品の価値や存在意義を維持するのに最適な環境を構築しています。

展示館に入り・・・振り返ると見えたのは
いま、私達が通ってきた 「トンネルと吊り橋」でした。 (2012年 撮)
〒529-1814 滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷300