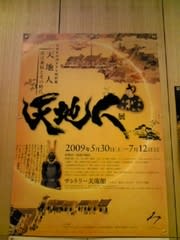@サントリー美術館

今日が最終日。
最終日の日曜なんて混んでそうな日、ふだんだったら絶対行かないけど、
やむなく今日行ってきた。
本当は金曜の夜に行こうとしていて、入り口まで行ったんだけどさ。
そこで前売りチケットを入れてあるお財布を忘れたことに気付いて
中に入れないっていう、アホみたいな失態をしていたのだ。
無駄な交通費と時間を費やしてしまった。
そんなワケでなるべく空いている時間にと思って、10:45頃には到着。
それでもけっこうな人だったけど。
江戸時代に日本に登場した、江戸切子や薩摩切子と呼ばれるカットガラス。
カットガラスが“ギヤマン”と呼ばれたのは、ポルトガル語の“ディヤマンテ”
=ダイヤモンドが語源になっているそう。
薩摩藩主の島津斉興が始めた薩摩藩のガラス産業は、おもに薬を入れる容器のために
作ったのがはじまりで、そのあと斉彬の代になって美術工芸品としてのものが
つくられていったそう。
19世紀のイギリス、アイルランドのカットガラスは、
細かいカットが光を反射してキラキラ
 している。
している。時間がたっても変わらない輝き。
深紅の色ガラスは薩摩が日本で初めて発色したそう。
小皿や、脚付き盃、紅い色味がキレイだなぁ。
展示台にうつる影までが美しい。
美しいものは影までもが美しいってことだね。
キッカワとおんなじ(笑)シルエット大賞

日差しのあたるテーブルに置いたら、どんな影をつくるのか見てみたい。
小さい脚付盃は、食前酒を入れたい。
小さい盃には酒盗とかね。
蓋付きの四角い三段重とか、何を入れたんだろうなーと気になる。
香水瓶がまた美しかったー。
なかには筆洗いなんてのもあった。
ガラスの入れ物で筆を洗うなんて、洒落ているなぁ。
脚付き盃は脚の部分がどっしりしたつくりになっているので
日用品っていうよりは、美術品として扱われていたのかな。
なかでも、へばりついて見てしまったのは雛道具
すんごい小さいのに、切子細工がほどこされている。
徳川記念財団の所蔵で、篤姫所用のものとされているみたい。
他にも、徳川記念財団所蔵の薩摩切子は篤姫の婚礼のときに
用意されたものじゃなかとされているとか。
深紅、藍色、紫、透明。
どれもため息のでるようなキレイさだった。
切子の文様には、それぞれ名前がついているのがへぇ~でした。
交通費2回分かけてでも行ってよかった。
キラキラきれいなものを見て、なんか脳みそのそうじができた感じ?
次はコレ