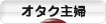コミックと映画は中身が違いますが、大友克洋の短編コミックと同じタイトルの付いたこの作品。
最後に「武器よさらば」を持ってきているからだと思いますが、
なにか、とても懐かしい“大友”を観たような印象でした。
「オープニングアニメーション」
デザインワーク/作画/監督:森本晃司
かくれんぼをする少女や
鳥居の向こうから異次元に飛ぶというのは、新しさは感じないものの、
綺麗な映像で見せられると、やっぱりいいですね。
テーマが“日本”なんだから導入としてはいい感じ、麻衣ちゃんカワイイし。
「九十九」
脚本/監督:森田修平 ストーリー原案/コンセプトデザイン:岸 啓介 キャラクターデザイン:桟敷大祐
18世紀。嵐の夜、深い山中で男が道に迷っていた。そこで見つけた小さな祠。
中に入るとその空間は突然別世界の部屋に変化する。
そこに次々と現れたのは捨てられた傘や、着てもらえなくなった着物などのモノノケ達。
男はその怨念を秘めた古い道具たちを丁寧に修理し、慰めてやる。
これは最初と最後に出てくる手書き風の樹海の背景とCG処理された人物との
馴染まなさ加減が半端なかった。いやこれはわざとこうしたのか!?
あの草木だらけの大地をオッチャン踏みしめてないだろw浮いてるよww転んじゃうよwww
それが別世界の部屋に入った途端一変するんだよね。
この完全CG世界は見応えありました。
反物を折り畳んでこれから縫うってとこの一瞬だけ映る畳んだ反物が
質感まで伝わるくらいでした。
けどね、リアル感のあるCG画面でいうなら、先日観た新海誠の『言の葉の庭』に負けてます。
技術は進歩してるよねって感じはするけど、『九十九』には新しさが見えない。
モノノケと男っていうと、どうしても『モノノ怪』の方が魅力的でこのオッチャンじゃ萌ねぇw
「火要鎮」
脚本/監督:大友克洋 キャラクターデザイン/ビジュアルコンセプト:小原秀一
18世紀、江戸の町。商家の娘お若と幼馴染の松吉。
惹かれあう二人であったが、松吉は家を勘当され町火消しとして生きる。
そんな最中、お若の縁談の話が進み始めた。
松吉への思いを忘れられない彼女の狂った情念からの行動は、
大火事を引き起こし江戸の町を焼き尽くす。
その大火の中で再びめぐり合う二人。巨大都市江戸の大火を舞台としたスペクタクル。
これはさすがに画が良かった。
日本画の様式美の世界に随所にCG処理をしていて『言の葉の庭』とは別の新しさを感じました。
今まで見た事のない大友作品ですが、凝りに凝ってる感じはやはり大友w
これぞジャパニメーションですかね。
残念だったのはストーリーの最後かな。えっ!?これで終わり??でした。
まあ、二人とも焼かれておしまいなんだろうけど、
もうちょっと悲恋を煽っても良かったんじゃないだろか。
「GANBO」
監督:安藤裕章 原案/脚本/クリエイティブディレクター:石井克人 キャラクターデザイン原案:貞本義行
16世紀末。戦国時代末期。東北地方(最上領)の山中に天空より何かが落下した。
直後、寒村に一匹の巨大な鬼のような化け物が現れ略奪の限りを尽くす。
時を同じくして寒村に暮らす少女カオは白い熊と出会う。
人の言葉を理解するその神秘的な熊にカオは救いを求めた。かくして鬼と白熊との激闘がはじまる。
新機軸のバイオレンス作品たるべく、荒く力強い画面を3DCGの技術を活用し描き出す。
貞本義行のキャラデザだけど、なんだか石ノ森章太郎の描く女の子のような印象でした。
鬼の造形がゲロゲロで衝撃的でしたw
「武器よさらば」
脚本/監督:カトキハジメ 原作:大友克洋 キャラクターデザイン:田中達之
近未来。東京。砂漠の中の廃墟と化した都市を訪れたプロテクションスーツで武装した5人からなる小隊は
一台の戦車型無人兵器と遭遇戦となる。しかし、次第に歯車が狂い始め小隊は窮地に陥っていく。
大友克洋の原作による伝説的な戦闘アクション漫画を、再構築し、
リアリティと革新性のある描写をめざした。
エキサイティングなアクション作品でありながらも、無常観の漂うテイストに仕上げた作品。
“大友克洋本人を越えるほどの大友克洋らしさを目指した”とありますが
それは大成功だったんじゃないだろか。
観ていて「ああ、大友のマンガだぁ。」と込上げましたもんw
戦闘シーンは迫力あるし、無常感漂うラストも
昔はこんな終わり方するマンガ、いっぱい描いてたよなぁなんて。
このテイストで『童夢』の映像化観たいな。
奮発して1,500円もするパンフ買ったら、納得の値段でしたw
黒いケースに入ってて、やたら分厚い。
チラシと同じデザインの表紙の冊子と蛇腹折りになった絵巻物?
片面は「火要鎮」の冒頭、子供のお若が出てくるところまで。
もう片面はそれぞれの作品の画です。
なんとも豪華です。