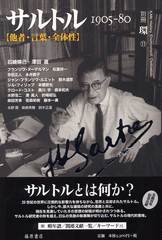| サルトル―1905-80藤原書店このアイテムの詳細を見る |
今回はサルトルとアンガージュマンということを考える第一歩としてアンガージュマン文学ということについて考えてみたいと思う。
まずは、最初にアンガージュマンという概念についておそらくここでは初めてきちんと検討したい思う。
本書の284ページ「サルトルを読むためのキーワード25」を視てみると、
「・アンガージュマンengagement
『社会参加』と訳されることもあり、知識人が政治に参加するということというように考えられているが、サルトルは必ずしもそういう能動的な意味としてのみでこの言葉を使っているわけではない。この言葉の元になっているアンガジェという動詞は『拘束する』とか『巻き込む』という意味であり、アンガージュマンという言葉にも、人間が世界に巻き込まれ、世界と否応なく関係している、という受動的な意味が込められている」(後に『存在と無』(上)
サルトルは、「作家は、誰であれアンガジェ」(51ページより)しており「作家は意識するにせよしないにせよ、時代の中での自らのアンガージュマンについて書くのです。『ひとつの時代の文学、それは文学によって消化された時代である』」(同)という風に捉えており、たとえ、いかにも政治的であったり経済的であったりとしない文学であっても、時代にアンガジェしているという風に捉えている。
このことを鈴木道彦氏は、
「『アンガージュマン文学』とは、あらゆる『知』を総動員してその全体化に迫ると共に、全体化の部分でもあれば動因でもある自分自身の存在を、張りつめた自覚と共に表現するもになる」というように評している。(115ページ)
また、鈴木氏は、
「作品を書くという行為自体は、世界内存在のひとつの選択であり、実践であるが、同時に言葉で表現することを選び、想像的なものを選ぶ以上は、どうしてそれがほかならぬ言葉であり、想像界でなければならないのか、ということは、やはり問われなければならない。」
「同時に書くということが世界内存在の実践であるならば、たとえ想像的なもの、つまりは存在しないものを作り出す行為であっても、他人の対象となる作品を生み出す以上は、これも他の行為と同じく、『方法の問題』でサルトルが言う『内面化を通っての客観的なものから客観的なものへの移り行き』の一つということになるだろう。その意味で、文学にはなんら特権的なものなどありはしない。人は書かなくてもいいし、別なものを選んでもちっともかまわない。またそうやって選んだ別のものが、世界を映し出すということもあるだろう。人間の行為は全体的なものだからだ。」(117ページより)
という風にも述べている。
何かを作り出すということ、何か行動を起こすということはその程度の差こそあれ、社会に巻き込まれており、それはの程度の差こそあれ、社会への参画を意味しているということであろう。
最後に今後アンガージュマンという概念を考えていく上においても参考になるであろうということから、フランソワ・ヌーデルマンによる分析を参照して締めくくるとする。
彼は、サルトルのアンガージュマンという言葉表現域(50ページより)として、
①声を受肉すること
②<人間以下の状況におかれて苦しみ>声なき人々に声を与えること
③拡声器であること
という3つを挙げている。
それぞれに対して具体的な説明がなされているわけではないが、
①の声を受肉すことということは、「私の身体もしくは他者の身体をして、肉体たらしめること」(『存在と無』(上),577『存在と無』用語解説より)という風に定義されている。
つまりは、この声を受肉するということという文脈においては、声という概念の本質たらしめるということ、声を届けるようにするということ、もしくは、声を躍動感を持たせ伝わる状態にもっていくということであろう。
②については呼んで字のごときである。
③については、今風にいえばアジテーションをするというか、ある主義主張を公に伝えるということであろう。
今回はここらあたりでしめるとして、
次回は、『存在と無』のページに取り上げることと少しかぶるかもしれないが、サルトルの自我観、倫理観ということをこの本より考えてみたいと思う。