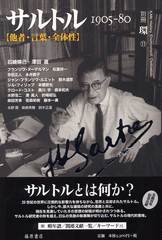| サルトル―1905-80藤原書店このアイテムの詳細を見る |
哲学者としてのサルトルの続き
③自由と状況を連結した
サルトルは、われわれは歴史的、経済的、社会的などあらゆる状況に「拘束され、全面的に自由な人間」〈本書112ページサルトル創刊の『現代』誌創刊の辞としてのことば〉であるというように捉えている。
われわれは自由であるが、それゆえ選択の基準が必要だ。
それは、本来性ということだ、水野浩二氏によると「自由とは、本来性に到達した状態のこと」〈本書207ページより〉である。
自由で在るからこそ、本来性に到達するということが私たちに求められているであろう倫理的な基準ということであろう。
さて、水野氏は、本来的であるということを「状況がいかなるものであれ、自己の〈状況-内-存在〉を余すことなく現実化すること」「自己の状況を『自覚し』、『引き受ける』こと」〈同〉という様に定義している。
われわれが本来的姿になるためには、水野氏はサルトルの『倫理学ノート』からの言葉として純粋な反省が必要であるとした上で、
「純粋な反省は、私の企てそのものによって、その企てが他者に対して現れるかぎりにおいてではなく、その企てが私の方へその主観的な面を向ける限りにおいて私を定義するのである。というのも、本来性に従えば、唯一妥当な投企は、〈在る〉ではなくて〈為す〉であるからであり、しかも、為すという投企は、具体的な状況に働きかけ、その状況をある方向に変える投企であるからである。」(同208ページ)という風に説く。
また、本来性への回帰を促す「純粋な反省」は〈挫折〉という経験によって導かれるというようにも水野氏は説いてもいる。
この〈挫折〉というものは、何も私たちがイメージするようないわゆる挫折とは少し意味合いが違うようだ。
状況に拘束された中で、そこへ自らを投企することによってしか生きることができない状況をさして、それを不自由としその状況をこそ〈挫折〉という風にサルトルは述べているようだ。
つまりは、生きとし生ける状況において、対自存在として自分の今にどのように関わるかということのベクトルが純粋な反省ということにつながるのであろう。
ここでの議論をいわばハウツー本的に言い換えるならば、「人間は、今ある状況において、自分を律することをしながら生きていくことが大切なのですよ。」といった意味になるだろうか。
読み流してしまうと意味を解すことが難しい哲学書ではあるが、じっくり読むとなんと感慨深い内容だ。