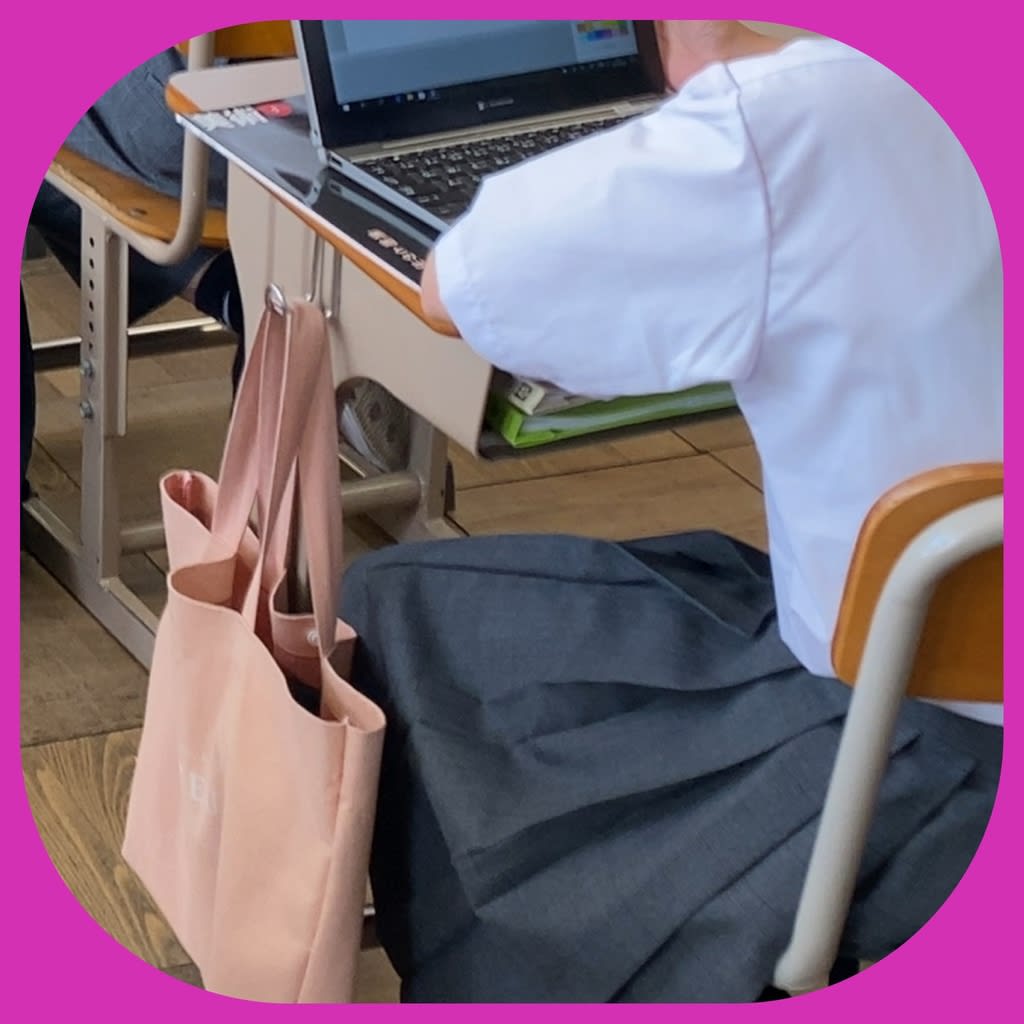
2022年が明け、新型コロナウイルス感染症は3年目にはいりました。
「自宅で過ごす時間が増えた。」
これが、新型コロナウイルス感染防止のためにテレワークを行った企業に勤める人たちの感想です。
自宅時間の増加は、男性にも女性にも共通しています。
では、この自宅にいる時間の増加で家庭生活に満足した人が増えたのか、減ったのかという点にはどうだったのでしょうか。
内閣府の「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」が参考になります。
「生活に満足している」という度合いが、感染拡大した2020年2月から春までの間に下がっていますが、女性の方がより大きく下がりました。(第1回調査結果)
では、何が女性の生活への満足度を大きく下げたのでしか。
家族が家で過ごす時間が長くなったことにより、家事・育児の男女別役割はどう変わったのかがカギになります。
では、この自宅にいる時間の増加で家庭生活に満足した人が増えたのか、減ったのかという点にはどうだったのでしょうか。
内閣府の「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」が参考になります。
「生活に満足している」という度合いが、感染拡大した2020年2月から春までの間に下がっていますが、女性の方がより大きく下がりました。(第1回調査結果)
では、何が女性の生活への満足度を大きく下げたのでしか。
家族が家で過ごす時間が長くなったことにより、家事・育児の男女別役割はどう変わったのかがカギになります。
そもそも、子育て中の夫婦の間での家事・育児の分担具合が生活への満足度におおいに関連するのです。
第1回調査結果では、子どもを持つ家庭の約4割で夫の家事・育児へのかかわりが増えました。
テレワークは「生活に満足している」人を増やしましたが、、子どもをもつ母親には、あまりその傾向が見られませんでした。
つまり、家に子どもがいる状態でのテレワークでは、母親にとっては家事・育児の負担が軽くなるのではないということです。
第1回調査は、全国一斉休校中の時期に重なり、子どもが家にずっといたときに行われました。
第1回調査結果では、子どもを持つ家庭の約4割で夫の家事・育児へのかかわりが増えました。
テレワークは「生活に満足している」人を増やしましたが、、子どもをもつ母親には、あまりその傾向が見られませんでした。
つまり、家に子どもがいる状態でのテレワークでは、母親にとっては家事・育児の負担が軽くなるのではないということです。
第1回調査は、全国一斉休校中の時期に重なり、子どもが家にずっといたときに行われました。
女性が家事・育児を担う時間が多いのが日本の特徴ですが、休校によりさらに増えたのです。
要は、休校によって家事・育児の負担・ストレスが母親にのしかかり、生活の満足度が下がったということです。
育児の負担でいえば、通常時の平日には子どもが学校に通っている状態が、母親にとっては子育ての負担減になるのです。
学校は、子どもが学力をつけ、人間関係を学ぶ場であるのですが、四六時中でなく昼間の時間には母親から子どもを離すことが、母親にとってはちよっとした「息抜き」の時間をもたらすという学校の「役割」をあらためて知ることになりました。
しかし、その一方で、夫は自分に家事・育児の分担が増えたことに満足している傾向が見られます。
しかし、夫は家事をやっているつもりでも、妻はそれに満足できていないとも言えます。
このあたりに、男女のテレワークの受け止めのちがいが見てとれます。
要は、休校によって家事・育児の負担・ストレスが母親にのしかかり、生活の満足度が下がったということです。
育児の負担でいえば、通常時の平日には子どもが学校に通っている状態が、母親にとっては子育ての負担減になるのです。
学校は、子どもが学力をつけ、人間関係を学ぶ場であるのですが、四六時中でなく昼間の時間には母親から子どもを離すことが、母親にとってはちよっとした「息抜き」の時間をもたらすという学校の「役割」をあらためて知ることになりました。
しかし、その一方で、夫は自分に家事・育児の分担が増えたことに満足している傾向が見られます。
しかし、夫は家事をやっているつもりでも、妻はそれに満足できていないとも言えます。
このあたりに、男女のテレワークの受け止めのちがいが見てとれます。










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます