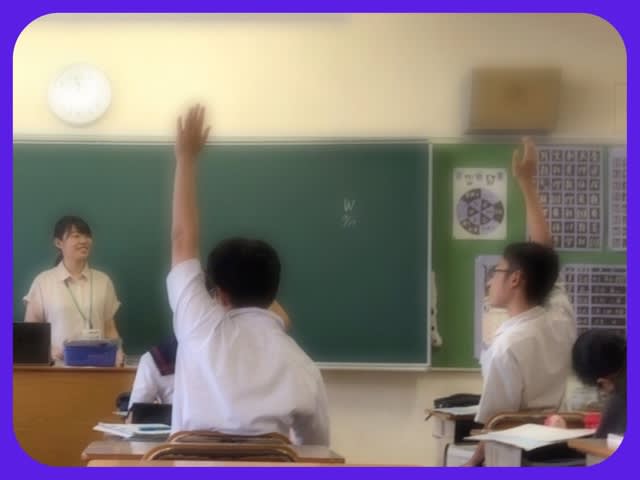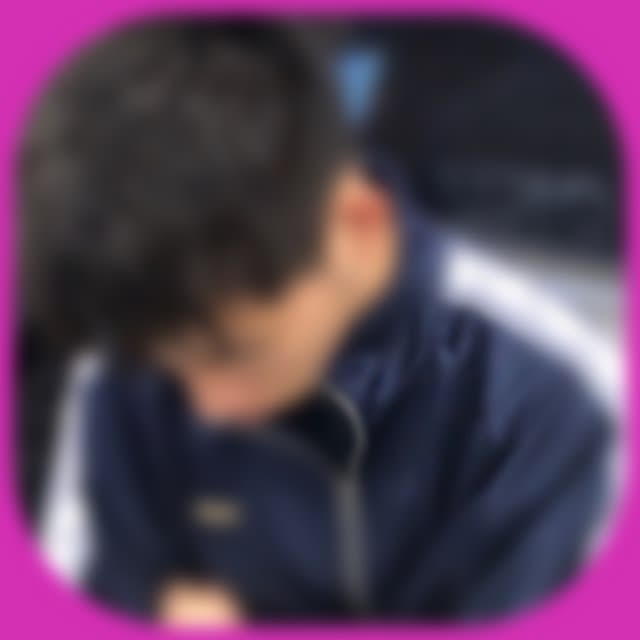日々、中学校生活を送る中学生ですが、同じ学校生活を送るなら、信頼できる教師がいた方がいいのです。
生徒が教師に信頼感を寄せるには、その前提条件として、教師という大人に対して期待していることが必要だと、前に述べました。(11月8日)
他にもあります。
生徒が教師には信頼感をもつには、教師はぜったいに生徒を裏切らないという自覚と実行力がいります。
裏切りは、相手から行われる行為です。
裏切られた側は大きく傷つきます。
誰もが傷つきたくありません。
だから、もし、たくさん裏切られた経験をすると、誰も信じないようになります。
浜崎あゆみの曲「Moments」の中に
こんな歌詞がありました。
「君が絶望という 名の淵に立たされ そこで見た景色はどんなものだったろう
行き場所を失くして さまよっている むき出しの心が 触れるのを恐れて 鋭い刺はり巡らせる
・・・」
人から裏切られると、鎧をつけ、誰も信じない、誰も好きにならないという生き方をしようとする人もいます。
そういう生徒に出会ったこともあります。
ただ、そのような生徒でも、心の奥底の深層心理では、人と信じ合いたいと、願っていることが多く、人と出会い直すことで、絶望が希望に変わることもあります。
その出会い直しは、教育の中で行われることがあります。
自身の経験からも思いますが、とにかく、教師は生徒をぜったい裏切らないことを肝に銘じ、振る舞うことが不可欠です。