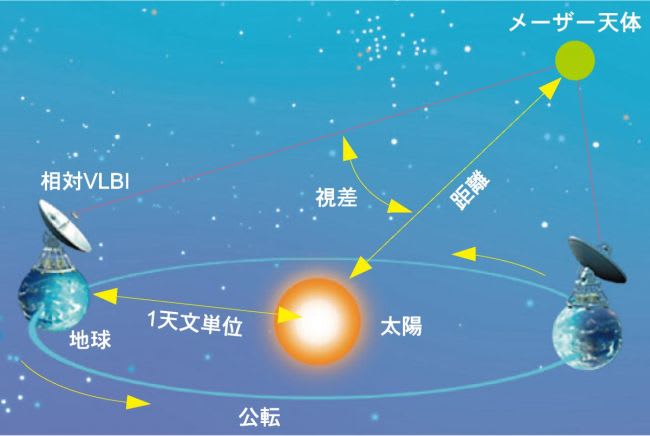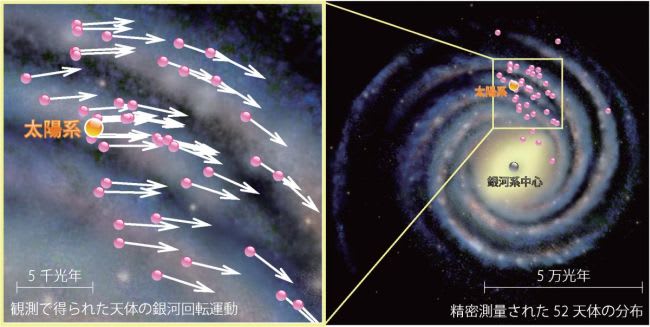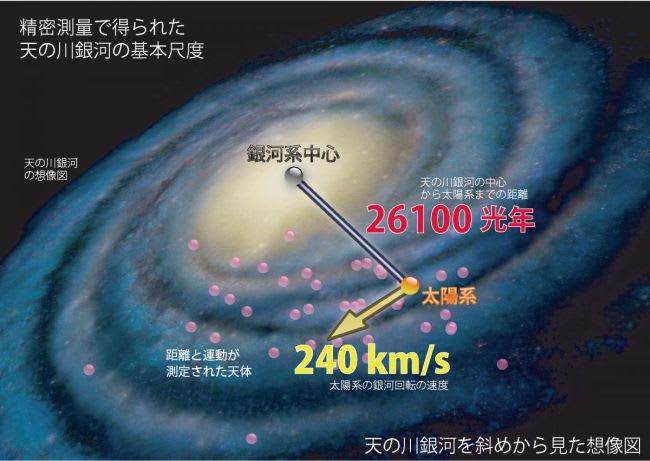欧州宇宙機関(ESA)の金星探査機“ビーナス・エクスプレス”が、金星の大気の中に二酸化炭素が凍ってしまうほど低温の大気層を発見しました。

金星の昼夜の境界域
金星の特長は分厚い二酸化炭素の大気と、とても高い表面温度(地表付近は500℃)です。
大きさは地球と似ているのですが、環境がかなり違うので「似て非なる双子」とも言われているんですねー
今回の研究では、金星を周回中の“ビーナス・エクスプレス”が集めた5年分の観測データを新たに解析しています。
この結果、高度125キロのところに、気温マイナス175℃という極低温の層があることが分かりました。
もちろん地球の大気には、これより低温の場所はありません。
金星が地球より太陽に近いことを考えると、とても不思議な現象なんですねー
極低温の層は、金星の大気を通過してくる太陽光を分析し、高度ごとの大気中の二酸化炭素分布を調べることで見つかっています。
二酸化炭素の分布データと、高度ごとの大気圧データを組み合わせて計算することで、大気の温度を推定できるんですねー
高度ごとの温度分布を見ると、ある高度では二酸化炭素が凍ってしまう温度まで下がっていることが分かります。
そこでは二酸化炭素の氷が発生しているようです。

昼夜の境界域での
大気の高度ごとの温度分布
高度130キロ付近で
温度が急激に下がっている
凍った二酸化炭素の粒は、光の反射率が高くなります。
なので、探査機で見つかる大気中の非常に明るい領域は、このような氷が原因かもしれません。
まぁー 大気の乱流による可能性もあるので、断定はできないのですが…
この研究では、この低温層が2つの高温層に挟まれていることも分かっているんですねー
高度120キロの大気は、昼側と夜側で極端に温度差があります。
その中間点にあたる昼夜の境界域では、低温の大気と高温の大気のせめぎ合いが起こっています。
高度ごとに、夜側の大気が優勢なところが低温層で、昼側の大気が優勢なところが高温層 っという感じです。
今回の研究結果は理論モデルと一致するのですが、
大気上層部で二酸化炭素よりも多く存在する、一酸化炭素や窒素などについても検証すれば、さらに確実なものになりそうです。
地球の昼夜の境界域では見られない不思議な現象が意味するものは?
温度分布や温度環境が違うと、想像を超える発見があるんですねー

金星の昼夜の境界域
金星の特長は分厚い二酸化炭素の大気と、とても高い表面温度(地表付近は500℃)です。
大きさは地球と似ているのですが、環境がかなり違うので「似て非なる双子」とも言われているんですねー
今回の研究では、金星を周回中の“ビーナス・エクスプレス”が集めた5年分の観測データを新たに解析しています。
この結果、高度125キロのところに、気温マイナス175℃という極低温の層があることが分かりました。
もちろん地球の大気には、これより低温の場所はありません。
金星が地球より太陽に近いことを考えると、とても不思議な現象なんですねー
極低温の層は、金星の大気を通過してくる太陽光を分析し、高度ごとの大気中の二酸化炭素分布を調べることで見つかっています。
二酸化炭素の分布データと、高度ごとの大気圧データを組み合わせて計算することで、大気の温度を推定できるんですねー
高度ごとの温度分布を見ると、ある高度では二酸化炭素が凍ってしまう温度まで下がっていることが分かります。
そこでは二酸化炭素の氷が発生しているようです。

昼夜の境界域での
大気の高度ごとの温度分布
高度130キロ付近で
温度が急激に下がっている
凍った二酸化炭素の粒は、光の反射率が高くなります。
なので、探査機で見つかる大気中の非常に明るい領域は、このような氷が原因かもしれません。
まぁー 大気の乱流による可能性もあるので、断定はできないのですが…
この研究では、この低温層が2つの高温層に挟まれていることも分かっているんですねー
高度120キロの大気は、昼側と夜側で極端に温度差があります。
その中間点にあたる昼夜の境界域では、低温の大気と高温の大気のせめぎ合いが起こっています。
高度ごとに、夜側の大気が優勢なところが低温層で、昼側の大気が優勢なところが高温層 っという感じです。
今回の研究結果は理論モデルと一致するのですが、
大気上層部で二酸化炭素よりも多く存在する、一酸化炭素や窒素などについても検証すれば、さらに確実なものになりそうです。
地球の昼夜の境界域では見られない不思議な現象が意味するものは?
温度分布や温度環境が違うと、想像を超える発見があるんですねー