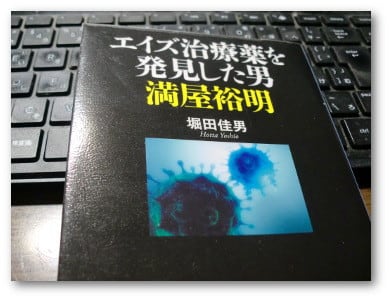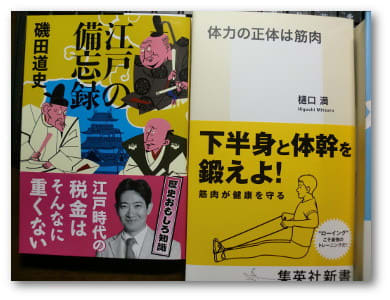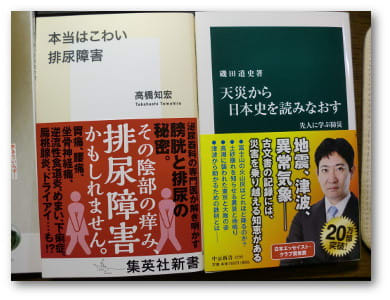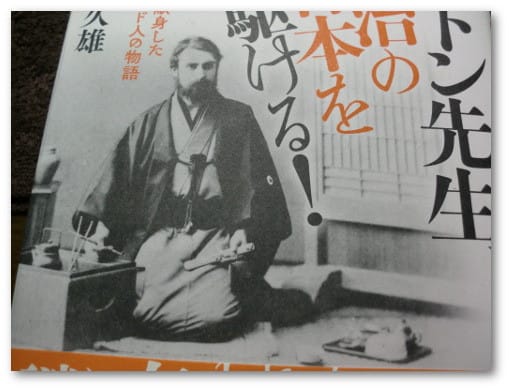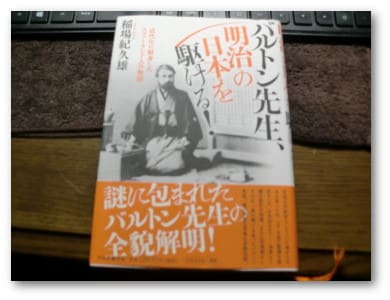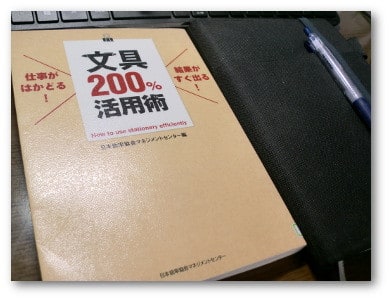今年、91歳になる老母は、先年の経カテーテル大動脈弁置換の心臓手術がうまくいき、歩行に不自由があるものの、幸いにぼけの症状は出ておりません。早寝早起き、畑仕事を楽しみながら毎日のように日記をつけ、自家栽培の野菜や果物を豊富にとるなど、健康的な生活習慣がプラスしているのだろうと思いますが、自分たちの「ぼけの予防」はどうすればよいのか、参考までに岩波新書で須貝佑一著『ぼけの予防』を読みました。2005年5月刊の赤版です。
本書の構成は次のとおり。
本書の「まえがき」に、次のような言葉がありました。
まさにそのとおりでしょう。病気になれば病院で面倒をみてくれる。家族は心配し、面会のたびにため息をつくけれど、認知症の場合はそんなレベルではないでしょう。在宅介護の場合の家族の負担はたいへんなものです。
認知症による知能の衰えは急激なもので、年のせいによる自然な老化とは明確に異なります。記憶や想起、見当識や判断力、思考や照合などの知的能力が急速に落ちていき、孤立や猜疑心、被害妄想、怒り、興奮などを伴うこともあるとのこと。認知症を起こす脳の病気はアルツハイマー病が50〜60%、脳血管性痴呆が30%、あとはレビー小体病、その他となりますが、甲状腺機能低下症や慢性肺疾患、糖尿病や肝硬変が原因となる場合もあるらしい。
早期発見により軽度のうちに治療すれば進行を抑えることができるので、精神科、とくに高齢者をよく診ているところが良いそうな。
ポイントとなるアルツハイマー病については、「忘れていることを忘れる」という病的な物忘れが特徴的で、発病から平均で8年、長くて10数年で死亡に至るとのこと。この期間、家族の葛藤は大変なものでしょう。原因についてはアミロイド・カスケード仮説を紹介し、神経細胞膜にセクレターゼが作用しアミロイドβたんぱくが生じますが、通常は分解されるものの、脳障害や活性酸素、アポE-ε4の存在等により脳内に蓄積、これが神経毒性をあらわし、神経細胞脱落にいたることでアルツハイマー病を発症する、という立場です。

そのため、活性酸素の処理システムの弱体化を防ぎ、酸化的ストレスを緩和するという意味で摂取カロリー制限、脂肪酸の種類や野菜、果物の効用など、食生活を改善することを重視しています。また、生活習慣として運動と頭の使い方、ストレスの軽減を図ることなども大切、という立場です。
○
残念ながら、アルツハイマー病と睡眠との関係、寝不足が続くとアミロイドβとタウが蓄積し、睡眠時に排出できなくなって蓄積してしまい、神経毒性を示してしまう、という記述(*1)はありませんでした。もしかしたら、これは本書刊行後の知見だったのかもしれません。その意味では、肝心の情報がないけれど周辺的な整理には役立ちましたが、本音を言えば、最新の情報を追加した改訂版がほしいところです。
(*1):「脳の老廃物」を除去するには、深い睡眠が必要だった:研究結果〜「WIRED」より
本書の構成は次のとおり。
I ぼけとは何か
「年のせい」と認知症の違い/認知症を起こす病気
II ぼけの診断
認知症の見つけ方/認知症を診てもらう方法
III アルツハイマー病の予防
アルツハイマー病とは?/食生活/嗜好品のとり方/生活習慣と頭の使い方/
薬とサプリメントの効用
IV ぼけ予防の先に見えるもの
本書の「まえがき」に、次のような言葉がありました。
がん、心臓病、脳卒中の三大生活習慣病ならどこの病院でもよくみてくれる。生活上で介護に負担がかかる、という事態は少ない。高齢化が進んで困ったことは認知症の増加である。
まさにそのとおりでしょう。病気になれば病院で面倒をみてくれる。家族は心配し、面会のたびにため息をつくけれど、認知症の場合はそんなレベルではないでしょう。在宅介護の場合の家族の負担はたいへんなものです。
認知症による知能の衰えは急激なもので、年のせいによる自然な老化とは明確に異なります。記憶や想起、見当識や判断力、思考や照合などの知的能力が急速に落ちていき、孤立や猜疑心、被害妄想、怒り、興奮などを伴うこともあるとのこと。認知症を起こす脳の病気はアルツハイマー病が50〜60%、脳血管性痴呆が30%、あとはレビー小体病、その他となりますが、甲状腺機能低下症や慢性肺疾患、糖尿病や肝硬変が原因となる場合もあるらしい。
早期発見により軽度のうちに治療すれば進行を抑えることができるので、精神科、とくに高齢者をよく診ているところが良いそうな。
ポイントとなるアルツハイマー病については、「忘れていることを忘れる」という病的な物忘れが特徴的で、発病から平均で8年、長くて10数年で死亡に至るとのこと。この期間、家族の葛藤は大変なものでしょう。原因についてはアミロイド・カスケード仮説を紹介し、神経細胞膜にセクレターゼが作用しアミロイドβたんぱくが生じますが、通常は分解されるものの、脳障害や活性酸素、アポE-ε4の存在等により脳内に蓄積、これが神経毒性をあらわし、神経細胞脱落にいたることでアルツハイマー病を発症する、という立場です。

そのため、活性酸素の処理システムの弱体化を防ぎ、酸化的ストレスを緩和するという意味で摂取カロリー制限、脂肪酸の種類や野菜、果物の効用など、食生活を改善することを重視しています。また、生活習慣として運動と頭の使い方、ストレスの軽減を図ることなども大切、という立場です。
○
残念ながら、アルツハイマー病と睡眠との関係、寝不足が続くとアミロイドβとタウが蓄積し、睡眠時に排出できなくなって蓄積してしまい、神経毒性を示してしまう、という記述(*1)はありませんでした。もしかしたら、これは本書刊行後の知見だったのかもしれません。その意味では、肝心の情報がないけれど周辺的な整理には役立ちましたが、本音を言えば、最新の情報を追加した改訂版がほしいところです。
(*1):「脳の老廃物」を除去するには、深い睡眠が必要だった:研究結果〜「WIRED」より